穴水町曽良は、深い湾と水路の風景から「東洋のベニス」と評する人もいた。富山湾のむこうに立山連峰をのぞむ海岸段丘上にある千手院では2009年から「曽良の盆灯」が催され、境内や集落の道沿いに最大1万ものロウソクがともった。【曽良の歩みはコチラ】
だが、千手院で「縄文焼き」をつくり「盆灯」を発案した新出良一さんが2017年に亡くなり、10回目の2018年を最後にイベントはとだえた。そして、主のいなくなった寺を2024年の地震が襲った。
カップ酒の瓶やロウソクどっさり

穴水町でガソリンスタンドを経営する森本敬一さんは景勝地の千手院を「復興ツーリズム」の拠点にしようと考えた。ボランティアとともに寺を掃除していると、盆灯でつかったカップ酒の瓶やろうそくがどっさりでてきた。2024年8月14日、千手院境内にロウソクをともす「復興の灯」(NPO法人「チーム能登喰いしん坊」主催)をもよおした。
翌2025年8月14日に開かれた第2回の「復興の灯」に私はおじゃました。
甲小学校に車をとめて10分ほど歩き曽良の集落に入った。千手院に近づくと、そろいのベストを着たボランティアたちが海辺にすわって、シシ肉のカレーやスイカをほおばっている。朝から周辺の草刈りをしてきたという。
よみがえった寺

千手院の古い建物は、床や天井の一部が腐り、いつ倒壊してもおかしくない状態だったが、震度6強にも耐えた。33年に一度開帳される本尊・千手観音が守ってくれたのかもしれない。

昨年の火文字は「NOTO NOT ALONE」だった。今年は「NOTO MOTTO COME ON」。境内には計800本のロウソクがともった。
本堂では地震後に住職になった北原蜜連さんが「御朱印」を書いている。寺は復活したのだ。

鐘楼の鐘をついて、玄関の鐘をガランガランと鳴らし、犠牲者追悼と復興祈願の法要がはじまった。真言宗のお経は音楽のよう。
「娯楽がなかった弘法大師の時代は、お経も音楽のように楽しんだのかもしれません」と北原さん。
光の万華鏡はタイムマシーン

建物などの立体物に映像を投影し、そこに三次元の像が浮かびあがるかのような錯覚を生み出す「プロジェクションマッピング」が本堂の内と外を彩る。


唐草模様かと思えば極彩色の熱帯林のようになり、海かと思えば空のイメージに変化する。本堂の外壁や内側、鐘楼や木々の枝にまで投影される。万華鏡のように、ひとつの図柄が崩れては次の図柄が浮かびあがる。


足が不自由な地元のおばあさんは、新出さんの指導でつくった縄文ランプシェードを今も大切にしているという。
「もう何十年前のことやろねぇ。あのころはにぎやかで楽しかったねぇ。笠をかぶった女の人が列をつくって集落のほうまで踊って歩いてねぇ……」
本堂から流れてくる北原さんのお経を聴きながら思い出話をする。別のおばあさんもうっとりと目を閉じて語った。
「ひさーしぶりにお寺さんに人が集まって、千手観音さんもきっとよろこんでるねぇ」

闇のなか、さまざまな色彩の光が次々に境内を彩ると、時がさかのぼり、千手院が生き生きとしていた時代にさかのぼるように思えてくる。


何十年か前は、白衣を着て集落を托鉢する「寒修行」の子が千手院につどった。10年前には、新出さんがつくった縄文焼きのランプシェードが本堂にずらりとならんだ。海沿いの道を「おわら風の盆」の踊り手たちがユラユラ踊り歩いた……。


豊かな悲しみを実感
私は、縄文土器のランタンを本堂にならべて火をともす新出さんの姿と、「あばれ祭り」の日に宇出津の彼の家におじゃまして、「祭りの日は警察もとりしまらんから大丈夫や」とごちそうをいただいたことを走馬灯のように思いだした。そんな新出さん夫妻ももういない。


午後8時すぎ、法要が終わると「スカイランタン」を打ち上げる。闇夜にするするとのぼっていく黄色い明かりのはるか上には天の川がまたたいていた。

年をとると、夢や可能性を失うかわりに思い出が蓄積される。祭りやお盆は、過ぎ去った記憶をよみがえらせ、自分も死者の側に近づきつつあることを実感させてくれる。能登のお盆は、そんな豊かな悲しみ(哀しみ)をしみじみと感じさせてくれる。
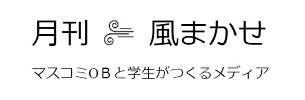

















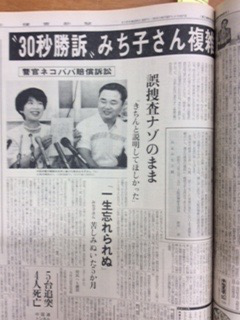
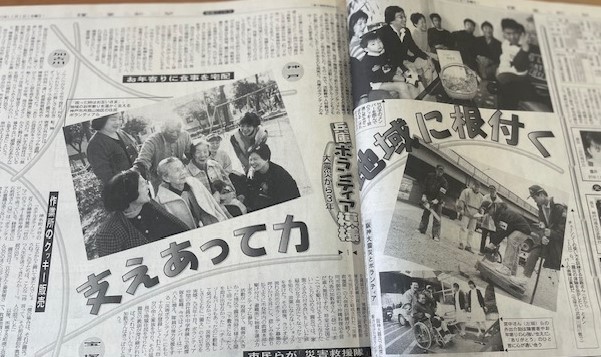
コメント