松江支局で、事件記者の第一歩を踏み出す
新人記者の1日は早い。鬼の支局長に言われたこと。まず、「警察担当記者に休みはない。いつでも出動できる準備をしておけ」。次に「朝は、遅くても午前7時からのNHKのニュースを聞け」「それから、警察署の当直が代わる前の8時15分には、所轄署に行って、事件の有無を確認しろ」だった。これは、かなりしんどかった。しかし、やらねばならない。事件記者になるためだ。ああ、ちなみに、今頃言うことだけど、1970年代当時は、ほとんどの新聞記者は事件記者になりたかった。今は全然違うけど。
しかし、そんな聖人君子のような新聞記者はいない、ほぼ。「まあ、やりますけど」という体でサツ回りを続けた。松江署の副署長にも、そこそこ挨拶がてらに話をしてもらええるようになり、副署長の隣にいる総務課の美人職員に会うのが唯一の楽しみだった。当時、当然のことだが、所轄署の刑事一課や二課のデカ部屋に新聞記者は入れた。かなり嫌味を言われながらも、刑事一課長や二課長の前までは。刑事一課の部屋に入れるが、刑事一課長の前にしか立てない。後ろには数十人の刑事たちが座ってはいるが。しかし、課長は若造記者などの扱いはお手のものだ。ポーカーフェイスでのらりくらりと話をはぐらかす。課長と話をしながら、後ろの席の様子を探る。上の空で課長と話していると、刑事たちから「おい、お前、背中がダンボの耳になってるぞ」と突っ込まれる。
まあ、それでも刑事課に入るのは、ネタを取るためではない、と分かったのは後になってからだ。本当は、「普段の刑事課」(要するに大きな事件がない)と「特別な刑事課」を嗅ぎ分けるために毎日のように入室するのだ。通い続けているうちに、妙に刑事課が浮足立っている、なんか雰囲気がいつもと違うな?と感じるようになる。それが仕事だ。また、本当に毎日真面目に通っていると、そこは人間、本来なら口を効いてはいけない係長やベテランの刑事たちが軽口をたたくようになったものだ。
対して、当時は隣接していた県警本部は堅苦しい。本部長に警務部長、刑事部長、監察官などのお偉いさんがズラリといる。もちろん、対面可能だが、そんなに話すことはない。ルーティンで回るのは、捜査一課や二課だ。ここでも課長さんは偉いので、主に記者の対応を受け持つのは、次長。同じ刑事さんでも、所轄の刑事と県警本部の刑事さんでは、「保秘」がきつく、口が重い。
悪名高き「記者クラブ」も県警本部内にあった。当時は2階の道路に面した100㎡以上の広い部屋だった。加盟社は、当時の机の並び順に思い出すと、読売、日本海テレビ、NHK、山陰中央テレビ、山陰中央新報、朝日、日本海、産経、山陰放送、毎日、中国新聞の11社だったと記憶する。ここに、わが読売新聞は3人も所属し、他社も複数人配置していたから、20数人が毎日、出入りしていた。ここにいると、基本的には、島根県内で起きた大きな事件や事故の情報が提供される。だから、ほとんどの記者たちは、ここに「出社」し、事件事故がなければ、麻雀や花札(主にコイコイと呼ばれる花札ゲーム)に興じていた。当時は、警察の建物内で現金を賭けていたと白状する。
要するに、記者クラブにいれば、県内の大きな事件事故の発生を落とすことはないし、逮捕事案も広報される、まことにありがたいシステムだ。しかし、駆け出しの若い記者たち、それも将来は東京や大阪本社に上がって、事件記者をやりたいと内心で思っている記者たちにとっては、「甘い巣窟」でしかない。若い記者たちは、麻雀や花札に興じながら、隙を見て「特ダネ」を取りに行く。その基本は、やはり、「夜討ち、朝駆け」であり、検察庁回りだ。夜討ち朝駆けは、新聞記者が単純に憧れて使う言葉だ。
松江支局の先輩記者たち
しかし、田舎の県警では、夜討ち朝駆けは無用だ。事実、支局で夜グズグズしていると、I支局長が言った。「夜回りに行って来い!おれも、海兵隊にいたころ、高い跳び箱を飛べなくて、ビビッていたが、えいっ、と飛んだ。夜回りも一緒だ」。なんのこっちゃ?と思いながら、警察官官舎に着いた。捜査一課の刑事さんの部屋が3階にあった。午後8時過ぎ。ピンポーンとチャイムを鳴らした。「ハイ」と奥さんらしい人の返事が。「あっ、読売新聞の安富と申します。夜回りに来ました」(なんと間抜けな)。奥さん「主人はもう寝ました」。ちゃんちゃん。跳び箱を飛べなかった。
仕方がないので、先輩たちが待つ支局近くのおでん屋さんに行く。先輩2人は「松江で夜回りしてもしょうがないよ」と慰めてくれ、お酒の強いM先輩はコップ酒の日本酒をぐいぐいとあおる。K先輩はビールをぐいぐいと飲む。仕方ないので。筆者も飲む。すると、K先輩が言う。「Mのコップ酒の数を数えとけよ。10杯過ぎたら要注意や」。10杯を超えたM先輩は明らかに表情も口調も変わった。突然、グローブのような掌でバンバンと背中をたたき、「お前も関西人やったら、もう少し上手にやれよ!」。M先輩は大阪市の出身で、K先輩は大分県国東半島の出身。それから、カラオケスナックに連れて行かれて、演歌を強要された。
全国特ダネを目指すが…
そんな生活を繰り返しながらも、月日は流れてゆく。大社会部の事件記者になりたい身としては、同期の動きが気になる。早い記者なら1年生のうちに全国版に特ダネ記事を放ち、地方部長賞(賞金1万円だった)を獲得する者が出てくる。筆者は全国版特ダネどころか、地方版(島根版)にさえ特ダネを書けない。発表記事や街ダネ(学校や交番を訪ねて話題のある記事を書くこと)で島根版を埋めているだけだ。
それでも、少しずつだが記事が載るようになる。(冒頭の写真は昭和54年6月16日と18日付け記事、上の16日付けがデビュー記事かな) また頭が痛いことが増えた。記事を書いて(あっ、これも大事なことなのだが、当時それぞれの新聞社ごとに独特の原稿用紙があり、鉛筆かボールペンで記事を書いていた。出先で書いた記事を、アルバイトが自転車で取りに来た)、支局では次席と呼ばれるデスクが原稿をチェックして、表現や言い回しを新聞記事的に直して出稿する。新人記者は当然、原稿が下手だし、誤字脱字が多く、次席や時々原稿を見る支局長に叱られた。特に支局長はひどい。「しん(本名は信でまことと読むのだがこう呼ばれた)、なんだ、この原稿は!それでも最高学府、それも同志社大学が出た学士が書く原稿かあ!」。訳が分からない。

まさか? 先輩が!
そんな生活を続けていたある日、衝撃的な「特ダネ」が飛び込んできた。松江署刑事一課の部屋を訪れ、いつものように、どうでもよい雑談をしていた時、ある巡査部長が「そういや、君とこの先輩M君、全然ここにこないな。なんでか、知っているか?」と意味深な質問が。周りの刑事たちもニヤニヤ笑っているだけ。夜、支局に帰ってK先輩に聞いたら、これまた意味深な表情で「とうとう聞いたか?」と苦笑いを浮かべ、締め切り後、支局近くのおでん屋で真相を聞かされた。
びっくりした。かの先輩は筆者が赴任する約1年前、いつものように酔っ払って帰宅途中、風呂に入りたくなった。ふと見ると、民家の風呂場が見えた。壁をひょいと乗り越えてなぜか施錠がされていなかった風呂に入ってしまった。そこへ、この家の主婦が入って来て、ギャーッ、当然110番。駆け付けた松江署の刑事さんは驚いた。「読売のMやないか!」。パトカーに乗せられ松江署の留置場に入れられた。いわゆるトラ箱である。しかし、現住建造物侵入の立派な刑法犯だ。本人は泥酔状態で全く前後不覚だったらしい。
知らせを受けてデスクや先輩がおっとり刀で駆け付け、身元引受人になって連れて帰った、という。今なら、さしずめ、逮捕され、新聞発表され、ひょっとしたら、懲戒解雇だろう。いや、当時でも多分、現行犯逮捕だったのだろう、寛大な処分になった。松江署どころか県警本部も知るところになり、当然、他社の記者たちも知ったという。それが、1年後には一種の笑い話になっている。おおらかな時代である。ちなみにM先輩はその後、事件記者となり、部長職も経て無事読売の記者人生を全うされ、某大学の教授を歴任された。(つづく)
やすとみ・まこと
神戸学院大現代社会学部社会防災学科教授
社団法人・日本避難所支援機構代表理事

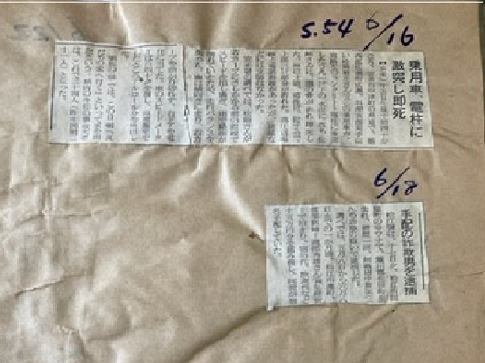





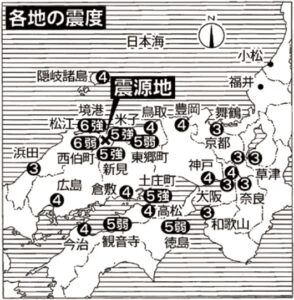
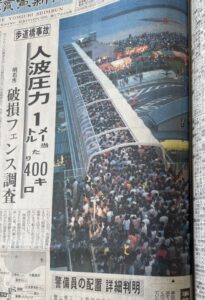













コメント