高校野球、地方版は「運動面」に
いよいよ、松江編も終盤を迎えて来たが、駆け出し時代でやはり忘れられないトピックとしては、高校野球取材を抜きにしては語れない。今回は松江「番外編」と題して、夏の高校野球の地方大会取材から、代表校に同行して甲子園まで取材した熱い夏を描きたい。
春の選抜は毎日新聞、夏の大会は朝日新聞の主催。なぜ、読売新聞がそんなに力を入れて、高校野球を熱心に取材し、地方版で主催者の朝日と同じくらいか、場合によっては朝日より大きく記事を扱ったのか?
それは、夏の甲子園は無理にしても、春の選抜大会は、ある時期毎日から本気で奪取する気があったように思う。そんな時代が昭和50年代から平成の初めごろまであった。筆者が松江で勤務していた頃は当にその時代の真ん中だった。
梅雨末期の7月20日を過ぎると、毎年夏の甲子園出場を目指して島根県予選が始まる。
当時の参加校は30校、8日間ほどの日程で優勝を争い、県代表の1校が夢の甲子園に出る。
この間、1年から3年生までの記者とカメラマンが連日、球場に行き、全試合を詳報する。スコアボードからテーブル記録、戦評に加えて、スタンドの応援団やチアリーダーの様子も伝える。ヒーローを取り上げる「ファイト」というコラム欄もあり、島根版見開きで展開する紙面はまるで運動面のプロ野球コーナーだった。朝日の記者から「どっちが主催者かわからんね」などと揶揄されたものだ。

「宇宙間を破る三塁打」「本塁への送りバント」
筆者は生来の阪神ファンで野球大好き人間だったから、高校野球もお手のモノだった。
毎日朝早くから車で1時間以上かけて県立浜山球場に通い、真っ黒になって取材・執筆に勤しんだ。
球場のバックネット裏には記者室があり、朝日は別室だったが、毎日、産経、中国、山陰中央新報と読売の記者が入り乱れてワイワイガヤガヤとスコアブックを付けたり、写真を撮ったりした。そうそう、支局勤務になって直ぐに、先輩からスコアブックの付け方を教わる“特別授業”が開かれるほどだ。球場にはFAXがないので、試合が終わるたびに、支局に電話して原稿を吹き込む。
こちらは一応、訓練を積んでいるが、支局のパンチャーさんは野球の素人が多く、時に笑い話が生じる。
球場から「3回、〇〇が右中間を破る3塁打を放って2点先制」と読んだのだが、支局に戻って原稿をチェックすると、「宇宙間を破る3塁打」となっていた。時には、スクイズの意味が分からず、「本塁への送りバントのようなもの」などと説明したことも
甲子園取材は同年代記者の「他流試合」
そうした地方予選取材が終わると、本番の甲子園取材となる。
各支局から主に2~4年生記者たちが集まり、取材チームは、夏の大会ならば、本社のデスク数人と大阪本社管内の支局だけでなく東京、西部本社からも応援が来て総勢20数人くらいの大所帯になった。
どこに泊まるか? 筆者が甲子園取材班に入った頃は、甲子園球場のライトスタンドの場外そばにある素戔嗚(すさのお)神社が宿泊所だった。社務所広間(50畳ほどの広さだったかな、もう少し狭かったかも)に20人以上の男たちが20日近く寝泊まりした。(後に球場近くのホテルが宿舎になったが、多分、10年以上はここでお世話になった)
まあ若かったから、この合宿生活はそれなりに楽しかった。
数年前に支局に配属になってから久しぶりの同期に会える機会でもあり、また、先輩・後輩たちと一緒に仕事が出来る、同年代の「他流試合」みたいなものだった。
支局代表でもあるので、支局長からは「ちゃんと仕事して来いよ」とプレッシャーをかけられた。もっと言えば、早く本社に上がりたい記者にとっては腕の見せ所でもあった。
しかし、まあ、久しぶりに“都会”に戻って来た喜びもあり、皆がはしゃぎ回っていた暑い夏だった。
松田聖子の「夏の罪」?
代表校が島根を出発する時から同じ列車、新幹線に乗り込む「同行取材」をし、甲子園近くの宿舎に着いてからも毎日、取材に行き、練習風景だけでなく、選手たちの宿舎での生活も詳報する。
試合が始まると、代表チームの試合経過を書く(これを本記と呼ぶ)が、他校の取材もする。初めて甲子園取材に参加した頃は、アルプススタンドで朝から夕方まで、次々来る応援団や両親、親戚、関係者たちに取材をして「雑感」という10行から20行までの記事を何本も書く。
ブラスバンドの奏でる曲が頭の中でぐるぐる回った。コンバットマーチに進撃ラッパ、ルパン三世のテーマ、、、。チャンスになると必ず演奏される山本リンダの「狙い撃ち」や「ウララ、ウララ」は夢にまで出てきた。
こんな替え歌が取材班で流行った。
「本記かしら? いいえ、雑感さ![]() 」。島倉千代子のヒット曲をもじって。
」。島倉千代子のヒット曲をもじって。
ある日、同期の上杉茂樹記者(故人)が書いた雑感記事が、夜の食事会(全員長机を囲んで)でやり玉に挙がった。デスクが言った。「上杉君、夏の罪ってどんな歌やねん?」
うん?と不思議そうな顔。
「今日、君が書いた雑感記事のことや」
アルプススタンドで何度も演奏される松田聖子の「夏の扉」のことを書いたのだが、「扉」が「罪」になっていたのだ。夏の扉は聖子ちゃんが昭和56年4月に発表した大ヒット作で、ノリが良かったのでその年の夏の甲子園で鳴り響いた。読売甲子園取材班ではその曲は密かに「夏の罪」と呼ばれた。
球場の取材に入らない日もあった。
「宿舎回り」と言って勝ち残ったチームが次の試合までの「空きの日」に宿舎を訪れ、練習風景などを地方版用に送るのだが、この日は記者たちにとって待ちに待った日だ。
たいていの記者が取材をそこそこにして、早めにデスクに原稿を出して遊びに出る。ちょっとした「休養日」だ。若い記者たちは大阪か神戸にある歓楽街に2,3人組で繰り出す。夕食までに帰舎しなければならないが、デスクもある程度大目に見てくれた。中には夕食を済ませてから出かけて、門限(夜11時だったかな?)までに帰って来た。
中には豪傑もいた。1つ下の後輩2人は出る前から「安富さん、ぼくたち今夜、神戸の方まで遊びに行きます。もし、門限に間に合わなかったら窓に石をぶつけますから、開けてください」と言う。厚かましい後輩だ。
果たして当の2人はきっちりと遅刻し、打ち合せ通り、招き入れたが、しっかりとバレていた。

筆者が同行してきた代表チームは、儚く1回戦で敗退した。
中には、帰局させられる記者がいる中、何とか決勝戦まで居残った。
昭和56年、初めて行った甲子園は第63回大会だった。決勝戦は今も脳裏に残っている。
兵庫県代表報徳学園対京都府代表京都商業(現京都学園)。報徳学園のエースで4番は近鉄球団で活躍した金村義明選手。準決勝でソフトバンク監督を務めた大投手・工藤公康を擁する名電工(現愛工大明電)を3対0で破って決勝に進出。対する京都商業のエースは「小さな大投手、沢村2世」と呼ばれた井口和人選手。168㎝と小柄ながら甲子園ではバッタバッタと三振を取り、3試合連続完封を果たしていた。
軽やかに朗らかに原稿を書くすごい記者
この試合で、その後40年以上も仲良くしている武部好伸さん(現、フリーライター、作家)とネット裏の記者室で席を並べた。
武部さんは京都商業の本記担当で筆者は報徳学園担当だった。
武部さんは1年先輩。身内に本社関係者もいないしバイト上がりでもなかったのに、初任地が京都支局(現総局)という大阪読売期待の若手記者だった。
噂は聞いていたが実感した。
筆が早い! 文章が上手い! 時折、横目で見る原稿からすぐに伝わって来た。凄い記者はいっぱいいるのだ! と実感した。それも、軽やかに朗らかに原稿を書く。
因みに、この時の取材班には1年上の優秀な先輩たちが沢山いた。
最後は読売新聞大阪本社副社長にまで上り詰めたUさん(大阪読売生え抜きの記者は社長にはなれなくて、それまでは常務か専務止まりだったがUさんは初めて副社長になった)。早くに亡くなられたが文化部の名文記者として名を馳せたIさん。取材班の中で一番気の合ったNさん(後に親友となって結婚式に来てもらったが、「冗談はよせ」という一言だけが挨拶だった)。


同期では、先の「夏の罪」の上杉記者。彼は後に同期№1というより、前後十数年の記者の中でも極めて優秀な特ダネ記者になったが、40歳になる前に東京のテレビ局TBSにヘッドハンティングされて転職、50歳になるかならない時に早世した。
その他、後に尼僧? になった、今で言えばLGBT宣言のS記者や、文化部で活躍したY記者らがいた。
先に書いたように、この取材班を手柄のひとつにして一日も早い本社を目指す筆者のような勘違い記者もいたが、Uさんは不機嫌だった。彼はすでに初任地の松山支局で事件に強い記者に成長していた。盲目を装って保険金をだまし取っていた男の犯行を暴いた特ダネは有名で、さらに追い続けている事件もあった。
「オレ、ここでこんなことをしている場合やないんや」とぼやいていた。
Uさんは、その後、本社社会部でいつも筆者の1年上として君臨し、後に書くことになるが、社会部大阪府警担当時代は、彼は同期の上杉記者と共に捜査2課担当、筆者は捜査1課担当。いつも言われた。
「安富君は松江でMさんと遊びすぎたね。もっと真面目に仕事せんとアカンよ」
ほっといてくれ!
この後、春の選抜を含めて連続5回甲子園出場を果たした。デスクになってからも2回行った。当時のN地方部長が「君は野球が好きか? 運動部に行くか?」と打診してきたこともあった。事件記者になりたかったので、丁重にお断りした。(つづく)










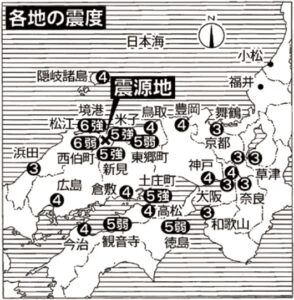
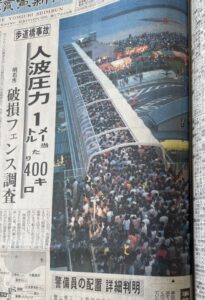










コメント