帰省客でにぎわう砂浜は…

2015年以来10年ぶりにお盆を能登ですごした。公費解体が進み、だだっ広くなった輪島の街から袖ヶ浜にでるとミンミンゼミとツクツクボウシの声につつまれる。地震の3カ月後は浜は多くのゴミがたまっていたが、今は地震前の夏のようにきれいに掃除され、帰省客らしい3、4人の若者が波とたわむれている。来年には海水浴客がもどってくることだろう。

海と市街を望む山上にたつ温泉旅館「八汐」は解体工事がはじまっている。町内会の人たちとカラオケをうたい、夏休みには弟の一家にごちそうをふるまった。思い出深い宿はまもなく消える。
隆起した岩場を歩いて土砂に埋まった道を迂回し、鴨ケ浦の岩礁へ。隆起で水を失った「塩水プール」から外海をながめると、舳倉島と七ツ島がくっきりと浮かんでいる。地震以来孤立したままの軽自動車は布で包まれている。

手掘りの「木の葉トンネル」に入るとひんやりする。夏、ジョギングをしてこのトンネルに入ったときの肌感覚だ。砂浜に出るとふたたび汗をかき、海に飛びこみ、服ごとシャワーをあびて家まで走ってビールをあおった。ごくあたりまえのそんな日常が幸せだったのだ。能登の人たちはみなそう実感している。
セミ時雨で頭がボーッとして、にぎやかだった「夏休み」が幻影のように脳裏にたちあらわれる。
オトミさん、3代目に

街にもどって住吉神社を参拝する。鳳至の街は更地だらけになり、神社の鳥居も倒壊したままだが、今年は祭りを催すらしい。かつて境内では毎日「夕市」が開かれていた。出店は2,3軒だが、パンチパーマのオトミさんが出刃包丁をふるって魚を三枚におろしていた。昼に揚がったばかりのシコシコの刺身をあてに地酒「千枚田」をあおった。オトミさんと娘のれいこさんが今にもあらわれそうに思える。

オトミさんは震災後、2次避難先で亡くなったが、れいこさんは最近輪島にもどってきて、魚の販売をはじめたらしい。祖母と母の呼称「オトミ」を今はれいこさんが継いでいるという。
冷やしたぬき

夏の昼食には「旭そば」の「冷やしたぬきそば」をよく食べた。手打ちでもなんでもないふつうの麵だけど、冷たくて甘めの汁はくせになった。輪島を代表するB級グルメだった。地震後、本店も支店も更地になり、店のあった場所がわからなくなったが、炎天下の街を歩いていたら、あの汁のにおいがした気がして「ここだ!」と直感的に店の位置がわかった。

花壇のように華やかな出前寿司

朝日新聞輪島支局は職住兼用の一軒家だった。子づれの友人が遊びにくると、しばしば「助ずし」から出前を頼んだ。オヤジと息子が握っていたが、2人の寿司のちがいはすぐにわかった。息子はまだ修業中だったのだろう。


地震でも3階建ての店舗兼住宅は倒れなかった。だが後継者の息子を数年前に失ったオヤジさんは再建をあきらめてしまった。更地になった助ずし跡を歩くと、色とりどりの花壇のように美しかった寿司桶と白髪頭のオヤジを思いだした。
「お盆」の強い日差しの下、けだるい風景のすき間から、過去の記憶や亡き人がわきだしてくる。輪島の街は過去の豊かな彩りのなかに生きている。
先人から学ぶお盆

輪島の漁師町・輪島崎では戦後、地域の民主化運動がおこり、「輪島海美味工房」の新木順子さんの義母らが漁協の女性部を創設した。
漁師町の女性の資質向上をはかるため、義母は、市議会や県議会の傍聴に母ちゃんたちをつれていき、見聞を広めるための視察研修にも力を入れた。「役所にしたがうだけでなく、ちゃんと筋を通して物を言うように」というのが口癖だった。
新木の家に嫁いだ順子さんは保育所につとめていたが、「公民館で女性部の総会するからきてくれ」と呼ばれて出席し、女性部長にまつりあげられた。
「ばあちゃんにも、漁村の資質向上はかれ、と尻をたたかれた。ばあちゃんは階段の上り下りができなくなっても『会議がある』と言うと『いってらっしゃい』と言う。お昼ごはんはどうする? って尋ねると、『昼ぐらい食べんでも死なんわいね』って」
新木さんは義母にならって、視察研修を重視し、石鹸販売や海浜清掃にも力を入れてきた。戦後の輪島崎の女性のシンボルのような存在だった義母は103歳まで生きた。
新木さん宅では、毎年お盆には先祖の写真を壁面にずらりとならべて、先人の歩みをふりかえってきた。四畳半の仮設住宅ではそれはかなわないが、地震後の避難所生活では「ばあちゃん」たちが育んだ地域力のありがたみを実感した。
人は死んでも、その人が積みあげたものは生きつづける。それを実感できるのが「お盆」なのかもしれない。
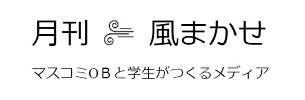

















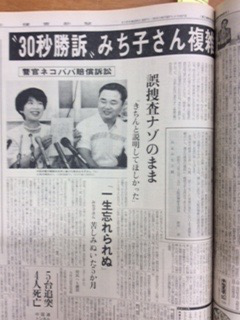

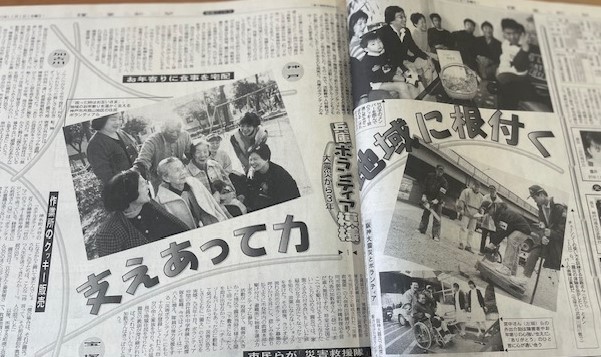
コメント