能登半島最北端の禄剛崎にほど近い横山集落は、2024年元日の能登半島地震後もほとんどの住民が地区にとどまった。
地震から4カ月後の4月末に訪ねると、水田のパイプラインが破断し、農道がくずれて山の畑にたどりつけなかった。5月には田植えをして大豆の種をまかなければならず、全壊した乾燥・調整施設を8月末までに復旧しなければ収穫物をくさらせてしまう。二三味義春さんは、市役所や県庁に早期の対応をくりかえし訴えていた。【2024年4月までの記録→】
その後、大浜大豆の畑や水田はどうなったのだろうか。2025年8月、二三味さんを訪ねた。
農道の応急修理
2024年春、大豆と小豆、ソバの各8町歩(ヘクタール)の畑への農道は崩れていたが、畑への途中に集落の浄水場があったから市が早期に対応することになった。だが畑の作業場までに段差ができて車が通れない。
「バラス(砂利)がダンプに2台もありゃいけるわい。バラスをくれ」
市役所に電話すると、
「バラスがないげー」
「知り合いからもらって請求書をまわすわ」
知人の建設業者からバラスを入手した。
ところが浄水場の手前の水道管の埋まっている個所が新たに陥没した。
「たのむ。管のうまってるところが陥没してしまってるさけ、今晩のあいだになおさないけん。あんたんところのバラスを貸してくれ」
市役所の担当者が電話をかけてきた。
「どんだけでも貸すけど、おらとこもはやいところ直してくれ」と言うと、畑までの農道も修理してくれた。
30枚の畑のうち27枚は、段差や亀裂ができている。ユンボで段差を崩して52日間かけて整地した。5月末までに大豆、7月に小豆、8月にソバの種をまいた。
ところが9月に豪雨が襲う。大豆は無事だったが、水田の一部が水没し、泥やごみが流れこんで収穫は3割減った。ソバや小豆はほぼ全滅した。2025年も、ソバは種まき直後の大雨で大半が流されてしまった。

政治の力で早期に対応
山の畑の作業場にあった乾燥・調整施設の復旧はどうなったのか。
農地・農業用施設の災害復旧には費用の9割を補助する制度があるが、建物の規模も機械も「現状復帰」でなければならない。申請しても「見積書を3社からもらえ」と言われる。人手不足で業者も見積もりをする余裕はない。
旧知の業者に「収穫まであと2カ月しかない。あんたに建ててもらうさかい、あとは建てるばかりにしといてくれ」とたのんだが、「地震になっても建物をたてる許可はだいたい1年後や。そんな早くおりるわけねー」と言われた。
市役所の知人は「あんたの状況はよおわかるけど、上から決まったことはオラでは曲げられん。上にどんどん言いな」と言う。
旧知の国会議員秘書は能登に思い入れがあり、地震後も「なんかあったら言えや」と声をかけてくれていた。6月30日に電話すると「要望を3点にまとめろ」と言う。
「完全に書類をつくって、申請して審査していたら遅くなってしまう。書類は後付けにしてほしい」「『現状復帰』は難しい。ある程度ゆるめてほしい」などと要望した。
7月4日、畑仕事をしていると、市役所の知人から電話があった。
「おーい、狼煙のヤクザ! 北陸農政局から県から大騒ぎになっとるぞ」
5日夕方、農水省の担当者から電話がかかってきた。
「二三味さん、あんたの要望に添ったような形で調整しました。市の担当に電話して内容を聞いてください。簡単に言うと、役場の係の人が、この人のこの要望なら認めてもよい、ということなら通るようにしました」
一気に手続きが進み、着工にこぎつけた。5月にさかのぼって申請したことにして、書類は後付けでよいことになった。
年内の復旧を無理だとあきらめていた農家にも「無理やと言ったけど、なんとかなるかもわからん」と役所から連絡がとどいた。
建設を担当する業者はさらにびっくりした。
「ふつうは早くて1年後や。なんでこんな早いことになったんや」
東京の本社の役員が事情を聴きにやってきた。
「なんで能登半島の先っちょにいて、そんな政治家を知ってるんですか」と驚かれた。
乾燥・調整施設は総工費2億円をかけて10月に完成した。地震前には山の上の畑にあったが、農道が崩れたため、道の駅「狼煙」から横山の集会所にむかう建造沿いにうつした。
稲刈りにはまにあわず、トラック2台を購入して農協のライスセンターなど4カ所に運んで乾燥してもらった。ソバや大豆の収穫には間に合った。

れいわ新撰組の山本太郎が地震直後に被災地を視察した際、維新の音喜多駿は「山本太郎氏が発信・提案している内容は、既知のもの」にすぎず、渋滞などの負担を被災地にかけてまで発信すべき情報ではない……などとののしった。二三味さんの要望を農水省に伝えた自民党政治家やれいわの山本太郎の「現場」を重視する姿と比べると、音喜多の薄っぺらさが浮き彫りになった。
「紙の家」で集落に残る
横山の住民は37人だが、体が動かない1人が施設にはいった以外は全員が横山に残っている。3人が入居した仮設住宅も地区内にある。
自宅が全壊になった女性はビニールハウスで暮らしていた。
二三味さんは市長に電話した。
「コンテナを家にして補助金がおりるがけ? 一人暮らしで、ビニールハウスで寝起きしているけど、朝になると暑いし、雨が降るとバタバタでかわいそうや」
「あしたまで待ってくれ。1年前の5月5日の地震で、(建築家の)坂茂さんの紙の家を正院に1軒たてた。つかってなかったらもらえるかもしれん」
正院地区は大半の家が倒壊したり傾いたりしたが「紙の家」は今回の地震でもビクともしなかった。
1時間後に市長から電話がかかってきた。
「建てる許可をとったらから、本当にほしいか聞いてくれ」
坂茂さんとボランティアの学生が建てた紙の家のおかげで、女性は横山に住みつづけられることになった。
「道の駅」引き継ぎ
道の駅「狼煙」の運営をになう「株式会社のろし」は、住民が出資して設立され、社員とパート7人ほどがはたらく貴重な雇用の場だった。
だが新型コロナや2023年5月5日の地震被害からたちなおりかけたところに元日の地震が襲った。4月から一部営業を再開したが9月の豪雨による断水でふたたび閉鎖した。
「地元の人に、だれか経営せい、と言ってもみんな『おとろしい』とひきうけなかった。ちょっこりかわった人じゃないと無理やわ」と二三味さん。
2025年4月、金沢市で民泊事業などを営む男性が経営を引き継いだ。7月から再開し、週3日(金・土・日)営業している。
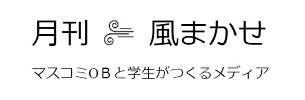
















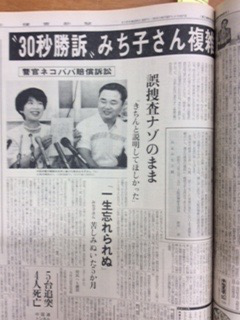

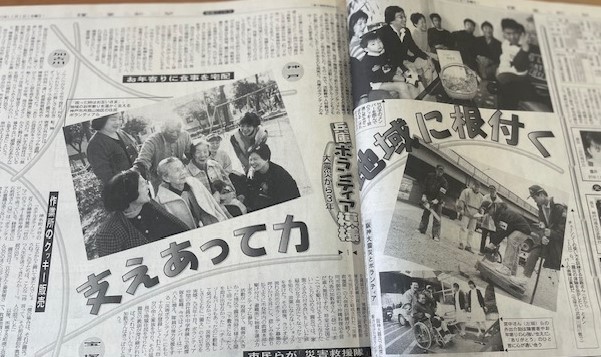
コメント