実はこの回、62回目だったのです。本来は。それが諸般の事情で、一旦公開して、各氏にメッセンジャーやLINEでお送りしたのだが、すぐに公開を延期しました。多くの方から、「見れない」とお叱りを受けました。申し訳ない。諸般の事情とは、大人の事情でした。つまり、内輪で仕入れたネタを書けない。公になってないからだった。それは人事だから。やっと異動先の取締役会が終わったので、元の文章を下地に少し書き直しました。それでも、かなりハレーションを含む内容になっているので、おっかなびっくりの番外編です。
屈指の元事件記者、熊本へ
6月14日付読売新聞朝刊2面に読売新聞グループの人事異動が掲載された。もう何の関係もないのだが、古巣の異動記事にはつい目が行ってしまう。特に大阪本社関係は。毎月送られて来る社報も一般記事はほとんど読まないが、人事面だけは必ず目を通す。もちろん、後輩たちの動向が気になるのだが。紙面を見て気になったことがある。30年ほど前に京都総局で3席をしていた時や、阪神・淡路大震災が起きた1995年に阪神支局次席をしていた時に、若く優秀な記者だった二河伊知郎さんが執行役員編集局長になられるようだ。おめでとうございます。それはいいのだが、前任の編集局長・松尾徳彦さんがどこに行くのか、紙面にはない。事情に詳しい者に聞いた。異動先は読売新聞グループ系列局で熊本県民テレビの取締役報道局長という。前任者はこの連載でも紹介した、一課担の同僚永田広道さん。永田さんは熊本出身だが、松尾さんは縁もゆかりもないはずだ。
どうやら柴田岳・大阪本社現社長とそりが合わないという。よくある話だし、筆者もそういう噂は聞いていた。そもそも松尾さんは一課担の後輩で読売新聞大阪本社でも屈指の事件記者だ。柴田社長は東京本社政治部の出身。関西ジャーナリズム(古いか!)の何たるかも微塵も知らない東京の偉いさんが松尾さんの矜持を理解できるはずもない。古巣の新聞社の幹部人事ではここ数年、同じような話を何度も聞く。松尾さんはこの異動を喜んでいると聞くが。
東京のマイナスパワーで大阪読売弱体化?
まあ、サラリーマンの社会ではどこにでもある話だが、全員出自が新聞記者と言う点で、極めて違和感と言うか虚脱感を抱く。最近の大阪読売の紙面に総じて「元気」や「力」がないと感じるのは、こうした東京の“圧力”というか、力を削ぐマイナスパワーのようなものが働いているからではないか?と思っている。多くの大阪読売のOBもそう感じているのでは?
さらに、同年代の幹部らも数人退職する。もちろん定年を迎える歳だから、当然なのだが、3年下のH、M、4年下のY各氏らだ。この年代で生き残ったのは、3年下の足達新氏だけだ。専務取締役総務局長と紙面にある。ほとんど全員が取材を共にした人たちだから、「一つの時代が終わったんだな」と感慨深い。ついでに書けば、筆者の同期3人も退職し、これで大阪読売昭和54年同期は全員いなくなった。7月にささやかなご苦労さん会が開かれるという。
新聞社の人事は奇妙なものだ、と今になって思う。現役の頃は当たり前だと思っていたが、よく考えると変だ。若い頃は新聞記者として同じような仕事をしていたのが、月日を経るに従って記者からデスクになって、次長→部長→局次長→局長と幹部社員になっていく。順調なら。しかし、その過程で、なかなかデスク作業に慣れない記者、デスクになりたくない記者がいて、“出世”が遅れる。さらに、部長、局長と階段を上るうちに、人心を掌握する能力がないとか、セクハラやパワハラをやらかすなどして、次第に外れて行く者が出る。そうやって生き残った元新聞記者が執行役員から取締役員、常務や専務、副社長となる。大阪読売の社長は生え抜きの社長はいないから、せいぜい副社長が生え抜きのトップなのだが。
10人から20人、バブル期の最も多い時期で30数人の同期の中から、役員クラスになれるのは1人か2人、期によっては筆者の同期のように役員はおろか局長も一人もいない期もある。面白いもので、期によって「優秀だ」と先輩方から褒められる期もあれば、昭和54年組などは「1年上は超優秀だが、君らは最低だ」と言われ続けた。53年、57年、59年と、昭和50年代の入社では奇数年が「優秀」と言われた。後の人事でもほぼその通りになっている。松尾さんは59年、専務の足達さんは57年組だ。要するに、数ある同期の中でトップを極めたということだ。ちなみに53年組の植松実氏は副社長になった。
初心忘れ経営陣めざす「元記者」
何をダラダラ書いているのか。要は、新聞記者として社会のひずみや悲哀、政治の裏側などを見つめ続けて、取材し、原稿に書き、世に問うてきた記者たちが40歳、いや30歳代半ばから、出世のコースに乗るか乗らないかで選別され、生き残った者が次第に経営陣の一員となるのだ。事実、筆者も支局長時代、「支局長は経営を学べ」と言われて、首を傾げた記憶がある。そんなことを含めて早々と読売を辞めた武部好伸さんには見習うべきことが多い。筆者は結局、58歳まで居座ったものだから。
記者は記者であって、経営のノウハウなど学んでいないし、新聞記者になった当初、社長や役員になりたいなどと思う記者は1人もいないと信じる。いや、今頃はいるか? 精々、編集局長になって自分の紙面づくりをしたいと思う若い記者はいるが、経営陣になりたいのではない。それが、何年か会社にいるうちに、役員や経営陣を目指すようになる。サラリーマンなのだから当然なのだが。これは読売新聞だけでない、朝日も毎日も産経も日経もだ。今の朝日新聞の凋落ぶりを見るに、記者出身の経営陣の“迷走”があるのでは?と考える。もちろん、筆者も40歳代半ごろまで、この道を闇雲に走っていたのだから、偉そうなことは言えない。幸いにも、部下を掌握する能力がなく、パワハラ、セクハラを繰り返していたので、晩年は経営陣ではなく、編集委員になって原稿を書けるようになった。
今、講演会などで経歴を紹介する時、「編集委員」と言えば、ほとんどが社説などを書く論説委員と勘違いする。論説委員は社の幹部に上るためのポストとなるが、編集委員は「記者の成れの果て」と照れ隠しで表現する。「生涯一記者」と言う理想に近いポストだし、実際に東京本社に筆者が「編集委員になりたい」と思わせた本物の編集委員鶴岡憲一さんがいた。本社にいれば編集委員、地方では支局や通信部で記事を書くのが理想だろう。今の大阪読売の後輩でも、地方支局や通信部で「シニア記者」として黙々と記事を書いている記者がたくさんいる。筆者が毎朝読む三田版には、高部真一さんや竹村文之さんが毎日のように記事を書いている。それはそれで幸せな記者人生だと信じたい。
ナベツネは「戦争しない平和な国」を求めた?
そんな折、NHKのBS1スペシャルで放送されたのを書籍化した「独占告白 渡辺恒雄-戦後政治はこうして作られたー」(新潮社)という本を書店で見つけた。あっという間に読み進め、数時間で読了した。ある意味で凄い書物で、渡辺恒雄・読売新聞グループ本社代表取締役主筆(97)の意外な一面を見た思いだった。それは、一種感慨深い思いだった。ナベツネは若い時から「経営者」だった。いや、政治家というか政治家以上にこの国を作ろうとしてきた。ナベツネは鼻から新聞記者ではなかった。そう思った。だから、ナベツネは別格なのだ。世間一般的には、今の読売新聞は政権寄りの右寄りの論調だとされ、筆者は苦々しく思っている。しかし、これは別に、読売新聞グループの総帥ナベツネが、経営陣にそういう風に指示しているのではない、とこの本を読んで確信した。ナベツネは自民党や政権がどうのこうというより、どうすれば日本の国が良くなるか? 戦争しない平和な国で居続けられるにはどうしたらいいか?を考えているように読めた。
つまり、今の読売新聞東京本社や大阪本社が毎日出している新聞の論調は必ずしも、ナベツネの意向が反映されている訳ではないのだ。他の経営陣が忖度した紙面を作っているつもりになっているだけだと。そう考えると、なんとなくホッとするのだが。違うかな?(つづく)










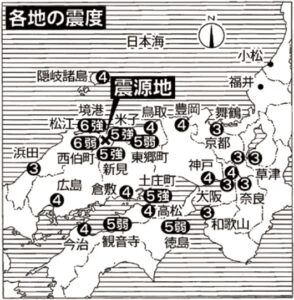
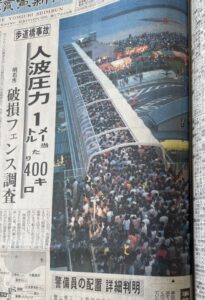









コメント