判決記事、朝日の1年生記者に「抜かれる」
「抜いた、抜かれた」。新聞記者の一番怖い言葉が「抜かれた」で、一番嬉しい言葉が「抜いた」だ。これは、今も昔も変わらないだろう。結論から言えば、38年間の新聞記者生活で、ほとんどが、「抜かれた」だった。
その最初の大きな抜かれ記事が、昭和55年2月4日。厳密に言えば、私が抜かれたのではない。2年先輩のWさんが裁判担当だったので、と今も言い訳するのが弱い新聞記者の証拠だ。少し難しい内容だったが、画期的な裁判の判決記事だった。詳しくは後回しにして、何で公開の裁判で抜かれたのか? というか、朝日新聞の特ダネになったのか。それも、筆者の同期の記者の1年生記者の。その当時、まだファックスも浸透していない時代だったから、他社の特ダネは「早版交換」という関西地区独特のシステムでわかった。深夜に大阪本社の全国紙4紙(朝毎読産)で早版と呼ばれる島根や高知県に行く早刷りの新聞を大阪駅近くで交換するというシステムだ。もちろん、重大な特ダネなら、「交換停止」で拒否もできるが、朝日は交換した。
「公訴棄却」という極めて画期的な判決を広島高裁松江支部の藤原吉備彦裁判長(当時)が出した。簡単に言えば、この4年前に行われた隣県の鳥取県赤碕町の町長選挙で、公職選挙法違反(買収、被買収)に問われた被告に対し、「当選した町長らの買収の証拠隠滅が明らかなのに、警察が町長らを送検せずに、検察庁も起訴しなかった。これは法の下の平等を定めた憲法第14条に違反し、公訴自体が無効である」として、公訴を棄却した。つまり、起訴された被告人だけを罪に問うのは、他の選挙違反者がいるのに、公平ではない。憲法違反だという画期的な判断である。
「公訴棄却」を「控訴棄却」と勘違い
公判なのに、なぜ、朝日の特ダネになったのか? この判決は、朝日新聞記者だけでなく、他社(読売新聞も含む)のほとんどの記者が傍聴していた。しかし、裁判長が発した「公訴棄却(こうそききゃく)」という単語を記者たちは「控訴棄却(こうそききゃく)」と判断した。つまり、控訴棄却なら、一審の鳥取地裁の有罪判決が支持され、記事としてあまり価値がないから、他社の記者たちは引き上げて行ったという。しかし、朝日の記者は居眠りをしていて判決の言い渡しを聞き逃した。ところが、目を覚ますと、他社の記者はいないのに裁判は続いている。藤原裁判長が延々と判決理由を述べている。「おかしいな」と思って、言い渡しが終わって弁護士に聞くと、「きわめて画期的な判決だ」とわかった。記者は先輩の応援を得て翌日の一面トップ記事に仕立てた、という。ちなみに、夜遅く朝日の特ダネ連絡を受けた他社は、大阪本社や東京本社近くに配られる最終版までには、事実確認をして、記事を突っ込んだ。以下の記事は翌々日1日遅れで島根県に来た読売新聞のスクラップだ。
ところで、この話の裏付けを取るために最近、読売や朝日のデータベースを調べたところ、同じ裁判長の画期的な判決がこの3か月の間に2件もあり、判決内容について、内容を混同していたことがわかった。もう一つの裁判は、公選法の戸別訪問を憲法違反だと判断したもので、どちらの裁判もかなりリベラルなこの裁判官が高裁段階で画期的な判決を出したのだ。最高裁段階で同様の判断がなされたということを後に聞いたことがないので、高裁止まりの判断だったのだろう。それに巻き込まれてしまったのも、若いころの勉強になったということだ。しかし、今にしてよく考えていれば、事前によく調べていれば、画期的な判決が出ることも予測できたのかな?とも思うが、それも駆け出し時代の貴重な教訓だ。
1日100行執筆、誤字脱字ナンバー2
そんなこんなで、2年目の記者時代が過ぎてゆく。警察回りをしながら、街の話題もの、地域版の連載記事などを毎日書いて過ごす。事件も少しは発生するが、基本的には山陰の小さな県でいつもいつもそんな大事件は起きない。火事や交通事故などで取材、執筆を重ねて少しずつだが成長してゆくのが、支局の生活だ。支局長やデスクに毎日毎日叱責されながら。原稿を書くと、当然、誤字脱字、間違った用法などが出てくる。外回りから帰ってきたら、壁いっぱいに誤字脱字原稿の元原稿が張り出されていた。最も多いのは、毎日300行(当時の新聞記事は1行15字だったから4500字以上)書いていた25歳上のベテラン主任さんだったが、2番手はなんと私だった、というのもご愛敬かな? ちなみに私の平均出稿量は1日100行程度だった。
娘に保険金をかけ殺害図った母
昭和55年12月半ば。いつものように、島根県警2階の記者室で、花札か麻雀に興じていた夕方だったと記憶する。少しひょうきんな面もある広報官(警視)がふらっと記者室に入って来て、室内をぶらぶらと歩きながら、「松江市内で一人娘に6000万円の保険をかけて、知人に殺人を依頼した母親の事件が発覚。殺しを頼まれた男が逮捕された」と“広報”した。
「えっ!なんやて!」。記者室は騒然となった。すぐに、隣の松江署に走り、2階の刑事1課長に詰め寄った。刑事1課長は用意していた紙を読み上げる。「母親は?」「どこかに逃げていない」「娘は無事なのか?」「殺し屋は粘着テープなどを準備して計画を練ったが、犯行を誘った別の男が逡巡して、そのうちに当署に垂れ込んできた。娘は無事だ」。凶悪事件なのに、何とも田舎らしいユーモラスな事件だ。失笑が起きた。53歳の無職男性は、殺人予備の疑いで松江署に逮捕された。
問題は、殺しを依頼したという母親だ。ところが、未遂でもなく殺害を計画した段階で逮捕されたため、殺人予備の罪に教唆はないという司法判断で、母親の逮捕は見送られた。松江署の刑事たちは切歯扼腕しながら母親逮捕の証拠を見つけようと懸命に捜査を続けていた。殺し屋逮捕から約2週間が過ぎた日の午後、筆者は松江署の刑事一課の部屋で刑事らとのんびりとテレビを見ていた。お昼のワイドショー。顔にぼかしが入った若い女性がインタビューに答えていた。「ハイ、私、あの逮捕された殺し屋に実際に殺されかけたことがありました」。20人以上の刑事たちが椅子を蹴飛ばして外に飛び出して行った。
なんのことはない、既に殺人未遂事件を起こしていたのだ。それを東京のテレビに抜かれたのだ。正午過ぎにやっていた人気のワイドショー、「そうなんです。川崎さん」というやり取りが有名な番組である。松江署は数日間の捜査を経て1週間後の大みそかの夜、母親を逮捕した。翌昭和56年1月1日元旦の朝の読売新聞大阪本社発行の早版(四国や山陰地方に届けられる新聞)の社会面トップに、猫を抱いたこの母親の写真とともに、「鬼の母逮捕」という大きな見出しが躍った。
逮捕前日、猫を抱く母親を撮影
なぜ猫を抱いた写真が掲載されたのか? もちろん、警察が提供してくれたのではない。これは、マスコミがよくやる予定稿づくりの一環だ。つまり、警察が逮捕する前に、容疑者になると見られる人物に事前に取材をする。例えば「松江署があなたを逮捕しようとしてますよ。心当たりはありますか?」などと言った質問をぶつけて、その反応を取る。同時に、逮捕された時点で、新聞掲載するための写真も本人の承諾を得て撮影する。逮捕の発表があった時点で、この写真を掲載することができるという訳だ。最近は、テレビなどでよく見るが、本人には内緒で隠し撮りするケースもある。道義的には良くないことだが、新聞社や週刊誌などもよくやる手法だ。この時は逮捕の1日前に、彼女の自宅を訪ねると、意外にあっさりと室内に招かれて、夫と共に取材に答えてくれ、写真撮影もOKだった。もちろん、事件への関与は完全否定だった。朝日の新人記者が一緒だったので、仕方なく同一取材となったので、翌々日の朝日新聞も社会面トップ記事で、被疑者は猫を抱いていた。
残念ながら、筆者はこの頃、スクラップをサボっており、切り抜きが見当たらず、データベースにも「猫を抱いた」写真が見当たらない。
この事件は、この後、思いもよらない展開を見せることになり、他の事件とともに、強力なライバルが出現することになるが、それは次回以降に。(つづく)
やすとみ・まこと 神戸学院大現代社会学部社会防災学科教授 社団法人・日本避難所支援機構代表理事













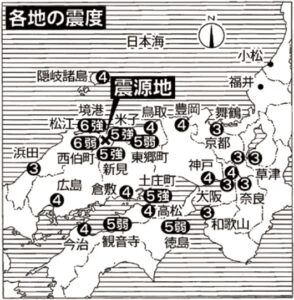
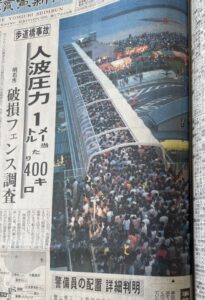










コメント