昭和の高度成長期、岩波映画製作所によって『年輪の秘密』と題された短編記録映画シリーズが製作されました。あまたの戦乱や災害、時代の変遷という試練にあっても、連綿といとなまれてきた日本の伝統産業・技術・芸能・習俗を記録した作品集です。時を重ねて成長する、巨木の年輪に例えた秀逸なシリーズタイトルです(後に〈日本文化シリーズ〉に名称変更)。
その一編に「輪島塗」(1959・昭和34年)があります。職人さんたちによる椀づくりのほかに、かつて輪島でおこなわれていた漆の樹液採集の様子や、つるはしを手にした能登珪藻土の採掘、地の粉の燻焼の様子、高度成長期の塗師屋の繁忙ぶりが当時の情景とともに収められ、今観るなら文化的・社会的に大変貴重な映像記録になっています。


この映画で記録されている塗師屋職人たちの仕事ぶりをみていると、私たちが今撮影している輪島塗技術者・坂下光宏さんの手の動きとほとんど違わぬものだということを実感します。漆の調合。糊漆の練り方。下地漆を器物にのばしていく箆の動かし方。上塗の際の椀刷毛の通し方…。
つくるうつわの数や造形こそ異なるかもしれませんが、時代を超えて受け継がれる手仕事の奥深さが伝わってきます。坂下さんは明治中期に創業した坂下漆器店の三代目です。それゆえ伝統的な輪島塗の技術へのこだわりは強く、震災にあっても高い矜持を保ち続けているのだと思います。

「修理ができるようになるにはまず新品のうつわをつくる力量がなければならないんです」と坂下さんは言います。うつわの傷の深さを見極めるため、器面の表層から下地へ、時には木地が見えるまで漆を削り取っていく。それはつまり、対象となるうつわの制作工程を遡って調べていくことにほかなりません。往時の職人はどんな素材で、どのような技法で作ったのか。その腕の良し悪しは。それらを判断するためには新品のうつわをつくるだけの知見と技術、経験―つまり力量が必要なのだ、というわけです。
そこで私たち映画スタッフの学びのためにも、坂下さんに新品の飯椀制作をお願いし撮影することにしました。輪島塗の工程は非常に多いため、ここでは特に下地制作を撮影する際に見聞きし感じたことを書いていこうと思います。
●糊漆
輪島塗の下地を施すにあたって、その基礎となる漆は糊漆です。米糊と生漆を混ぜて練り、そこに地の粉を加えて下地漆をつくるのです。

米糊ですが、米粒(うるち米)を水に浸して柔らかくしてから煮る場合と、米粒を挽いて上新粉のようにしてから水を加えて煮る場合があります。坂下さんは前者の方法で作ります。

「この米糊と生漆がとても相性がいいというか、反応が良くて強い接着効果が生まれるんです」と坂下さん。そして下地仕事のしやすさと仕上がり具合は米糊で決まるとさえ言います。
米糊は使用する量が多いため、輪島にはかつて糊屋がありました。漆器を大量に生産する塗師屋は米糊の製造や管理の手間を惜しんで、糊屋から買い求めていたのです。その糊屋は現在輪島に一軒もありません。ですから技術者たちはお手製の米糊をつくらなければならないのですが、水加減やねばりなど、つくり方が案外シビアなのです。坂下さんは下地に先がけて、まず米糊のレシピを記録しなくちゃ次代の人の役に立たないと仰いました。
●下地つけ

「本堅地」と呼ばれる輪島塗の下地は一般的に三辺地まで塗り重ねる。



箆の素材は指物や曲輪木地でも使われる能登アテ
下地の工程では塗った漆を研ぐ場面が何度も出てきます(下地に限らず上塗を除くすべての漆塗工程の節目には研ぎがあります)。
せっかく丁寧な下地づけができているのに何で?と最初は思ったのですが、器面に近づいて見てみると塗ムラやわずかな起伏があることに気づきます。これらは後々うつわの堅牢さに影響する急所となります。熟練の技術者による箆さばきでも、均一な厚みで漆を塗ることは不可能です。だから砥石で研いで修正する。修正することを前提として下地漆を塗るのです。
「それだけでなく、研ぐということは直前までの工程を一度リセットして次の工程を重ねていくということでもあるんです」(坂下さん)


椀には様々な「面」があります。外側と内側に加え、底にしつらえてある高台や、高台がくりぬかれた内側は糸底といった具合に。面と面が交わる部分は角や隅ができるので、そこをくっきりと密着させるために、下地漆を面ごとにつけていくのです。

一つの面に下地をつけたら漆を乾燥、硬化させないと次の面にとりかかれません。そのため乾燥のための時間を設けることになります。夏なら一日あれば乾きますが冬なら数日かかることもあります。その間、技術者は手を休めて乾燥を待ちます。
漆塗りのことを工芸では髹漆(きゅうしつ)という言葉であらわします。髹は髪を休ませると書きます。漆刷毛は人の毛髪を束ねたもので出来ていますから、刷毛を休ませながら(漆の乾燥を待ちながら)おこなうのが漆仕事の本質なのだということを表現しているのだと思います。
輪島塗はこの面ごとの作業を一工程としてカウントします。輪島塗の工程数の多さと長期にわたる制作期間は有名ですが、子細に見ると実に細やかな作業の積み重ねで成り立っているのだということがわかるのです。

●地縁引き
他の漆器産地にはなく、輪島塗独自の技法に立ち会うこともありました。
椀の口縁部は木地が薄く、落下の衝撃やご飯をいただく時、口があたる部分でもあるので傷みやすい箇所です。そういったところには木地の上に麻布を糊漆で貼ってクッション処理を施し(布着せといってこれは他産地でもおこなわれている工程です)、その上に下地をつけていくのですが、輪島塗ではさらに下地つけの直後に生漆をしみこませるのです。「地縁引き」といいます。

地の粉を顕微鏡で見ると、粒に微細な気泡状の穴がたくさん空いています(珪藻土が原料だからでしょう)。その穴に生漆を入れることで地の粉そのものの硬化が進み、下地の強度が上がるのです。

…とまるで専門家の受け売りみたいなことを書きましたが、顕微鏡で地の粉の粒を見ることなんてできなかった先人たちはどうしてこんな技法を考えたのでしょうか。しかも地縁引き専用の箆はアテの樹皮を細かくほぐしたものがいいとか、その箆をあてる角度や動かし方とか、力加減とか…先人たちは長持ちで丈夫なうつわをつくるため、どんな試行錯誤を繰り返してきたのか。そう思うと、苦労とともに費やされた年月の重さに頭が下がります。
柔らかい下地漆がのったうつわの上縁を撫でるように進む桧皮箆の美しさをカメラは接写で追いかけます。工房の外では隣接する仮設住宅の工事が急ピッチで進んでいました。

「美術品みたいに展示するだけならこんな手間をかける必要はありません。木地に生漆をしみ込ませて固めたうえに色漆で上塗をすればそれでいいんです。
輪島塗は使ってなんぼの器です。使うときにおこる様々なトラブルを想定して、対処できるようあらかじめ新品の時点で防御策が仕込んである。だから手間と時間がかかるんです。対価もかかるんですけど一生ものですから、と自信をもって勧めています」(坂下さん)。
輪島塗は完成するとその下にどんな仕事をしたのかが見えなくなります。この見えない部分、秘められた場所にこそ、伝統に裏付けられた技術が息づいているのです。しかしこれを逆にとれば、見えないことによっていい加減な仕事が通用してしまうという、品質に結び付く問題を抱えることになります。
「漆器の品質は時間が経つとわかってくる。大切に使ってたのに突然漆が剥離したとか。ひび割れしたとか。自分がまだ生きていれば修繕できるけど、死んだ後も漆器は残る。使われるんです。未来の使い手が自分が手掛けた漆器を見てどんなことを思ったり、言われるか。そう考えるととても怖い仕事なんですよ」(坂下さん)
坂下さんの先輩で輪島塗技術保存会の仲間である惣田登志樹さんは半世紀以上にわたって輪島塗のあゆみを間近で見ながら仕事をしてきました。

惣田さんは輪島塗の未来にとって脅威なのは、バブル期以降の低迷から抜け出せないまま高齢化が進んだ業界全体の低迷と、材料原価の高騰、しっかりとした技術を受け継ぐ人材の枯渇にあると以前から仰っていて、過日に掲載された新聞記事にも同様の主張をされています。
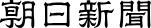
思えば輪島塗が重要無形文化財に指定されたのは、国がその技術の保護に乗り出さなければ、近い未来には途絶えてしまうという危機的な状況にあったからでした。震災や豪雨災害によって、よりその危機は迫ってきています。工房が損壊しても、すきま風が吹き込んでも、先人たちが研ぎ澄ませてきた技術を絶やさず次代につなげていく、そのような強い意志が坂下さんから伝わってくる時があります。その意志と共鳴するためにもまず彼の技術を凝視したい。能登の地で2024年に重ねられた、年輪の模様を記録したいと思っています。
井上実(記録映画演出)

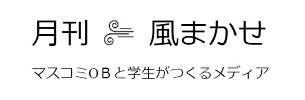




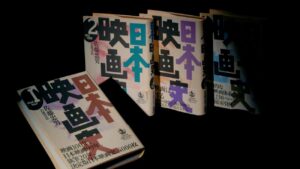

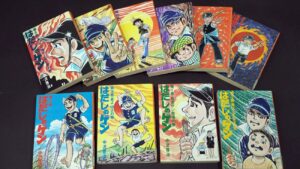











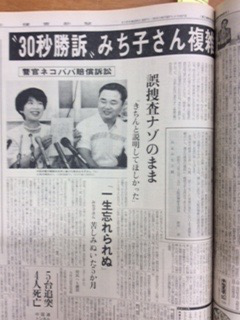

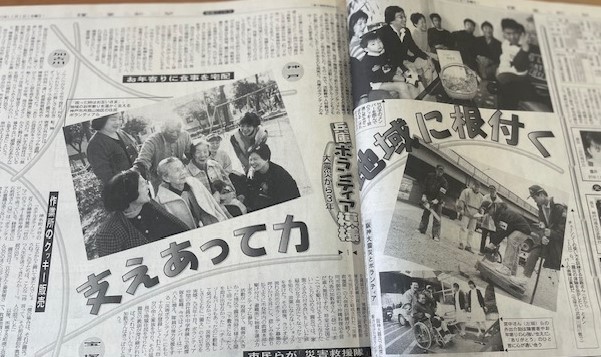
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] (つづく) […]