「数千人の殺人事件」泣きながら読んだデスク陣
やっぱり1回では終わらない。阪神・淡路大震災をもう1回だけ書きます。
地震が発生した平成7年(1995)1月17日は前述のように、バタバタ、ドタバタととにかく、若手の記者たちが取材して書いて来たものを、ちぎっては投げちぎっては投げの状態で、本社社会部へファックスした。翌日がどんな紙面になったのか、よく覚えていない。17日夜になって、行方不明になっていた中島広支局長が支局に到着し、社会部から次から次へと記者がやって来た。
当時、社会部阪神支局は阪神尼崎駅から北へ500mほど、国道2号線を北にすぐ、安藤病院の北隣にあった。被害が酷かった芦屋や西宮、宝塚、伊丹、川西各市に比べて、尼崎は比較的被害は少なかった。なので、電気、ガスはもちろん、上下水道もすぐに復旧した。当時の支局は3階建てで、1階が編集フロア(150㎡くらいかな)、2階が会議室、3階に支局長住宅があった。そこへ社会部や他本社、東京、西部(九州)からの応援取材も多く来て一番多い時で、50人以上の記者でごった返した。
座れる机は10ほどしかなく、フロアに座って記事を書く人、2階の会議室で書く人、それぞれだった。翌日からは、社会部の応援デスクとして、加藤譲、江崎丈両次長に、真鍋和彦主任が来て、筆者も入れて4人体制で原稿を見た。
本記というか、地震の被害やライフラインの復旧などの硬派的な記事は主に県庁がある神戸総局が担当した。神戸総局は当時、阪急花隈駅近くの、これも3階建ての古い総局だった。ここに、大阪本社地方部の若手記者や、他本社、他部などから総勢100人以上が来た、という。
阪神支局は、主に軟派記事を受け持った。社会面に掲載される喜怒哀楽あふれる記事だ。当然、愛する子どもを亡くした父母、兄弟を亡くした子、両親や祖父母を亡くした人、教え子を失った教師、友だち、恩師が亡くなった人、、、色んなドラマがあった。捜査一課担の大先輩記者の加藤次長は言った。「亡くなった人、数千人。それぞれの人生があった。ひとり一人の悔しさを胸に記事を書いてくれ。数千人の殺人事件だ」。こう言われた記者たちは毎日毎日、悲しい記事を書いて来た。記事を読む最初の読者である、デスク陣は涙を流しながら読んだ。
ラブホに泊まった記者50人
50人もの記者たちは、どこに泊まったのか? 阪神支局のすぐ裏にラブホテル街があった。水は出るし、お風呂にも入れる。若い記者たちは2人1組で部屋に入った。女性記者も何人かいたが、差別なくラブホ泊まり。100人もいた神戸総局は有馬温泉に宿を取ったが、温泉は止まっていたし、総局からタクシーで30分ほどかかるので、毎夜4時ごろに寝て、6時起床の生活だったらしい。2時には朝刊が締め切られていたが、それから翌日の取材打ち合わせと称する反省会が毎日1時間以上、開かれたという。若い記者が多く、取材上の心構えや注意があったのだろうが、それにしても、シンドイことだ。
翻って、阪神支局には中堅からベテランの記者が多く、いちいち心構えなんか要らなかった。2時に終わると、簡単な打ち合わせをして解散! 中には2階の会議室にあった卓球台で深夜遅くまで卓球に興じていた記者もいた。ある意味、毎日悲しい話を聞き続けるだけに、気分転換が必要だったのかもしれない。
ラブホでの笑い話もある。2人組で入った男性記者が備え付けのゲームを遅くまで続けてフロントから注意されたり、朝、男性デスクとエレベーターに一緒になり、本物のカップルに不審がられたり。女性記者は「心の中で、ちゃうちゃうと否定してました」と笑った。
そうこうしているうちに、あっという間に1月が終わった。2月になって11日の建国記念日の祝日が来て初めて新聞休刊日となった。震災以来約1か月。やっと帰宅し、翌日、沢山の着替えを持って出た。
「明るい記事を」と強いる東京本社
このころ東京本社からの指示があった。いつまでも悲しい、涙することばかり書かずに、「復興」に向けた明るい記事を書け!と。信じられなかった。阪神支局のデスク陣は怒った。しかし、本社社会部からは、東京の指示に従えと言って来た。地域版の阪神版では、確か「復興へ」というワッペンが作られて無理矢理明るい記事を書かされた。正直言って、東京では、阪神・淡路大震災は遠くで起きた災害なのだ。他人事のようだった。
それでも、阪神支局は毎日、社会面に喜怒哀楽の記事を送った。ほぼ連日、社会面トップ、第二社会面トップを飾った。筆者は満足していた。それが当たり前だと思っていた。しかし、その後、災害報道の研究を続け、被災者や専門家の意見を聞き、少し考え方が変わった。それは、本当にまた後ほどに、お伝えしよう。
3月20日、突然、紙面に阪神・淡路大震災の記事が載らなくなった。この日朝8時ごろ、東京で地下鉄サリン事件が起きたからだ。(続く)









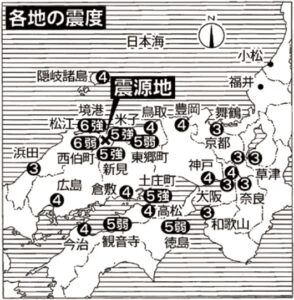
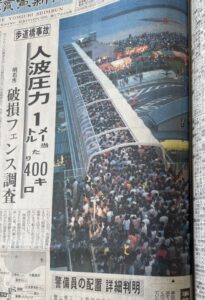











コメント