
©NO MAN PRODUCTIONS LLC
2022年1月27日午後1時半。東京地裁712号法廷では、2019年公開の映画『主戦場』の判決が言い渡された。私はこの日上京し傍聴。裁判長の判決の主文言い渡しを聞いた。
この裁判の意味すること、また上映取り下げを起こした映画祭の元スタッフとしての考えを述べたい。なお、昨年(2021年)3月末をもって諸般の事情で私はKAWASAKIしんゆり映画祭を辞め、生まれ故郷の大阪に戻ったので、以下は映画祭自体の見解ではなく、あくまでも私見であることを留意いただきたい。
「同意なく映像を使用」出演者が提訴
2019年4月20日に東京のシアター・イメージフォーラムで公開された映画『主戦場』は、全国のミニシアター約40館を中心に上映され、多くの観客を動員した。当時、川崎在住だった私も初日初回を観に行き、パンフレットに監督からサインをいただきながら「議論のきっかけになればいいですね」と話しかけたことを覚えている。
従軍慰安婦問題の作品と言われることが多い本作だが、私は「従軍慰安婦問題や、ヘイトスピーチ、日本人の歴史認識など、多くの様々なことを問う作品」と私は今でも思う。
日・米・韓の多くの方々にインタビューを重ねていった本作は、2019年6月19日、一部の出演者から訴えられた。原告は本作でインタビューを受けた中のケント・ギルバート氏、トニー・マラーノ氏、藤岡信勝氏、藤木俊一氏、山本優美子氏の5名。
被告は、本作監督のミキ・デザキ氏と、配給会社東風(とうふう)。
原告の訴えは「同意なくインタビュー映像が使われ一般公開されたのは不当」とし、被告に対し、上映禁止と1300万円の損害賠償を求めたものだった。
川崎市役所からの電話で上映取り下げ
KAWASAKIしんゆり映画祭(以下「しんゆり映画祭」もしくは「映画祭」とする)は、1995年から神奈川県川崎市北部の麻生(あさお)区・新百合ヶ丘駅近辺で毎秋開催されてきた市民映画祭で、川崎市から多額の支援金を得て運営されている。『楢山節考』などで知られる今村昌平監督が作られた日本映画学校(現・日本映画大学)も新百合ヶ丘駅すぐそばにあり、かつては映画学校の学生たちも、映画祭運営に携わってきたと聞いた。
私は2016年にスタッフとなり、翌年から作品選定などにも関わってきた。『主戦場』はスタッフ間でも話題の作品となり、2019年秋のしんゆり映画祭で上映することに決まった。私は『主戦場』の作品提案者であり、その後配給交渉も行った。2019年以前にも東風には何度も私はお世話になり、私自身は、とても尊敬し信頼できる配給という印象を今も持ち続けている。
作品選定が佳境に入っていた頃、本作が訴えられたことを知った。スタッフ間では共催者の川崎市に「何かあった時には対応をよろしく」を伝えようと話がまとまり、映画祭事務局スタッフから川崎市にそのことを伝えに行ってもらったはずだった。
その後、映画祭から配給へ上映申込書を送り、受理された(この「受理」をもって、映画祭と配給との間に上映契約が整ったことになる)。受理された数時間後、川崎市の担当者から映画祭事務局へ「係争中の作品を上映することはいかがなものか」という電話があった。
プログラムに関わるスタッフと、映画祭の上層部の議論もあったが、結局は映画祭上層部により上映取り下げが決定。私を含めごく数人のスタッフから対応策等を上層部に提言したり、この取り下げが意味することなどを伝えたりしたが全て却下された上での決定だった。全上映作品の発表前だったので、一般から何の抗議もないままの取り下げだったことも記しておきたい。

©NO MAN PRODUCTIONS LLC
新聞報道が突破口、最終日の上映実現
映画祭初日まであと3日となった10月24日夜、しんゆり映画祭の上映取り下げについて、朝日新聞が記事にしてくれたことで、映画人を含め広く多くの方たちが知るところとなり、多くの監督や配給会社、この年のゲストを含めた関係者の方たちもそれぞれのやり方で声をあげ、行動をしてくださることとなった。私にとって、朝日新聞の記事はまさに「突破口を開いてくれた」ものであった。
市民・配給会社・メディア・映画祭スタッフすべてに呼び掛けて、上映取り下げ問題について広く話すための「オープンマイクイベント」を行うべく奔走して下さった配給や監督たちもいた。このオープンマイクイベントにおいても「上映再決定を!」という多くの強い声を聞き、その後、映画祭スタッフが約3日にわたって長時間の議論を重ねた。「もともと上映するはずだった作品です。やりましょう」と、シンプルだけれど一番もっともな意見を言ってくれた新人スタッフもいて、スタッフ間では上映を内定。そして、各配給会社や監督たちに了解を得て、関係各所への連絡も経て、ようやく、最終日に1回だけ上映をすることがかなった。本来は2回上映するはずだったが、それでも、見守りにかけつけて下さった多くの方たち、弁護士の方たち、「表現の自由は僕らの問題でもありますから」と取材をしてくれたディレクター・記者たち、記事を連日書くことで支えてくれた記者たち、警察の方たちのおかげもあって無事に上映ができたことは、今でも私は感謝しかない。
原告全面敗訴は「無理筋な訴えにビビるな」のメッセージ

撮影:越智あい
この裁判の判決主文は次の通り。
「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」
2年半にわたる裁判は原告の全面敗訴、すなわち被告の全面勝訴となった。
今回の裁判の大きな争点は二つ。津田大介氏のポリタスTV(2/1)から引用をさせていただく。
デザキ監督がオファーする際に出演者を騙したか⇒<地裁判決>騙したとは言えない
元々は修士論文代わりの映像への協力ということで出演者は許諾したが「映画の出来がよければ映画祭への出展や一般公開したい」旨を説明し許諾され書面も残っている。
歴史修正主義者という表現は名誉棄損に当たるか⇒<地裁判決>名誉棄損には当たらない
・この映画以外にも様々なメディアで同様の表現はされており、概念的、評価的なものなので監督の論評の範囲。
・「客観的な資料などなくむやみに歴史的事実を否定する人々である」ようには表現していないし、視聴者もそうみないだろう
88ページにわたる判決文を知人から私はいただき、全文を一読した。どちらが勝ったとしても判決主文だけではなく、判決文全文が大切と思っていたためだった。昨年(2021年)9月の本人尋問は傍聴に行かなかったが、それ以前の公判を私は傍聴した。けれど、私の傍聴した範囲では、書面などのやりとりの確認がほとんどで、その後本人尋問に至るまでの長期間、非公開の協議などに入ったこともあり、具体的にどのようなやりとりがなされていたかわからなかったが、その一端も判決文で知ることができた。
原告の請求は、法に明るくない私が読んでも無理筋と思えることも含まれていた。(そんなことまで著作権に含むの?)という部分には正直、呆れた。
原告の請求に対して、被告が証拠・資料を確実に提出し、それに基づき裁判官が本当に丁寧な確認と検証をしたことが、ど素人の私にもよく伝わってくる判決文で、その丁寧さは、変な表現かもしれないが、数学の証明問題の、丁寧な答えを読むような印象だった。
この判決を出すために、裁判官たちはいったい何回『主戦場』を観たことだろう。作品中で流れるドラムの音が頭の中でずっとリフレインしなかったろうかと心配にすらなったほどだった。
この資料・証拠を出すために、被告である監督、配給、弁護団はどれだけの時間と労力を割いたことだろう。
そう思い、ため息をつきながら判決文を読んだ。
監督の、作品制作過程にはなんら落ち度はなく、かつ、上映禁止にする理由も見当たらないという判決内容は、すなわち「表現の自由」を守ったことになると私は解釈した。
けれど、この判決が意味することはそれだけではないと私は思う。「無理筋なことを訴えられても、臆さず、ビビらなくて良い」。そういう声が判決文から聞こえたように思った。上映取り下げを押しとどめられなかったがゆえに、思うことなのかもしれないが…
「恐れ」への向き合い方とは?
判決文を読み、改めて思う。私は、そして私たちはどうすればよかったのか、と。
朝日新聞の最初の記事から映画祭終了までの2週間弱の間に上映を再決定させねばと、私自身がかなり強い言動も取った面もあった。2年半という時間が経ったがゆえに、改めて考えることなのだが…
しんゆり映画祭のスタッフの中には、ある団体の猛攻を職場で受けた辛い経験を持つ者や、街宣車の怖さ、裁判そのものの面倒くささを実体験として持っている者もいた。
またこの2019年夏には、新百合ヶ丘から数駅しか離れていない登戸で、登校途中の小学生や見守りの保護者たちが無差別に襲撃される事件も起きていた。映画祭スタッフの中には、「襲われる」怖さを少なからず覚えていた者もいた。
あいちトリエンナーレの展示中止のことも、私たちスタッフは知っていた。「威力業務妨害だから、きちんと捜査がされたりしたらきっと展示再開するよ」という、数名のスタッフでの雑談もあった数日後の、川崎市からの「いかがなものか」という「懸念」の連絡だった。
川崎市からの「懸念」表明は、支援金を減額されるかもしれないという、スタッフ間の恐れにつながった。減額などされたら、しんゆり映画祭はたちまち立ち行かなくなることを、数年でもスタッフを経験した者の多くは知っていた。
「そんなに肝の小さいことでどうする!」「覚悟もなく映画祭なんてやるな!」と言われる方もいるかもしれないが、ちょっと待っていただきたい。個々人の体験に基づく「恐れ」や様々な心配に対して、どのように「大丈夫」と言えただろうかと今も考えてしまう。叱咤で動く人がそんなにいるだろうか、とも思う。
また当時の川崎市は、ヘイトスピーチ条例制定に向けて動いている真っ最中だった。私自身は、(ヘイトスピーチ条例を作ろうとしている市だから、きっと、対応策など持っているはず)と思ったが、反応は逆だった。あくまでも想像に過ぎないが、面倒なことはひとつでも避けたいというのが市の本音ではなかったかと思う。

©NO MAN PRODUCTIONS LLC
先述したが、一般からの抗議がひとつもない中での、上映取り下げ決定だった。たまたま、上映申し込みが完了していたがゆえに、その後の大きな動きへとつながったが、もし申し込みが完了する前に市からの「懸念」の連絡があったら、きっと、上映決定そのものが映画祭内部で反故になっていた可能性が高いと私は思う。
面倒なことは避けたいと考え、『主戦場』を上映候補からそっと外した他の映画祭や自主上映団体はいなかっただろうか、とふと思う。
今の私がもし言えるとしたらこの二つだ。
「どんな事態でも、丁寧に、切り分けて検証し、ひとつひとつ対処・対応すればよい」ということ。
また、先日『人生フルーツ』を久しぶりに劇場で観て、建築家である故・津端修一さんが、いつでも求めがあれば設計図を書けるように用意をしてらした場面に出会った。そうだ、私も、淡々と用意を続けよう。出会った方たちとつかず離れずのお付き合いを続け、つながり、折に触れて勉強し、いざという時には動けるよう整えておこう。「大丈夫」と言えるための言葉をたくさん持ち、法や判例を知り、備えておこう、と。

©NO MAN PRODUCTIONS LLC
薄かった判決日の報道
2019年の秋、海外でも報道されたしんゆり映画祭の上映取り下げ問題。映画祭が終わって2か月弱後の2019年暮れに知人から「(しんゆり映画祭と同時期に行われていた)東京国際映画祭よりもしんゆりの方がニュースの量が多かったよ」と言われたほどだった。
しかし、先日の1/27の判決公判の日、『主戦場』の裁判について、テレビカメラは一台もなく、記事も多かったとは言えない。
この日の東京地裁は、故・星野文昭さんに関する国賠訴訟もあり、「甲状腺がん患者6人が東京電力提訴」という大きく取り扱うべき裁判もあった。テレビ局の都合もあるはずで、「なぜ取材に来ない!」と居丈高に言うつもりは私は毛頭ない。が、表現の自由に関わるこの裁判の判決を、もう少し注視していただきたかったと正直思う。
当然の判決だったと私は思う。けれど、今回の裁判、そしてそれにまつわる出来事が日本の社会に与えた影響は決して小さくなく、また、日本の社会のある側面をあらわにしたことだったと思う。メディアの皆様を含めて、一人でも多くの方に、今後も関心を持ち続けてほしいし、この地裁判決を今後多くのことに活かすことも考えてほしいと思う。
「いつまで私を生け贄に差し出すつもりですか」監督を孤立させるな

©NO MAN PRODUCTIONS LLC
2020年の2月頃だったと思う。横浜の黄金町で行われたトークイベントに私は行き、デザキ監督たちの話を聞いた。うろ覚えだが、その中でデザキさんは「日本の方たちは、いつまで私を『生贄』に差し出すつもりですか?」という趣旨のことをおっしゃっていた。
とても悲しい言葉だった。
私は既にしんゆり映画祭のスタッフではない。けれど、デザキさんを一人にしない、今後もじわじわと関わり、注視し続け、私にできることで動こうと思う。
◆公式WEBサイト: http://shusenjo.jp FB: https://www.facebook.com/shusenjo Twitter: https://twitter.com/shusenjo






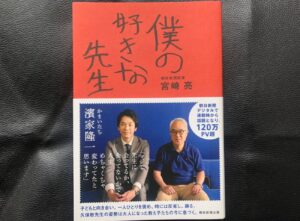
















コメント