2024年7月、バングラデシュではZ世代(1990年代半ばから2010年代序盤に生まれた世代)の学生たちが反政府デモを起こした。その背景には就職問題がある。反政府運動は市民社会に広がり、多くの犠牲者がでた。8月に入り、政権は崩壊した。政変後、学生たちは自分たちの思い、考えを壁画に描いた。高温多湿の気候のため壁画は消えていくが、神戸女学院大学南出和余准教授は壁画を写真におさめた。その数は1000を超える。
南出和余さんは専門が文化人類学で、神戸女学院大学国際学部グローバル・スタディーズ学科准教授。2023年12月20日の朝日新聞EduA(エデュア)に南出さんのインタビュー記事が掲載されている。南出さんは「グローバル・スタディーズコースの学びで伝えているのは『現代社会の問題を考えるとき、それらとあなたを切り離すことはできない』ということです。どんなテーマを選んだ学生も、必ずどこかに自分とつながる点があると気づいていきます」と言う。
昨年10月29日、放送法研究会が南出和余准教授を招いて勉強会を開いた。放送法研究会は関西の放送局・新聞社などメディア関係者有志が集まる会で、メディアに関する勉強会を続けている。今回はスピンオフ企画として行われた。その模様を報告します。最初に、南出さんは自身の研究についてこう話した。
南出
私自身、大学院で研究を始めた時、研究対象をバングラデシュの子どもたちにしました。バングラデシュでは、エリート教育は別ですけれども、1990年代から農村にも小学校が普及していく中で、子どもたちは学校教育を受け出します。私はその子どもたちを「教育第1世代」と呼んでいます。子どもたちの親世代はほとんど学校に行ったことがありません。2000年にフィールドワークでバングラデシュに滞在し出した時、ベンガル語はほとんどできなかったので、小学校4年生のクラスで子どもたちと一緒に勉強しながら子ども社会を参与観察するという生活をおよそ1年間、送りました。そのときに一緒に勉強した、90年代生まれで、当時10歳だったバングラデシュの子どもたち38人を今もずっと追いかけています。現在その子どもたちは、田舎から都市に出て行き、アパレル産業で働いていたり、海外に出稼ぎに行っていたり、バングラデシュ経済の底辺を支えている大多数層の中にちょうど位置づけられる層です。
今回のバングラデシュの政変は、私がずっと追いかけている90年代生まれの次の世代、「Z世代」の学生たちが起こしました。私自身、バングラデシュの若者を研究しているので、この政変から目を離せませんでした。
バングラデシュの歴史を振り返らなければ、この「バングラデシュ7月革命」を理解することはむずかしい。南出さんはバングラデシュの歴史を説明する。
南出
イギリスの植民地支配下にあったインドは1947年、ヒンドゥー教徒を中心とするインドとムスリムが多いパキスタンに分裂して独立しました。パキスタンはインドをはさんで西パキスタン(現在のパキスタン)と東パキスタン(現在のバングラデシュ)が遠隔で1つの国を形成することになります。
1947年の独立後、1971年にバングラデシュがパキスタンから独立するに至るには、いくつかポイントがあります。当時のパキスタン政府はウルドゥー語を唯一の国語にすると声明を出します。これに対して、大多数の住民がベンガル語を母語とする東パキスタンでは、学生を中心にベンガル語公用語化運動が起こります。この運動中に、ダッカ大学の学生たちがパキスタン兵の弾圧によって亡くなります。このダッカ大学殉教学生が、今回のバングラデシュ政変の流れにも大きく関係していると思います。ダッカ大学生が亡くなったのは1952年2月21日で、1999年にユニセフは「2月21日」を「世界母語デー」と定めました。ユニセフの「世界母語デー」はベンガル語公用語化運動に由来します。
その後、1971年にバングラデシュで内戦が起こります。9ヶ月間の内戦を経て、バングラデシュはパキスタンから独立します。最初は完全に劣勢だったバングラデシュをインドがサポートし、12月16日に独立します。世界史的には第3次インドパキスタン戦争と呼ばれているのが、バングラデシュ独立戦争です。国土は荒廃し、300万人の死傷者、1000万人近くの難民を出したと言われています。建国の父とされる最初の首相はムジブル・ラーマンで、その娘シェイク・ハシナが今回の政変で倒れた政権の首相です。ムジブル・ラーマンは1975年、軍のクーデターで暗殺されます。家族も殺されましたが、ハシナはイギリスに留学中でした。
〈ムジブル・ラーマン暗殺後、バングラデシュは軍事政権となる〉
南出
冷戦が終わり、世界的に民主化の動きの中、バングラデシュでも民主化運動が起き、1990年にバングラデシュは民主化します。平和的に民主化がなされました。1991年から5年ごとに総選挙を行う、選挙と選挙の間に一時的に無政党選挙管理内閣を立ち上げる、そういうシステムが民主化以降ありました。1991年はBNP(バングラデシュ民族主義党)連合政権、1996年はアワミ連盟政権、2001年はBNP連合政権、このようにアワミ連盟政権とBNPが交互に政権を握りました。アワミ連盟の首相はバングラデシュ建国の父ムジブル・ラーマンの娘シェイク・ハシナで、BNPの首相はバングラデシュの独立戦争の時に軍を率いたジアウル・ラーマンの妻カレダ・ジアです。BNPもアワミ連盟も汚職がひどく、2001年から2006年までのBNP連合政権時は特にひどくて、2006年に終了したBNP政権後に立ち上がった選挙管理内閣は汚職の一掃と公平な選挙実施のためのシステム構築に2年半の年月を費やしました。1980年代から1990年代にかけてのバングラデシュ政府の汚職が国際的にも問題視される一方で、バングラデシュの貧困問題解決に向けて、国際機関はバングラデシュ政府を介さずに、現地のNGOを支援しました。国内NGOの成長がバングラデシュの開発発展を率いたところがあり、その代表的存在がノーベル平和賞を受賞した経済学者のムハマド・ユヌスさんです。
〈貧しい人たち向けの無担保少額融資を考案し、貧困からの脱却に貢献した功績で、2006年にバングラデシュの「グラミン(農村)銀行」と創設者のムハマド・ユヌスさんがノーベル平和賞を受賞した〉
南出
2008年の選挙ではアワミ連盟が大勝しました。この時、私はバングラデシュの農村にいて、街はお祭りのような雰囲気でした。しかしその後、結果的に独裁状態になっていきます。2014年の選挙の時は、選挙管理内閣を無視するような状態でアワミ連盟主導の選挙が実施され、BNPは選挙をボイコットし、引き続きアワミ連盟が政権を握ります。一方で、この時期、バングラデシュは経済成長がかなり進みました。経済を動かすという意味ではアワミ連盟政権は開発独裁的な性格を持っていました。バングラデシュのような低賃金労働の国にグローバル企業が集まる、これがバングラデシュの経済成長の要因です。
〈2014年に続いて、2018年、2024年の選挙でも、BNPは選挙をボイコットし、アワミ連盟が政権を握る〉
南出
2024年1月に選挙がありましたが、完全にしらけたような選挙でした。こうした政治的な流れの中で2024年7月に学生運動が起こります。学生たちにとって、特に大学卒のエリート層にとって、公務員はほぼ唯一のホワイトカラー職です。IT企業など民間の企業も増えましたが、それ以上に教育の進学率が上がりました。民間企業では契約雇用が多く、やはり安定しません。一方、公務員は年金制度もあり、何より安定が得られます。学生たち、特に国立の大学生のエリート層にとって、公務員試験がどんどん過熱化していきます。
バングラデシュの公務員試験にはクオータ制度というものがあります。バングラデシュ独立戦争で戦った兵士は「フリーダムファイター」と呼ばれ、国の英雄です。バングラデシュの国旗は、日の丸のようなデザインで緑地に赤の丸ですが、緑はバングラデシュの自然の豊かさを、赤は独立戦争で戦って犠牲となった人々の血を表しています。「フリーダムファイター」は国のために戦ったと賞賛されています。「フリーダムファイター」の子ども世代には、父親が独立戦争で亡くなったり、負傷したりしていることもあって、特別に公務員の枠が設けられました。さらに孫の世代にもその権利が世襲されています、これがクオータ制度です。
〈今回の運動以前のクオータ制度:フリーダムファイターの子ども・孫の枠は30%、実力に基づく枠(一般の枠)は44%。女性枠10%、辺境地出身者枠10%〉
南出
今回の運動の発端は、このクオータ制度の対象とならない学生たちが、クオータ制度見直しを要求したことに起因します。実は、2013年にすでに若者たちがクオータ制度に関する議論をしていましたが、クオータ制度を中心とした運動が大きく起こったのは2018年です。この時に裁判所はクオータ制度廃止を決定しました。しかし、アワミ連盟政権はクオータ制度廃止を実施しませんでした。2024年1月の選挙では、アワミ連盟は若者の票を得るためにクオータ制度廃止を公約として打ち出しました。ところが、6月に最高裁は2018年に裁判所が決定したクオータ制度廃止を違法だとしました。結局、クオータ制度はそのまま維持されることになりました。そして、7月になって、クオータ制度に関して学生運動が起こったのです。
運動はどんどん激化していきます。政府がこの運動を押さえつける中で、7月14日、ハシナ首相が「ラジャカール発言」をします。バングラデシュ独立戦争時にパキスタン軍についたバングラデシュ人を「ラジャカール」と言います。ハシナ首相はクオータ制度廃止を求める学生たちを「ラジャカール」だと言ったのです。それで火がつきました。
翌日の7月15日、政府は運動弾圧のために警察を投入します。「チャットロ(学生)リーグ」と呼ばれるアワミ連盟学生部とクオータ制度見直しを求める学生が対立します。バングラデシュ独立戦争の時から学生の力は大きく、1947年のイギリス植民地から分離独立後の早い時期にアワミ連盟は結党し、アワミ連盟の学生部「チャットロリーグ」も形成されます。ダッカ大学など主要大学には、各党の学生部があります。この16年間、ハシナ政権独裁状況下で若者たちは政治への関心を軽薄化させ、政党の学生部は弱小化しました。チャットロリーグ自体も弱くなりました。けれども、今回この運動を押さえつけるため、アワミ連盟はチャットロリーグに対して武装支援をしました。クオータ制度見直しを求める学生たちは言ってみれば「ノンポリ」です。そのノンポリ学生の運動に対して、チャットロリーグに武器も持たせて弾圧しようとしたので、まず学生同士の衝突がありました。
7月16日、抗議運動をしていた学生、アブ・サイードが射殺されます。運動中の学生が殺されるのは、1952年のベンガル語公用語運動の時を思わせる、そういう出来事でした。ベンガル語公用語運動で亡くなった学生やバングラデシュ独立戦争で亡くなった殉教者は、ベンガル語で「ショヒード」と言います。「アブ・サイードはショヒードになった」とSNSでどんどん市民全体に広がります。そして「ハシナは独裁者だ」と攻撃していきます。若者たちはすごく上手にSNSを使って運動を広げるので、7月18、19日に政府はインターネットを遮断します。
完全にインターネットも電話も繋がらない状況にあって、19日夜から外出禁止令が出ます。この時に、警察はダッカの街で、学生が家にいるかどうかを一軒一軒回って確認し、運動している学生が連行される事態となりました。
7月21日に最高裁はクオータ制度の見直しを認めます。「フリーダムファイター」の子ども・孫の枠は30%から5%に減り、実力に基づく一般枠は44%から93%に増えました。新たに、少数民族1%、ジェンダーマイノリティと障害者合わせて1%ができました。
7月24日にインターネットが復旧しますが、この時には、学生の要求はクオータ制度見直しだけではなくなっていて、7月29日に9つの要求を出します。その中にはハシナ首相の謝罪、暴動を押さえつけるために動いた警察長の辞任などが含まれています。一貫して、学生の運動は非暴力です。しかし、9つの要求は聞き入れられません。
7月31日、「正義の行進」が行われます。警察の弾圧はヘリコプターからの射殺にも至りました。それでも学生たちは非暴力運動に徹しました。SNSを使って非暴力で「正義の行進」で訴えかけて、市民も「正義の行進」に参加します。8月2日に、要求事項をハシナ首相辞任の一点に集中します。この時、私は日本にいて、アルジャジーラとBBCバングラ―、在外バングラデシュが発信するネットニュースを情報源として注視していました。8月2日にハシナ首相に辞任要求が出ましたが、ハシナ首相が辞めるとは思っていませんでした。BNPは完全に弱体化していましたし、政権が変わるとも思っていませんでした。
8月4日、「ロング・マーチ・トゥー・ダッカ」の呼びかけがなされます。これは、首相公邸に向かってみんなで行進しよう、というものです。学生だけではなくて市民にも呼びかけられました。8月5日に行進が行われますが、その午前中にまたインターネットが繋がらなくなりました。午後2時の段階でインターネットが繋がって、この時にはすでに、ハシナ首相は軍のサポートによりインドに逃げていました。
軍はアワミ連盟と近い関係にあり、独裁政権の中で恩恵を受けていたのは事実です。警察はアワミ連盟の指示のままに弾圧に出ました。しかし、軍は学生には手出ししなかった。「アワミ連盟が引いたら軍が統制を取る」「警察の長は政府だけれども軍の長は政府ではない」それがバングラデシュに従来からあった認識です。軍の出世コースはPKO、国際連合平和維持活動、国連部隊です。そういう意味で警察と軍には立場の違いがあります。
ハシナ首相がインドに逃亡した背景には、アワミ連盟政権とインドとの関係が極めて強いという点があります。バングラデシュ独立戦争でインドに支援をしてもらい、バングラデシュ初代首相はハシナ首相の父ムジブル・ラーマンでした。また、バングラデシュの国土はほとんどインドに囲まれています。結局、インドのモディ首相がハシナ首相を受け入れました。
ハシナ首相が逃亡した状況で、その後は軍が統治するとみんなが思っていましたが、学生たちは軍には政権を取らせないと主張しました。8月8日、学生代表らの要望で、ノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌスさんを長とする暫定政府が出来ました。
〈クォータ制度廃止という学生たちの切実な要望〉
なぜ、公務員は学生たちにとって魅力なのか。バングラデシュは学歴が上がるにつれて失業率が上がります。これは、バングラデシュの経済的な構造の問題だと言えます。現在のバングラデシュ経済はグローバル経済の影響をダイレクトに受けています。いわば「下請けの仕事を軸とした経済成長」です。その主要産業は、アパレル産業と海外出稼ぎ者からの仕送りです。アパレル部門の多国籍企業は、賃金が安いからバングラデシュに来るわけですが、バングラデシュの人たちにとってもその労働条件は決して良くないし、イメージも良くありません。海外の出稼ぎについては、2022年にカタールで行われたサッカーワールドカップの時に、スタジアム建築で多くの外国人労働者が亡くなりましたが、バングラデシュ労働者がかなりの部分を占めていました。そういう仕事に就く層は、学歴で言えば中学校卒業ぐらいです。彼らは他に選択肢がない中でそういう仕事に就くのですが、大学まで出た人たちはプライド的にもそれらの仕事には就けないのです。
ホワイトカラー職、あるいは中間職が欠如しているために、大学生たちの希望が公務員に一点集中します。例えばアパレルのバングラデシュ人工場経営者はお金持ちですが、そういう富裕層の子どもたちの一定数が私立の大学に行き、卒業後は多くが海外(特に先進国)に出て行きます。国立大学では、地方からの優秀な学生たちも集まっていますが、彼らが伝手なしに自分の実力だけで仕事に就けるのは公務員だと、そういうことになっています。これが、学生たちがクオータ制度の見直しをこれだけ必死に求めたバックグラウンドです。
今、バングラデシュ人は世界中にいます。抗議運動はバングラデシュ国内に止まらず、特にインターネットが遮断された7月18日ごろには海外在住のバングラデシュ人たちも各国で抗議運動を起こしました。日本では東京のバングラデシュ大使館前で抗議運動がありましたし、バングラデシュからの国費留学生たちが北海道大学、京都大学、神戸大学、九州大学で抗議運動を起こしました。その時のスローガンは「学生を殺すな」、インターネット遮断に対する「情報アクセスという人権を守れ」といったものでした。人権や「グローバルな正義」が掲げられていたのがポイントです。
〈壁画デワル・リコンに描かれた学生たちの思い〉
政変直後の8月17日に渡航し、1ヶ月間のバングラデシュでの調査の間に集めたのが、Z世代の若者たちによる壁画です。バングラデシュには壁画文化があって、ポスターを貼るかのように壁画を書きます。今はおそらく天候の影響でどんどん消えていると思いますが、8、9月は街中にあって、写真を1200枚ぐらい撮りました。
抗議運動中には、スプレーで落書きのように「キラー、ハシナ」(殺人者、ハシナ)や「ステップダウン、ハシナ」(首相を退け、ハシナ)などの言葉がたくさん書かれていました。8月5日にハシナ首相が逃亡し、アワミ連盟も政権から下りました。警察はアワミ連盟の指示の元に学生たちを弾圧していましたから、逆襲を恐れて雲隠れし、一時、街は無警察状態になりました。バングラデシュは信号があまりなくて、基本的に交差点に警官が立って指示をするのですが、その交通警官もいなくなりました。代わりに学生たちが街に出て、交通整理をしたり、抗議中に出たゴミの掃除もし、自治をしたのです。
学生たちは運動中に書かれた「殺人者、ハシナ」などの文字を政変後に全部消して、清掃活動の一環として、そこに壁画を描きました。壁画に若者たちは一連の出来事を記録しました。その一つが、ベンガル語の数字で書かれたカレンダーです。ハシナ首相が逃亡した8月5日は「7月36日」とされ、7月1日から7月36日まで、その日その日の出来事が描かれています。
7月16日に抗議運動をしていた学生アブ・サイードが射殺されましたが、アブ・サイード射殺時の写真が現地の新聞に掲載され、その写真がSNSで広がり共有されて、多くの壁画に描かれました。壁画は一つの語りになっています。
「水、要りますか」と書かれた壁画もあります。売店で働いている人が負傷した学生に水を持って行って声をかけた時に殺されました。このこともSNSで共有され、壁画に描かれています。
首相公邸を目指して行進する「ロング・マーチ・トゥー・ダッカ」に参加する学生や市民らの姿もたくさんの壁画で描かれています。
風刺画の壁画もあります。ハシナ前首相その父ムジブル・ラーマンの肖像画に落書きしたものや、インドに逃げていくハシナを描くものもあります。インターネットが遮断されたとき情報大臣は「サテライトに雨が降ったから」と言った、それを皮肉った壁画もあります。
政変後、8月後半に大きな洪水が起こりましたが、学生たちは支援活動も行いました。それも壁画で記録されています。
バングラデシュでは大学生はエリート層です。特にZ世代の彼らは、情報社会の中でグローバルな感覚を持っています。バングラデシュの人口の9割はムスリムですが、パキスタンからの独立時には世俗性が重視され、〈ヒンドゥー、クリスチャン、ブッド、みんなバングラデシュ人だ〉、そういうスローガンが使われました。今回の壁画でそれが再現されています。また、人口の2%の少数民族・先住民の名前が書かれた壁画もあります。同じムスリム社会としてパレスチナ支援もとても強く、パレスチナ支援を描く壁画も多くあります。
学生たちは、この政変を「バングラデシュ2.0」「2度目の独立」と言います。そして、自分たちを「ジェネレーションZ」(Gen-Z)と強く自覚しています。「ジェネレーションZが今回の政変を起こした」、そのアイデンティティがとても強い。「革命が必要ならGen-Zに連絡を」という壁画もありました。政変直後の8月のバングラデシュでは国中が学生たちを称賛し、学生たちは高揚感の中で壁画を描きました。
今回の政変は学生たちの勢いによって起きたものであることははっきりしています。市民たちは、この16年のハシナ政権の独裁的な状況を嘆きつつも半ば諦めていた中で起こった学生たちによる運動に、「同調して乗った」のだろうと感じています。
学生たちが訴えたのは何だったのか。宗教の多様性や民族の多様性、殺害に対する抵抗、非暴力の運動、そういうグローバルに正義とみなされるスローガンを挙げながらも、出て来るものはやはりナショナリズムです。壁画で使われていた言語の約6割はベンガル語です。アブ・サイード射殺の壁画に、1971年の独立時に用いられたベンガルの詩が添えられています。ベンガル社会ではタゴールに象徴される詩の文化が昔から盛んで、文字が読めなくても詩は暗唱できる、そういう社会です。独立時に使われた詩の再生、再利用です。ナショナリズムの再生にも繋がっています。ナショナリズムとグローバルな正義がくっついている、それがZ世代の学生たちの感覚だと見ています。
〈南出さんが撮影した1166枚の壁画の写真を公開したオンライン写真展は、次のURLからアクセスできる〉
●編集担当:文箭祥人
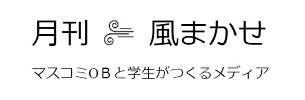

















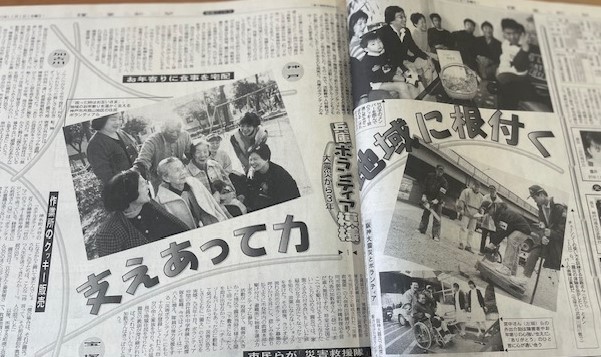
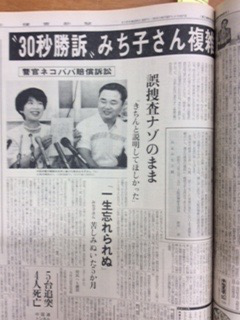
コメント