4月27日、大阪・九条の下町長屋の本屋さんMoMoBooksで「春のノンフィクション祭り2024~第7回角岡伸彦ノンフィクション賞発表会~」が行われた。
『芝浦屠場千夜一夜』(山脇史子、青月社、2023年)と『僕の好きな先生』(宮崎亮、朝日新聞出版、2023年)が第7回角岡伸彦ノンフィクション賞に、『移民の子どもの隣に座る 大阪・ミナミの「教室」から』(玉置太郎、朝日新聞出版、2023年)が第1回西岡研介ノンフィクション賞を受賞、発表会にフリーライターの角岡伸彦さんと西岡研介さんが出演。

角岡伸彦
1963年、兵庫県加古川市生まれ。89年、神戸新聞へ入社。記者として勤務後、フリーになり、現在はフリーライター。『カニは横に歩く 自立障害者たちの半世紀』(講談社)で2011年、講談社ノンフィクション賞受賞。著書に『被差別部落の青春』(講談社)、『ピストルと荊冠 〈被差別〉と〈暴力〉で大阪を背負った男・小西邦彦』(講談社)、『ゆめいらんかね やしきたかじん伝』(小学館)、『はじめての部落問題』(文春新書)、『ふしぎな部落問題』(ちくま新書)などがある。大阪市在住。
西岡研介
1967年、大阪市生まれ。91年、神戸新聞へ入社。98年、「噂の眞相」編集部に移籍。その後「週刊文春」「週刊現代」の記者を経て、現在はフリーライター。『マングローブ テロリストに乗っ取られたJR東日本の真実』(講談社)で2008年、講談社ノンフィクション賞受賞。著書に『襲撃 中田カウスの1000日戦争』(朝日新聞出版)、『ふたつの震災 [1・17]の神戸から[3・11]の東北へ』(松本創との共著、講談社)、『トラジャ JR「革マル」30年の呪縛、労組の終焉』(東洋経済新報社)など。神戸市在住。
角岡さん、西岡さんは元神戸新聞社記者。角岡さんは5年、西岡さんは7年在籍し、そのうちの1年間はともに姫路支社勤務。
偽ノンフィクション本への批判がきっかけで「角岡伸彦ノンフィクション賞」を設立
角岡さん、西岡さんのトークは、どうして「角岡伸彦ノンフィクション賞」をつくったのか、その経緯から始まる。
角岡
7年前、『路地の子』(上原善広、新潮社、2017年)という本があって、この本は屠畜場を舞台にしたノンフィクションなんですが、ウソが多い。ブログでずっと批判したんです。その内容は『ノンフィクションにだまされるな!』(角岡伸彦、2019年、にんげん出版)に詳しく書きました。ずっとブログで批判をやってきて嫌になってきて、他人が書いた文章を批判するって、その本をじっくり読まなあかんし、場合によっては取材せなあかんし、面倒くさい。
西岡
その執念はすごいと思います。一人ファクトチェッカーですもんね。
角岡
その時、憂鬱でね。ええ本を紹介したいという欲求が出て来たんです。突発的に、ノンフィクション賞をつくったら、おもしろいんちゃうかって。それで角岡伸彦ノンフィクション賞をやり始めたけど、第1回と名乗ってしまったところもあって、第2回もせなあかんみたいな。ほんで、毎年やるようになってんけど、続けるのが面倒くさい。
西岡
それはそうだと思います。
角岡
なんでかというと、そこそこ読んでないとあかんやん。5冊の中から選びましたという訳にいかんので、それなりに意識して読まないと。しかも、自分で買うてるし。年間100冊ぐらい読んでるねん。
西岡
手弁当感、満載ですもんね。
角岡
僕はツイッター(X)もやっているんですけど、ツイッターで受賞作を発表してたら、反響がわりあい、あんのよ。それが増えてきて、辞められなくなってきて…。
《角岡伸彦ノンフィクション賞受賞作品》
第1回
『黙殺 報じられない”無頼系独立候補”たちの戦い』(畠山理仁、集英社、2017年)
第2回
『スターリンの娘 クレムリンの皇女スヴェトラーナの生涯 上・ 下』(ローズマリー・サリヴァン、染谷徹訳、白水社、2017年)
第3回
『黙示録 映画プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』 (春日太一、文藝春秋、2019年)
『二重らせん 欲望と喧騒のメディア』(中川一徳、講談社、2019年)
第4回
『ルポ 東尋坊 生活保護で自殺をとめる』(下地毅、緑風出版、2021年)
『愛をばらまけ 大阪・西成、けったいな牧師とその信徒たち』(上村真也、筑摩書房、2020年)
『沢村忠に真空を飛ばせた男 昭和のプロモーター・野口修評伝』(細田昌志、新潮社、2020年)
第5回
『細野晴臣と彼らの時代』(門間雄介、文藝春秋、2020年)
第6回
『親愛なるレニー レナード・バーンスタインと戦後日本の物語』(吉原真里、ARTES、2022年)
『亡命トンネル29』(ヘレナ・メリマン、中島由華訳、河出書房新社、2022年)
角岡
ジャンルがバラバラ、なんでもかんでも読む感じ、国内も海外も対象にしているから世界にほとんど例のないノンフィクション賞やねん。
西岡
こういう本をどういうきっかけで読むんですか。
角岡
本屋に行って、おもしろそうなノンフィクションを買うか、書評もあるし、広告もあるし、あと、ネットで見つけたりします。
芝浦屠場で7年間、働き続けたライター <私>が大きなテーマ 『芝浦屠場千夜一夜』
西岡
それで、第7回ですが。
角岡
今年の3月末に発表しました。まずは『芝浦屠場千夜一夜』(山脇史子、青月社、2023年)。この本がすごいのは、ライターである著者が90年代から東京の品川にある屠場に働きに行って、その屠場を7年間も取材して、去年になって本にしたという、時間のかけようがすごい。なんで本にならなかったかというと、部落問題がからんでいたり、職業差別がからんでいたり、なかなかOKが出なかったんです。
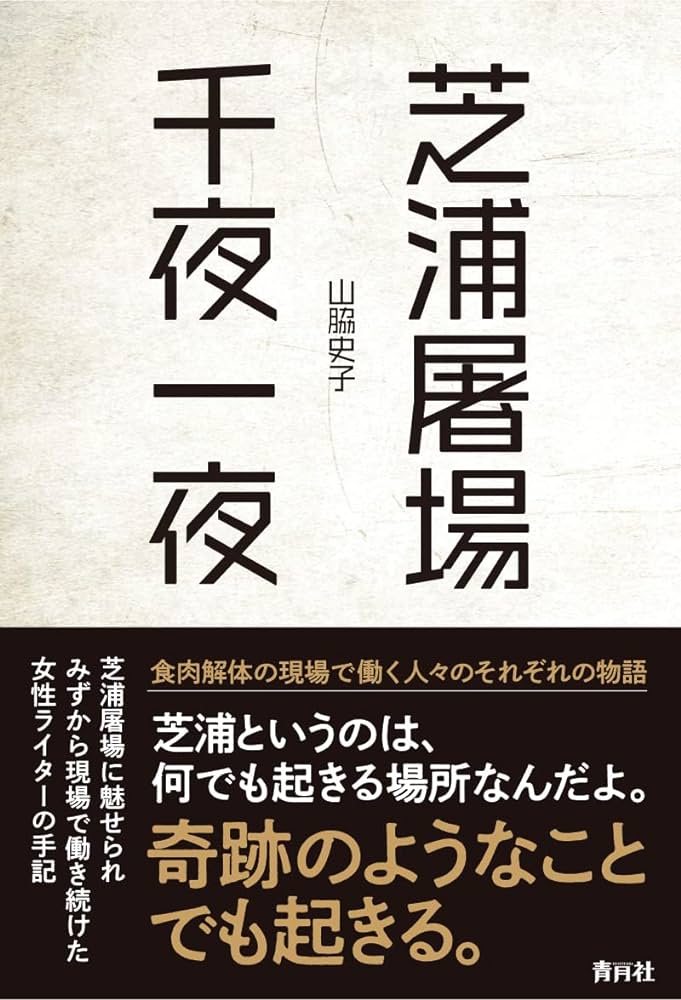
西岡
著者もすごいですけど、これを本にしようという編集者がえらいですよね。角岡さんは、ずっと部落問題のことを書いてきはって、どこがすごかったですか。
角岡
なぜ屠場に行きたいのか、なぜ屠場を取材するのか、という問題意識を書いたらどうかと友人にすすめられて、自分のこととか、自分の家族のこととかを書いている、それが成功しているかなあと思います。屠場というのは、元々部落にあったり、部落の人が働いていたりするんで、部落問題と密接に結びついているんだけど、著者は友達が差別的な発言することに違和感を持ったり、父親との関係で引っ掛かりがあって、その引っ掛かりってなんやろか、というのが屠場の取材につながっていく。自分がらみで書いてあるところがすごくいいなあ。例えば、こんなことを書いてはるねんなあ、読むわな。
<人に会って話を聞くことは面白かったが、短い取材時間で企画意図に沿った話だけを、手際よく聞いてまとめるやり方に、物足りなさや寂しさを感じるようになっていた。それ以上に、私自身が「何を知りたいのか」がわからなくなっていた。記事を書くために何が必要かはわかる。誰に何と何を聞いて、何を確認すれば記事になるかはわかる。でもそれは自分の知りたいこととは違う。
私は「納得」したかった。何を納得したいのか。少なくとも自分がなにかをわかったと思いたかった。なにかを理解したうえで、きちんと「仕事」をしたかった>
角岡
西岡が神戸新聞を辞めるきっかけとよく似てるよな。
西岡
何を聞かなあかんのか、何を確認せなあかんのか、どうやったら記事になるのか、それはわかんねんけれども、それを書いてどないすんねんって。そんなんNHK見といたらいいやんみたいなところがあって、それが嫌という訳ではなくて、借り物の服を着せられているような感じ。僕が新聞記者のとき、仕事はこなせるけど、違和感が積もり積もって、結局、自分は何が書きたいねんとか、何がやりたいねんというので、新聞社を辞めたというのはありますよね。
角岡
けっこう、西岡とも重なるなあ。
西岡
新聞が嫌いか嫌いじゃないかと言えば、嫌いでもないんです。新聞記者は定型から覚えさせられるんですよね。火事原稿の書き方ってあるんですよね。何月何日、どこどこから出火、何々と見て調べている、みたいな書き方。速報性が必要なんで定型を徹底的に叩き込まれるんですね。いい学校に入ったんやけど、制服が合わないなあという感じが新聞社に入って、ものすごくあって、次に行ったのが無茶苦茶な雑誌やって、極端な話、定型なんかない。それからフリーになって、はじめて、自分は何が書きたいのか、何に興味があるのか、わかってきた。

角岡
もう一つ、読みたいところがあんねん。<私>が大きなテーマで、最後の方にこんなこと書いてはんねんね。
<「私」と文字にするだけで違和感がある。自分を書きたいと思わない。書きたいのは私が通った芝浦だ。そこに居た人々だ。書きたい、書こうと思いながら、書き上げることができないままに時間がたってしまった。
「そんな昔のこと今書いて出すことに意味があると思えないよ。あえて意味を見出すとしたら、あなたの物語にすることですよ」
そうアドバイスしてくれたのは、森なのだ。
「あなたぐるみでなければ、読み手には伝わらないよ。世の中に自分を離れて客観的事実なんてないんだから。世の中は自分込みの世界なんだから。全部書いちゃえよ」
そもそも、なぜあなたが芝浦にこだわり続けるのか。わからないわけではないけどね、と続けた>
角岡
森さんはライターの森幸江さんのこと。最後まで読んでまうわな。
<「そこで働いている人は、それなりの必然があってそこで働いている。それなのに、いやになったらいつでも逃げられるおまえのような立場で関わるのはひきょうだ」
声が死んだ父になる。芝浦のことを初めて話した時のことだ。
「それなら私、死ぬまで芝浦にいます」
思わず言い返すと、
「ばかな。絶対に反対だからな」
と怒った。その父も死んだ。
受け入れてくれた伊沢さんも死んだ。芝浦での私の居場所もなくなった。
それなのに、今ごろになって芝浦のことを書いている。自分の頭の中身を外に出したい。私が死んだら私と一緒に消えていくもの、誰も代わりに語ってくれないものを書き残しておきたい>
角岡
私が死んだら自分が体験したことは跡形もなく消えていく。そういうことを、父親が亡くなり、世話してくれた人が亡くなり、同業者の森さんも亡くなっていく、死が重なったこともあって、この本をつくってはるから、<私>がある意味、主人公。だからこそ、リアリティーがあることが書けてるなあと思います。
西岡
めっちゃ取材してはるから、<私>が出てきても、違和感がないんでしょうね。めっちゃ取材してはるからこそ、<私>が出て来た時、この人こんな思いでやってはったんやというのが自然に溶け込むから、すごく効果的かなあと思います。亡くなった森さんというライターのアドバイスもそうやろと思います。誰とは言いませんけど、ノンフィクション作家とか名乗る人で<私>と言いはるんやけど、<私>と名乗れるほど取材してへんやないかって、いうような時に、滅茶苦茶、違和感を感じるんですけど。
西岡
角岡さんは、<私>を書いている本はあるんですか。
角岡
部落問題は、僕は当事者なんで、どこかに入れるようにしている。
西岡
講談社ノンフィクション賞をとった『カニは横に歩く 自立障害者たちの半世紀』(角岡伸彦、2011年、講談社)もそうですもんね。
角岡
障害者のノンフィクションで、ぼくは介護者。
西岡
その話、書いてはりますもんね。
角岡
どういうふうに<私>を登場させるか、むずかしい。この本は最初の方は全然、<私>が出て来ない。芝浦屠場の30年ぐらい前の話がずっと出てきて、読んでて、この人なんで屠場を取材してるんやろなあと思って、真ん中辺ぐらいで出て来るねんな。それは、屠場の人がなんでお前ここ取材して来てんねんと言われて。
西岡
突き付けられてから、もうどうしようもなく、出さなしゃーない。ほんまはあんまり出したくないわけですよね。オレがオレがのタイプやないんや。
角岡
全然、違う。屠場のリーダーに作文を書いて来てよと言われて、なぜ屠場を取材したいのか、それを書いてて、この本の中に出て来る。その文章が非常にいいねん。父親が転勤族で関西に暮らしていた時に部落問題を知って、父親との確執もあって、自分の差別意識と絡んでくる、それを書いていて、読んでいてすっと入ってくる。
西岡
月刊誌『文藝春秋』で『部落解放同盟の研究』(2022年1月が第1回、連載は7回)で、芝浦屠場のことを書いて、芝浦屠場の労働組合を運営している人たちが滅茶苦茶、意識がしっかりしているんですね。追及の仕方もものすごく論理的。そんなところで取材をやりはったなあと思いますね。著者の山脇さんも試されたんやなあ。
角岡
山脇さんは、芝浦の労働組合が戦闘的に闘っている組合やってのを人づてに聞いて、それで興味を持ったというものあるんです。
西岡
なるほど。
角岡
だから、芝浦の労働組合が当時、屠場をめぐる表現で、マスコミや映像、活字の世界を糾弾して、その時の状況がこの本にたくさん出てくる。このことについて、山脇さんがこう考えたとか、こう考えるべきやとか、そういう書き方でもない。ニュートラルな書き方。そこも非常に資料的価値がある。
新人時代の失敗と反省、解放教育との出会い、市長へ送った「提言書」、大人になった教え子との再会… 『僕の好きな先生』
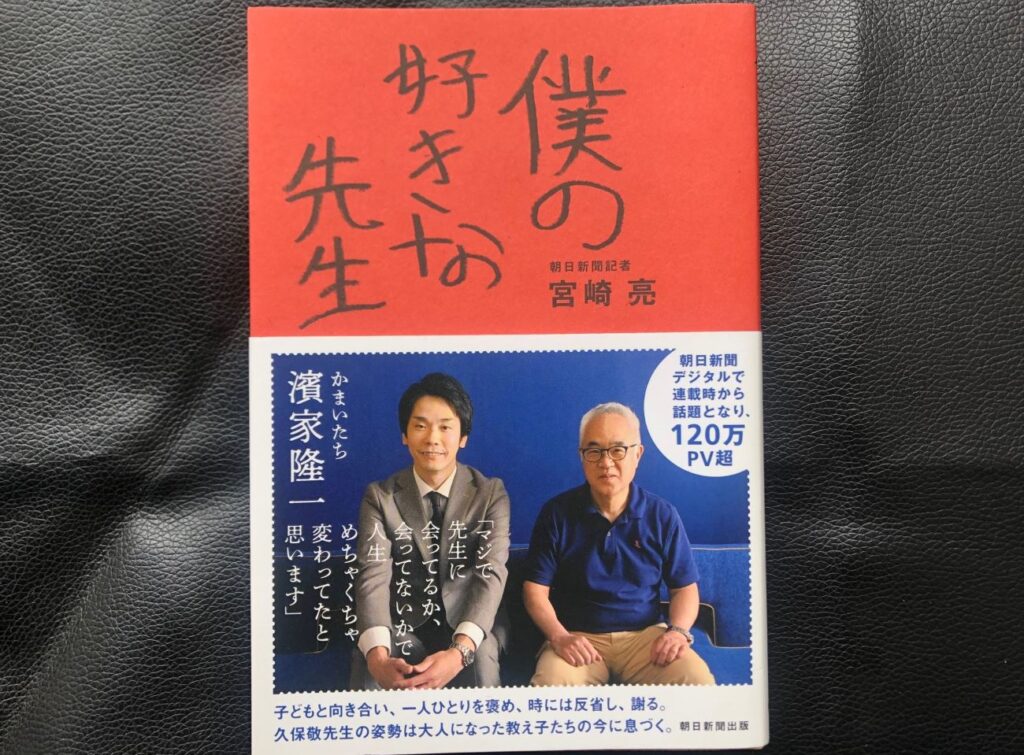
西岡
受賞作のもう一冊は。
角岡
『僕の好きな先生』(宮崎亮、朝日新聞出版、2023年)。元々の話をするとやね、久保敬先生、一昨年、定年退職しはったんやけど、コロナの時に小学校の校長をやってはって、当時の大阪市長の松井一郎のコロナ対策に対して、提言書を郵送したんやけど、それがSNSで出回って、すごく大きな問題になって、朝日新聞の宮崎記者が取材に行くねんけど、宮崎記者がいろいろ話を聞くと教え子に、お笑いコンビのかまいたちの濱家がいた。久保先生は教え子に慕われる先生で、教師一年目から退職されるまで、ずっと追っている。
西岡
僕、宮崎君のこと、よう知ってるんです。すごくセンスのいい記者なんです。角岡さんが説明された通り、松井がトップダウンで、パソコン導入してモバイルで授業を展開していくと、久保先生は、現場はそんな態勢ができていない、大混乱に陥るから待ってくれやと。久保先生のええところは、オラーっていう運動家じゃないんですよね。これアカンとなって、止むに止まれず、オレ定年退職やし、いうようなところで、提言書を出して、最終的には教育委員会と争うことになるんですけれでも、自分の身を賭してやると。それで宮崎君が取材しに行く。この本のいいのは、久保先生が完全無欠の教育者じゃないというところを、久保先生の歩みと同時に書いているところが抜群にいいんですよね。もう一つ、久保先生の礎をつくったのが解放教育やったというところをきちっと抑えてて、それが久保先生の基礎をつくってて、でも、肩に力が入りまくって失敗するところから書いているんですね。

角岡
さっきの『芝浦屠場千夜一夜』は30年前の話から書いて、今の屠場も書いているんだけど、『僕の好きな先生』は今起こっていること、すぐ取材してすぐ書く。それってなかなかできることではない。一回ストレートニュースで提言書のニュースを書いてんねんけど、それだけで本にならなかったし、そのつもりもなかったやろけど、教え子に濱家がおったり、濱家だけやなくて、他の児童、そのかかわりとか、失敗談とか、いろんなことを書いている、そこの馬力がすごいなあ。
西岡
すごい、すごい。朝日新聞出版から本を出すことが決めてから、その当時の子どもの追っかけぶりもすごいですよ。当時の子どもで、あの子はどこにおんねん、延々追っかけている。宮崎君に聞いたら、追っかけて本に出せなかった子もけっこういるみたいですよね。取材の蓄積で書かなかった部分が多いだけにけっこう、いい本になっているなあと思います。
角岡
ノンフィクションも新聞記事も一緒やけど、取材対象の人間がどれだけおもろいのか、大きいやんか。主人公だけでなくて、脇役もそうだし。
西岡
そうそう。
角岡
そういう意味で、この先生がいいなあ。
西岡
いい先生ですね。
角岡
昔の教え子を取材したら、おもろかったというのもおもしろいし、それも先生が学級通信を書いてはって、それは生活綴り運動の流れなんやと思うんやけど。それが記録として残っているのが大きいやん。我々、書き手にとって、それを見たら児童がどういう状況やったのか、先生が何を考えていたのか、それがわかる資料があるっていうのがいい。それを教え子が残しているとか、濱家が、先生が書いた学級通信全部残してたっていう、それだけ慕われたっていうことが、読んでたらわかるもんね。
西岡
そうですね。
角岡
そういういろんな素材と言うたら言葉悪いけど、取材対象もそうやし、資料もあるし、記者の馬力もあるし、文章力もあるし、というのですごくいい本だった。
西岡
そうですね。さっき角岡さんが言った綴り方教室というのは本人に確認したことないですけど、あっ、こんにちは。
宮崎亮さんが遅れて、会場に到着。
西岡
宮崎君、綴り方教室というのは昔から取材してたん。
宮崎
10年ぐらい前からですね。
西岡
蓄積があったのが大きかったと思いますね。
宮崎記者は、2016年3月から『安井小 こころの作文』という題で17回にわたって朝日新聞大阪版に連載した。「生活綴方」と呼ばれる作文教育法に取り組む堺市立安井小学校を宮崎記者が1年間、密着取材した。安井小学校講師の勝村謙司さんと宮崎記者の共著『こころの作文 綴り、読み合い、育ち合う子どもたち』(かもがわ出版、2018年)に、子どもたちの物語が子どもたちが書いた作文とともに紹介されている。
10年間、移民の子どもたちの学習支援ボランティアをしてきて見えたこととは。 『移民の子どもの隣に座る 大阪・ミナミの「教室」から』
MoMoBooks松井
この2冊が第7回角岡伸彦ノンフィクション賞なんですけど、西岡さんも…。
西岡
角岡さんがノンフィクション賞をつくった時、大変やのになあと思っていたから、僕はたまたま会うた本で、賞をあげたいなあと思う本だけに賞をあげるという限定にしました。賞を自分でつくりたいなあと思うぐらいの本ははじめてですよ。
角岡
これを読んで賞をつくりたいと。
西岡
そうそう。『移民の子どもの隣に座る 大阪・ミナミの「教室」から』(玉置太郎、朝日新聞出版、2023年)には、賞をあげたいなあ、それぐらいすごくよかったです。
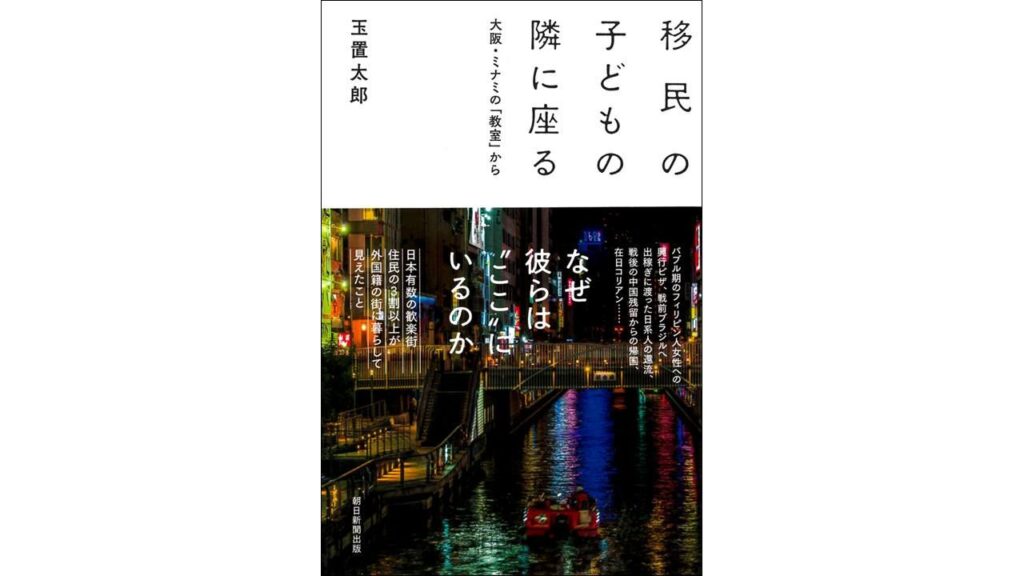
角岡
大阪ミナミの島之内に外国籍の子どもがいっぱいいて、その子たちの課外教室というかね、それをずっと追っている作品ですね。その教室に著者の玉置記者がボランティアとして参加して、子どもたちの様子や親たちの生活を綴っている。どこがよかった?
西岡
まずね、これも<私>がちゃんと出ている本ですよ。移民の子どもの隣に座るんやけど、新聞記者として君たちのことをいつか書くために座ってんねん、それをいつ言おうか思いながら、モヤモヤしながら、子どもの隣に座っているんです。
西岡
新聞記者らしいなあと思うのは、宮崎君もそうやし、この本の著者の玉置君もそうやし、事件をきっかけにしている。フィリピンの子どもが亡くなる事件がきっかけ。その時、玉置君は大阪府警担当で、事件が起これば右から左に書いて、はい終わりました、みたいな感じになってたなあと、移民の人たちにずっと引っ掛かりを持っていて、移民の子どもたちの勉強会のボランティアとして参加していく、そこがすごくいい。新聞記者が持っている業をも抱えながら、しゃっちょこばった問題意識じゃない。その事件で今までずっとボランティアとして取り組んできた人らがどれだけ衝撃を受けたか、その事件を機に教室が始まったという歴史的な経緯も書いています。もう一ついいのは、取材しまっせ、はいどうぞ、というような関係じゃない。例えば、課題がある地域とか、課題がある人たちにかかわって、文字にするって、滅茶苦茶むずかしいやないですか。関係が壊れることもあるやろし、もちろん、ボランティアしながら途中途中で記事にしながらやってるんですよね、関係性をずっとつなぎながらやっているのがすごい。
角岡
記者しながら、ボランティアを毎週行っているのは、ようそんなことやるなあと思いました。イギリスに留学して、イギリスの移民の子どもたちはどういうふうに生活しているのか、取材しているのもすごいね。
西岡
玉置君は本のなかで多様性について毒づいていますけど、毒をはいているところもいいんですけれども、多様性という簡単な言葉というのは、実践するのがどれだけしんどいのか、それが滅茶苦茶よく描けている本だと思いました。
(つづく)
●編集担当:文箭祥人 1987年毎日放送入社、ラジオ局、コンプライアンス室に勤務。2021年早期定年退職。






















コメント