筆者(文箭)は2007年から大阪・毎日放送ラジオ報道部記者として空襲被害者の補償問題を取材テーマに空襲被害者や研究者、弁護士に話を聞き、番組をつくり放送してきた。その後、報道現場を離れたが、今も空襲被害者の補償問題に関わり続けている。戦後80年にあたり、日本の空襲の歴史を振り返り、戦争被害受忍政策によって未補償のままになっている空襲被害者の補償問題を考えようと思う。以下の原稿は、今年5月に広島のSocial Book Cafeハチドリ舎で、7月に大阪の15年戦争研究会で報告した内容を基にしている。
空爆は軍事目標に対して行うべきとされていた
1923年、国際連盟のハーグ法律委員会が「空戦に関する規則」案を作成し、爆撃は基本的に軍事目標に対して行うべきで、軍事目標に対する爆撃でも、民間人を巻き込む可能性がある場合は避けることとされた。正式な条約にはならなかったが、日本を含めた各国は指針として、この案に沿うことを認めていた。(『東京大空襲・戦災資料センター図録』)
日本軍は中国に無差別爆撃を行い、多くの中国人が死傷した
1931年満州事変が起こり1937年日中戦争が始まった。日本軍は中国の各地各都市を空爆。中でも、1938年2月から1943年8月までの5年半、重慶を200回以上空爆。「重慶大爆撃」と呼ばれている。南京陥落後、国民政府は首都を揚子江上流の重慶へ移転。政府機関、各国大使館、工場、大学などは日本軍の占領から逃れて重慶に移動、多くの住民も重慶に避難した。人口は30万人から70万人以上と膨らんだ。日本軍は重慶まで直線距離780キロの武漢まで追撃したが、それより先は山岳がそびえ立ち、追撃ができないと判断、空爆のみの作戦が考え出された。
アメリカ人カメラマンのレイ・スコットが1939年から1940年にかけて中国各地を撮影し、記録映画『苦干』(くかん)を制作。後半に地上から撮影した重慶大爆撃の映像がある。撮影日は1940年8月。1942年アカデミー賞記録映画特別賞を受賞。2010年、米国籍中国人の映像作家により再発見された。『苦干』はネットで配信されていて、誰もが観ることができる。月刊誌『世界』(2022年10月号)に「座談会 重慶大爆撃から考えるウクライナ戦争」の中でこの映画が紹介されている。冒頭の写真は『苦干』の一場面。
◆『苦干(重慶大爆撃)』(14分22秒)
https://www.dailymotion.com/video/x8rgpyo
重慶大爆撃による死者は1万1000人、負傷者1万数千人にのぼる。歴史家の荒井信一、ジャーナリスト前田哲男、一瀬敬一郎弁護士らがメンバーの「戦争と空爆問題研究会」はその著書『重慶爆撃とは何だったのか』(発行:2009年、高文研)に重慶爆撃の全体像を次のように示す。
- 日本軍の重慶爆撃は、「戦政略爆撃」なる名称を公式に掲げて実施された世界最初の「意図的・組織的・継続的な空中爆撃」であった。
- 爆撃は都市そのものを対象とし、焼夷弾投下の必然の帰結として、被害の大半は住民の身体と住居に降りかかった。
- 手法が徹底的に「眼差しを欠いた殺戮」であった。攻撃は、高度数千メートルから爆弾を投下することによってのみ遂行された。数年後、日本に行われた、より強力な油脂焼夷弾による空襲、その原型は、ここ重慶に刻まれているのである。それは東京にとって、「投げたブーメランが戻ってきた」というつながりをもつ。

今年4月、重慶大爆撃の被害者らがメンバーの「重慶・沖縄平和訪問団」が沖縄を訪問した。重慶・沖縄平和訪問団は4月6日に那覇市内で、沖縄の「南京・沖縄をむすぶ会」と「ノーモア沖縄戦命どぅ宝の会」が共催する交流会集会に参加し、重慶大爆撃の被害者は自身の体験を語った。地元紙・沖縄タイムスが交流集会の内容を報じた。その一部を引用する。母や祖母、弟ら親族6人を亡くした蘇良秀さん(空爆当時11歳、現在は95歳)の娘である馬欄さん(61歳)は「より多くの人に重慶大爆撃の歴史を知ってもらいたいと母はよく話していました。平和を愛する中国と沖縄の人々が協力し、再び戦争が起こらないように願います」と語った。被害者を支援する徐斌弁護士は「沖縄は中国に対する戦争準備の最前線の場所。だからこそ今回の民間交流は日中の友好のために重要な意義がある」と述べた。「南京・沖縄をむすぶ会」の沖本裕司さんは「日本は中国にミサイルを向けるような国ではいけない。日本は重慶大爆撃の被害者の賠償にもっと真摯に向き合うべき。それが今後の日中友好につながっていく」と訴えた。
太平洋戦争時、米軍は日本に無差別爆撃を行い、多くの民間人が死傷した
第2次世界大戦が始まると、アメリカは高高度・長距離の飛行が可能なB29爆撃機、日本の家屋を想定した焼夷弾を開発。焼夷弾は、火のついた粘着性の強いガソリン(ナパーム剤)を家屋内にまき散らすように開発された。日本の家屋を再現した建物を建て、燃焼実験も行った。当初、アメリカ軍の空爆は軍需工場などを狙う精密爆撃が中心だった。その後、無差別爆撃を行うようになった。1945年3月10日の東京大空襲は、B29による焼夷弾の無差別爆撃で10万人が亡くなったとされている。空襲は東京や大阪、名古屋などの大都市から地方都市に広がり、空襲は終戦当日の1945年8月15日未明まで続いた。
精密爆撃から無差別爆撃に切り替えたアメリカ軍、その背景は?
200人を超えるアメリカ軍将校の録音テープが残っていることがわかった。2017年8月に放送された、NHK・BS1スペシャル『なぜ日本は焼き尽くされたのか』は、そのアメリカ軍将校246人の証言から、日本への空爆の真相に迫った。その中からごく一部を紹介したい。
太平洋戦争時、アメリカ軍において空軍は陸軍の下部組織だった。そのアメリカ陸軍航空軍を率いていたのがアーノルド大将。一人の将校は「アーノルドは空軍独立を貪欲なまでに追い求めていた」と証言。日本に対して、アメリカ陸軍航空軍は軍需工場などを爆撃する精密爆撃を続けたが、「失敗」が続いた。その後、空軍独立の野望を持つアーノルド大将は「都市への焼夷弾攻撃を試せ」と指令。そして、1945年3月10日。ナレーションは「B29は合わせて1600トンを超える焼夷弾を積んで東京へ向かった。空軍独立の野望と、戦果を求める声、そして現場への圧力。無差別爆撃がついに実行された」。番組の終盤、ナレーションは「終戦から2年後、日本を焼き尽くしたアメリカ陸軍航空軍は、太平洋戦争での戦果が認められ、悲願だった独立を果たした」。2021年、番組内容を大幅に加筆した『日本大空襲「実行犯」の告白』(著:鈴木冬悠人、新潮新書)が刊行された。
アメリカ軍の空爆に対して日本政府は国民にどういう対応をしたのか?
1941年、防空法により「逃げるな、火を消せ」が義務化された。政府は国民向け冊子『時局防空必携』を発行。『時局防空必携』(昭和十八年改訂)の表紙を開くと「一、重要な都市の家庭には必ず一冊づつ備へ、全員これをくり返し讀み合つて理解して置く。隣組でも常會で研究する」などと書かれている。次のページには「防空必勝の誓」が記されている。最初に「私達は「御國を守る戦士」です。命を投げ出して持場を守ります」と記述。
東京大空襲の4日後、貴族院本会議で、貴族院議員・大河内輝耕が「火を消さなくてもよいから逃げろ、と言っていただきたい」と質問、大達茂雄内務大臣は「どうも初めから逃げてしまうということは、これはどうかと思うのであります」と答弁。防空法が廃止されたのは戦後の1946年1月31日。
空襲被害の実態はわかっているのか?
空襲による犠牲者数を新聞や放送がどう報じたか調べた。その一部を紹介する。1994年、東京新聞は「空襲による民間人の犠牲者数は、いまだ確定できないが、65万人と推定されている」と報じた。2017年8月12日放送のNHKスペシャル『本土空襲 全記録』は自治体が蓄積したデータをベースに「死者45万9564人」と報じた。放送内容を書籍化した『NHKスペシャル本土空襲全記録』(2018年、KADOKAWA)に「アメリカでも日本でも「本土空襲の全貌」と向き合う姿勢は、これまで十分だったと果たしていえるのか。そんな疑問が自ずと湧いてくる。実際には、「本土空襲」と向き合ってきた者がいるとすれば、それは何よりも日本の市民であった」と書かれている。2025年3月9日、朝日新聞「戦後80年企画」記事で「戦後は都市の復興が優先され、詳細な全国調査は行われず、全容はいまだ明らかではない。東京大空襲・戦災資料センターは、各地の地域史などに残る記録を集計したところ、原爆を除く一般空襲の死者は約20万3千人だった。実際はさらに多いと見られている」と報道した。2025年5月7日、毎日新聞は自治体の調査を元に「空襲犠牲者50万人超に及ぶとされる」。このように死者の人数が明確になっていない。
犠牲者は日本人だけではない
『東京大空襲・戦災資料センター図録』には「東京都で戦災を受けた朝鮮人は、少なくとも4万1300人いたことがわかっています」と記述されている。大阪では、1230人の朝鮮人が空襲で亡くなったと推測されている。
朝鮮半島や中国大陸から多くの人が強制的に連行され、過酷な労働を強いられた。大阪では1千人を超える中国人が強制連行され働かされ、86人が死亡し、そのうち8人が空襲で亡くなったことがわかっている。大阪において、朝鮮人強制連行者は1944年末に約1万3千人で、70人から100人が空襲で死亡したと推測されている。大阪の収容所にいた連合国捕虜3人が空襲で亡くなったことがわかっている。
空襲被害者は国との雇用関係がないから補償しない
1952年4月28日、日本は主権を回復。その2日後に戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下、援護法)が制定された。国家補償の精神に基づき、軍人・軍属を援護するという法律で、障害者本人には障害年金、死亡者の遺族には遺族年金などを支給するというもの。民間人戦争被害者は適用外とした。1953年、GHQの指令により廃止されていた軍人恩給が復活した。恩給は国家補償を基本とする年金制度。軍人やその遺族の大半は援護法適用から軍人恩給に移行した。戦後補償において、政府は軍人軍属を補償する一方、民間人である空襲被害者を放置した。その根拠理由は、国との雇用関係がないということだ。
1972年、杉山千佐子が一人で全国戦災傷害者連絡会(以下、全傷連)を立ち上げた。29歳だった杉山千佐子は1945年3月24日、名古屋空襲の時、防空壕で生き埋めになり、爆風を顔に受け、その結果、左眼球摘出、左頬に傷跡が残り、鼻の上部をえぐりとられた。全傷連は①空襲その他による一般民間戦災犠牲者(傷害者、死没者遺族)に対する援護法の立法化を国に要請すること②一般民間戦災傷害者の実態調査を国ならび地方の自治体に要請することを目的とした(後に調査に死没者が含まれるようになる)。
全傷連の運動を支援する国会議員が現れ、運動は急速に広がった。社会党が戦時災害援護法案をまとめた。法案の内容は、空襲その他の戦時災害によって身体に被害を受けた者及び死亡した者の遺族に対し、軍人・軍属に対する援護法と同様に、国家補償の精神に基づく援護法を制定すること。1973年、社会党が国会に法案を提出したが、廃案になった。1975年、参議院本会議で三木武夫首相は「民間戦災傷害者は国との雇用関係がないから法律で救済する気はない」と答弁。戦時災害援護法案は、1973年から1989年まで16年半にわたり合計14回、国会に提出されたが、実現しなかった。
杉山千佐子は自身の半生を書いた『おみすてになるのですか』(著:杉山千佐子、発行:1999年、クリエイティブ21)に「さんざん国民を国のために働かせておいて、けがをしても、国に補償の義務はないなんて、こんなばかな話があるでしょうか。この法律を成立させないということは本当に、国民を軽く見ているということです。私はこの法律は、私たちだけでなく、のちの世代の国民が国に簡単に踏みにじられることのないよう、その人権を保障した法律でもあると思っています」と書く。
政府、自民党は空襲被害者と被爆者との「均衡論」を持ち出した
1956年結成の日本被団協は国家補償の被爆者援護法制定を要求し、全傷連は国家補償の戦時災害援護法制定を要求した。2つの団体が運動をすすめる中、政府、自民党は「均衡論」を持ち出した。全傷連会長の杉山千佐子は「国は被爆者に対しては「戦災傷害者との格差をつけることはできない」と被爆者援護法を拒否し、戦災傷害者に対しては「放射能障害の遺伝の恐れのある原爆被爆者にさえ国家補償をしていないのだから、お前達にできるはずがない」と拒否しているのです」と均衡論を批判した(全傷連の会報『傷痕』(1980年、第7号)。
全傷連は両援護法制定運動を「車の両輪」と考え、両援護法制定を要求した。一方、日本被団協は「私たちは、一般市民の戦争犠牲者についても、すべて国の責任で補償されるべきだと考えます。被爆者に対しては、その被害を全面的に補償し、一般市民の戦争犠牲者補償への第一歩とすべきではないでしょうか」(会報『被団協』、1980年、第23号)とした。
実際、運動の現場はどうだったのか。『傷痕』(1981年、第8号)に「毎年広島で長崎で叫びつづけてきましたが、耳をかたむけてくれる被爆者は少なくいつも悲しい思いでした。しかし本年は長崎大会へ私を招き共に連帯してたたかう事を約束してくれました」とあり、被爆者側からは「自民党が長い間(20年も)「一般戦災者との均衡論と波及阻止」をもち出していたため、被爆者の中に一般戦災者との違いを強調する風潮のあったことは事実です」という証言(1994年)がある。
戦争によって被害を受けたとしても、国民は受忍(がまん)しなければならないとする「戦争被害受忍論」
1980年、被爆者対策の基本理念を検討するため設置された、厚生大臣の私的諮問機関の原爆被爆者対策基本問題懇談会が意見書を提出した。そこに書かれているのが「戦争被害受忍論」。その部分を引用する。「およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態のもとにおいては、国民がその生命・身体・財産等について、その戦争によって何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは国をあげての戦争による「一般の犠牲」として、すべての国民がひとしく受忍しなければならない」。「およそ戦争」としているが、「およそ」は「一般に」の意味。「戦争被害受忍論」は被爆者だけでなく空襲被害者ら戦争被害一般について受忍を強いる。

全傷連の運動を全国空襲連が引き継ぐ
全傷連の活動は2013年に終わるが、全傷連の運動は2010年結成の全国空襲被害者連絡協議会(全国空襲連)に引き継がれた。2015年、自民党国会議員を会長とする超党派の空襲議員連盟が発足。全国空襲連と空襲議連との間で協議などが継続して行われ、2020年に空襲議連が法案のもととなる要綱案をまとめた。要綱案は①空襲等で障害を負った生存者を対象に一人当たり一時金50万円を支給すること②被害の実態調査の実施。遺族を対象外としたが、それは、立法の実現を優先するための苦渋の選択だった。
いまだ空襲被害者に対する法律は存在しない
2025年3月、立法化について石破首相が国会で「次の世代に対する責任として行政が判断をしなければならない問題と理解をしているところでございます」と答弁した。
2025年5月8日、空襲議連が総会を開催し、法案を決定した。法案決定は空襲議連が結成して、はじめて。法案は「前文」から始まる。「前文」は衆議院法制局が事務的に整えたもの。「前文」の後半、「戦争被害受忍論」が出てくる。「空襲その他の災害による被害については、戦争という非常事態の下で生じた被害は国民が等しく受忍しなければならないやむを得ない犠牲であるとして、国会及び政府において、これを救済するための取組はなされてこなかった」とある。国会及び政府は「戦争被害受忍論」を根拠に空襲などの民間人被害者を救済してこなかったと明記されている。「前文」には続けてこう書かれている。「ここに、戦後八十年のときを迎えるに当たり、我々は、恒久の平和の実現への決意を新たにするとともに、空襲その他の災害によりその心身に障害や傷跡を受けた者の長年にわたる多大な労苦に鑑み、国として、これを慰謝し、及び空襲その他の災害による被害の実態を明らかにしてその犠牲者へ追悼の意を表するため、この法律を制定する」。
法案の内容は①「空襲その他」で心身に障害を負い、現在存命する人に一時金50万円を支給 ②「空襲その他」の被害の実態調査の実施 ③「空襲その他」により亡くなった人を追悼する事業の実施。国籍条項はない。担当省庁は厚生労働省。「空襲その他」は国内の空襲・艦砲射撃及び沖縄地上戦を指す。沖縄戦を体験した高齢者の4割が戦争PTSDを含む外傷性精神障害に罹患している可能性が高いことが判明している(2013 年沖縄の研究グループが調査)。空襲被害者にも精神障害に苦しんでいる人がいるのではないだろうか。
空襲議連が総会で法案を決定した後、各党は党内手続きに入った。野党が法案に賛成する一方、自民党と公明党の賛成を得るに至らなかった。
6月19日、空襲議連は総会を開き、与党が法案賛成に至らなかった現状から今通常国会での法案提出の見送りを決めた。総会で平沢勝栄空襲議連会長(自民党)は「不思議でしょうがないのは、なんでこれが通らないんだろう。この法案は国会議員のほとんどが賛成しているんです。反対している人にほとんど会ったことがありません。しかも、反対している人もいますけれども、予算が足りないとか言うならわかりますけど、その話でも何でもないんです。なんかよくわからないけど反対している」と述べた。また、同年3月の空襲議連の会合で松島みどり空襲議連事務局長(自民党)は「厚労省は反対している」と説明した。
総会で松島みどり事務局長が法案の前文を読み上げたが、「戦争被害受忍論」部分を読み上げる前に、「ここからが大事です」と付け加えた。松島事務局長は前文の読み上げ後、法案内容を説明し、実態調査に関して、「これまでいったい、全国のどこでどれほどの空襲が行われ、何人の方が亡くなり、あるいは、けがをされたということについての記録を日本は持っていません。これはやはり日本の政府として、遅きに失した感はありますけれども、専門家、郷土史家、歴史家の手を借りて、それを解明していくべきだと考える」と述べた。総会で空襲議連は、秋の臨時国会での法案の国会提出、成立を目指すとした。全国空襲連も運動を継続し、今秋の臨時国会での制定を目指すと表明した。8月5日、全国空襲連は総会を開き、空襲議連の国会議員から「全力で取り組んで行く」「尽力する」とのメッセージが届いた。全国空襲連は「秋の臨時国会で救済法の実現を!」のスローガンの下、空襲議連と緊密に協力し、運動を継続する決意を表明した。


「戦争被害受忍論」に対する批判
<およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態のもとにおいては、国民がその生命・身体・財産等について、その戦争によって何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは、国をあげての戦争による「一般の犠牲」として、すべての国民がひとしく受忍しなければならない>(1980年12月11日、基本懇の意見書から)
基本懇が意見書を提出したその日、日本被団協は声明を発表。戦争被害受忍論に対して「一般市民の戦争被害に対し国が今日まで何らの措置を講じて来なかったことを当然視している。これは、国の戦争責任を問おうとしないのみならず、戦争を肯定する姿勢といわざるをえない」。
1981年1月6日発行の日本被団協の会報『被団協』に「平和憲法 ふみにじる基本懇」の見出しで各界の声が掲載された。家永三郎(歴史学者)は「一国あげての存亡にかかわる戦争だから国民は被害を受忍しなければならないというのは、戦前の戦争国家体制下の考え方と同じで、日本国憲法の平和主義を全く度外視したこの姿勢に非常な怒りを感じます」とコメント。
2006年に日本被団協が発行したパンフレット『原爆被害者の基本要求』に「「受忍」政策は、被爆者をはじめ一般空襲被害者、中国残留孤児など、アジア・太平洋戦争で日本政府が生み出した戦争被害に押しつけられてきただけでなく、その網はさらに“これからの戦争”にも広げられようとしています。周辺事態法、武力攻撃事態法、それに基づく国民保護法などでは、国(の戦争政策)に協力した者以外の戦争被害は「受忍」せよといっています」と記述。
2024年12月、ノーベル平和賞授賞式で日本被団協の田中熙巳さんが演説した。その中で、「日本被団協は二つの基本要求を掲げて運動を展開してきました。一つは、日本政府の「戦争の被害は国民が受忍しなければならない」との主張に抗い、原爆被害は戦争を開始し遂行した国よって償われなければならないという運動」と述べた。さらに「もう一度繰り返します。原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府は全くしていないという事実をお知りいただきたいというふうに思います」と訴えた。日本被団協は6月18、19日、定期総会を開き、「原爆や空襲被害者にいまだ償いが行われておらず、国の受忍政策を変えさせる」と決議した(時事通信の報道)。
研究者の直野章子氏が批判を続けている。『長崎平和研究』22号(発行:2006年、長崎平和研究所)の「戦争被害受忍論と被爆者運動」(九州大・直野章子)に「受忍論の言う国の非常事態に国民は命も含めて犠牲を強いられても我慢しなさいというのは、国民は国家のために命を捧げるのは当然であるということになり、ここには国民主権でなく、国家主権といえるようなロジックが生きていると言えると思います」
『広島平和研究所ブックレットVol 5』(発行:2018年)の第9章「戦争被害受忍論と戦後補償制度」(直野章子)に「受忍論の本質は、国家の行為によって引き起こされた被害を耐え忍ぶよう国家が命じる発話だという点にある。受忍論は国民が国家に対して責任追及することを許さず、被害を黙って受け入れさせ、戦争終了後に主権が回復して「非常事態」を脱した後も、非常事態の領域を創出しながら被害を「受忍」させ続ける効果を持つのである」
2025年6月29日、朝日新聞「戦後80年 救済こぼれ落ちる市民」の記事で直野章子氏(京都大学)は「受忍論は、法律論ではなく政治論だと私は考えています」「これ(受忍論)を放置したならば、私たちも受忍を強いられる当事者になるでしょう」と警鐘を鳴らす。
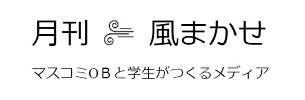
















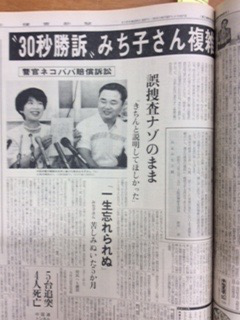

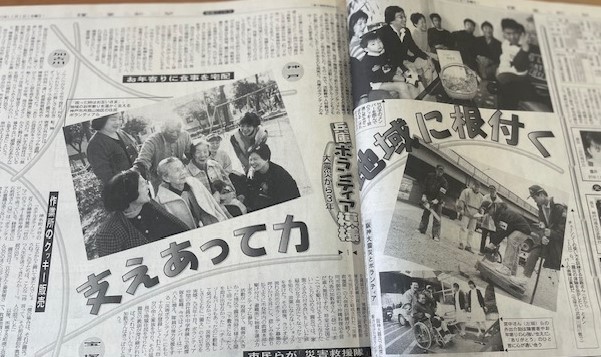
コメント