
『ハチドリ舎のつくりかた ソーシャルブックカフェのある街へ』(著者:ハチドリ舎店主 安彦恵里香)まえがきから。
「ハチドリ舎は広島の平和記念公園から徒歩3分の場所にあるカフェで、月に約30本、ほぼ毎晩、社会課題を取り扱ったイベントを開いています。ソーシャルブックカフェという言葉はわたしがつくった造語です。”ソーシャル“という言葉を使ったのは、お店をつくるときのコンセプトが「まじめなことを話しても引かれない場所がつくりたい」だったから。まじめなことというのは、社会で起きている様々な問題。政治、ジェンダー、差別、基地問題、日米安保、原発、核問題、紛争・戦争、医療・福祉…。そうしたソーシャルイッシューに対して、自分ができることを考えたり、動いたり、知識を得たり、対話をしたりすることでアップデートする必要があると思っているから。けれど、特に日本はそういったことを話しづらい雰囲気があって。社会課題について語ろうとすると「すごいね」とか「えらいね」「重い」と言われて、距離を取られてしまったりします。いちばん傷つくのは「めんどくさい」。そう言われて悲しい想いをしたことがあって…。でも「いやいや、それでもやっぱり話していかないと、社会はアップデートしていかないでしょう!」と思ったんです。もうこうなったら、まじめなことばっかりしゃべる場所をつくってしまおう!ここはそんなふうに逆張りでつくった場所です。なんならもう「まじめで何が悪い?」くらいの(笑)」

MoMoBooks(モモブックス)のホームページから
「2023年3月21日にオープンした新刊書店です。大阪・九条の下町長屋にあるお店で、分野を限定せず様々なジャンルを取り揃えた街の本屋です。ご来店されたお客さんや街の人たちと日々対話しながら、どなたにでも居心地の良い空間を目指しています。書店の棚は日々変わっていきます。街の書店は、僕たち営業している人間が作っていく部分と、ご来店されるお客さんたちそれぞれが作っていく部分とがあります。ぜひ九条の書店作りにご参加ください」
2月18日、トークイベント「新刊刊行記念 『ハチドリ舎のつくりかた』をMoMoBooksが聞く〜広島と大阪をつなぐ〜」がモモブックスで行われました。ハチドリ舎店主の安彦恵里香さんとモモブックス店主の松井良太さんが登壇、その模様を報告します。

松井
本日のイベントの主役、『ハチドリ舎のつくりかた』の著者であり、ハチドリ舎の店主である安彦さんです。大阪にはちょこちょこ来られることはあるんですか。
安彦
用事があったら、そんな遠くないんでね。ハチドリ舎に関西方面や大阪から来る人って結構いてくださってて、私以外みんな、大阪みたいな時もあります。
松井
不思議とうちも、広島の方が多いんですよ。いろいろ聞きたいことが山ほどあって、今回、イベントができてすごく良かったです。
〈ハチドリ舎ができるまで〉
安彦
2009年に5年間勤めたピースボートを退職しました。この時30歳でした。それから、ハチドリ舎を開く2016年7月までは、3ヶ月とか半年とか仕事をして、その次の1ヶ月は次の仕事を見つけるという、無職の間に仕事がある感じでした。ピースボートもそうですけど、それまで不動産屋さんとかでも働いていたんですけど、雇う雇われるとか、上司部下というヒエラルキーの中で、自分の責任が取れない、自分がやったことのフィードバックを直接受けれない組織形態が嫌だったんです。そこから逃れたいなあという気持ちがあったので、どこかに就職するという生き方を選択しなかったんです。
茨城県出身ですけれど、広島にすごくたくさんの友達がいて、2009年にピースボート退職後、海外に放浪の旅に出て、2010年に茨城ではなく広島に帰りました。この年は核拡散防止条約(NPT)再検討会議の年で、反核のキャンペーンの事務局長を時給800円でしたり、2011年、2012年も雇われ仕事を短期でするという生き方をしていて、すごく心地よかったんです。けれども、2016年7月に参院選挙である候補者の選挙を手伝った後から仕事が入ってこなくなったんです。
〈2016年参院選:自民、公明の与党が大勝。改憲勢力が3分の2以上を獲得。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた初めての国政選挙〉
8月から12月までの4ヶ月は、実家に行ったり広島に行ったりしながら、お金もそんなにない中、どうしようかなあって思っている時、私38歳でした。ピースボートで5年勤めてイベントもできる、社会的視点もある、フリーで仕事も受けて取り仕切ることもできる、そんな人を雇いたくないだろうなあと思ったんですよ。いよいよ自分でやるしかないかと思って、本当は自分でやるのは嫌だったんですけど、もうしょうがないと思って、おずおずしながらですね、2016年12月29日の誕生日にFacebookに投稿するわけです。
〈わたし、前々から気兼ねなく“社会ごと“を話せる場所を広島でつくりたいと思っていて。おしゃべりやイベントが中心で、お酒もお菓子も珈琲も全部オーガニックなブックカフェをやろうと物件探しはじめてます。
県外や海外から来た人が「あそこに行けば情報は得られるし、硬派なトークもできるよ」って場所。「平和って何?」を探してる人が集う場所。本もそーゆー本ばっかり。ピックアップ時事ネタとかがミニ黒板に書いてあるみたいな(笑)。
平和公園を中心に市電の線路が囲んでいる内側のエリアで、30人規模くらいの空き物件や大家さんをご存知の方がいましたら教えてくださーい!!
他にも何かいい情報があれば、誕生日プレゼントにください♪(笑)〉
膝を突き合わせるようなすごく近い距離で、被爆者の方のお話が聞ける場所が必要だと思っていました。この投稿、どうかなあと思いながら書きましたが、503件の「いいね」をもらって、コメントも141件もらって、これはいけるかなあと思ったんですね。
年が明けて2017年1月半ば、近くのワインバーに飲みに行った時に、お店の人に「うちの物件の不動産屋さんに新年の挨拶に行くけど、一緒に行く?」と言われて、この不動産屋さんは茶柱不動産というなんともいい名前なんです。「行きます!行きます!」と言ってついて行って、「物件ありますか?」と聞くと「ないですね」と言われたんですよ。しょうがないと思って帰ろうとしたら、後ろから「どんなにボロボロでもいいですか?」と。そこは元雀荘。後にそこがハチドリ舎になるんです。
〈2017年1月に物件が決まり、カフェつくりが始まる〉
安彦
この時、手元に20万円しかなかったんですよ。日本政策金融公庫に借り入れをしよう、公庫の担当者さんのアドバイスもあって、親にお金を借りて、借り入れの申し込みができたんです。クラウドファティングも始めました。直接寄付をしてくれた友達もいました。7月オープンを目指して、5月から内装工事を開始しました。日本政策金融公庫に借り入れをするため事業計画書を作ったのが5月でした。
松井
7月にオープンしようとしたのはどうしてですか。
安彦
8月6日、広島では「ハチロク」と言うんですが、ハチロクに合わせたかったんです。
松井
ハチドリ舎ができるまでの流れは、この本にいろいろ書いてあるんですけど、準備をどんどんやっていくと、これやらなあかん、あれやらなあかん、問題もいろいろ出て来ませんか。
安彦
バタバタだったけれども、無理した感じはなくて、全部スムーズでしたね。問題をクリアするのが、めちゃくちゃ好きなんです。それが面白いんですよ。
松井
これをどうしよう、これをどうしようとなりませんか。
安彦
これが必要だなあと思ったら誰に聞けばいいか、お金がかかるんだったらどうしたら安くなるか、そういうのを考えるのが、めちゃくちゃ好きなんですよ。楽しんでやってました。
松井
僕、事業計画書作りは大嫌いで、スムーズにいきましたか。
安彦
なぜ、スムーズだったかというと、創業サポートセンターというところがあって、無料で相談に乗ってもらえるんです。この相談に乗る人は登録されている人で、高めの自給をもらってね。最初に紹介された人が、俺すげえぜみたいな、なんでも聞けよみたいなおじさんだったんですけど、そういう人嫌いなんで、「チェンジ、お願います」と言って、担当者が変わりました。その人に「横でしゃべるから、それを事業計画書にして下さい」と。いわば‘聞き取り事業計画書作り’です。
松井
すげぇなあ。
安彦
その人もお金をもらえるわけだから、相談に乗るほど、その人にお金が入ってくる、それで、事業計画書が出来ました。
〈2017年7月、ハチドリ舎オープン〉
安彦
真面目なことを話しても引かれない場所が作りたい、社会と人、人と人をつなぐブックカフェを作りたい、それをどうやって達成しているかと言うと、半端ない数のイベントです。とにかく月に30本ほどの社会課題解決のイベントをやっています。これまでに2500以上やってるんじゃないかなあ。
松井
8月6日までにオープンすると最初から決めていたんですよね。
安彦
決めてましたね。ハチドリ舎を作る前から、8月6日は何かしらのイベントをやっていたんで、そのイベントの会場としてハチドリ舎を使えるようにしたいというイメージがありました。
松井
ハチドリ舎では、6のつく日にずっとイベントをやっていますね。
安彦
広島原爆忌の8月6日にちなんで、6日と16日と26日にイベントをしています。6日だけの1回だと少ないなと思ったんで。被爆者の方にハチドリ舎に来てもらって、「6のつく日 語り部さんとお話しよう!」というイベントをやっています。ハチドリ舎に来た人は被爆者の方と同じテーブルを囲んで双方向でやり取りをします。そうすることで、この人の頭の上で原子爆弾が炸裂したんだというリアリティー、原爆投下の歴史の中に自分もいるんだという感覚が生まれる、そう思っています。
私、ピースボートのスタッフでした。被爆者の方100人が乗ったクルーズがあったんですけど、船の中で日刊の新聞をつくる仕事があって、私はその担当で忙しくて、被爆者の方たちとコミュニケーションを密にとれなかったんです。でも、船内に居酒屋さんがあって、そこでお酒を飲んでいたら、被爆者のおじいさんと友達みたいになりました。被爆証言を聞く前に、つながりが生まれて、それからお話を聞くと、友達に原爆が落とされたんだ、そういう気持ちになって、許せないし、原爆をなくしたい、とういう感覚がすごく身近になったんですね。6のつく日のイベントで、そういう追体験をしてほしいなあと思うので、ハチドリ舎に来た人には最初に「ぜひ、被爆者の方と友達になってください」と言うんです。
松井
この本の中に「場の空気のつくり方」の話がありますけど、「友達になって下さい」と言う上で、意識していることとか、どんなことをしていますか。
安彦
なりたい人はなるし、ちょっとという人はならない、その自由度も結構大事だなあと思っていて、あなたが選んでくださいという、自立独立みたいな感触もすごく大事で。
松井
それぞれが独立して自由にやってくださいと。
安彦
ただ、口火を切れない人もいるから、ちょっとだけ、その人の関心があることを聞いておいて、同じような関心を持っている人とつなぐ、そういうことはやりますよね。
松井
その人の個人の話を無理やり別の人につなげるのもよくないなあと思いながら、どこまでやろうかなみたいなところがあります。
安彦
うちはカフェなので、わざわざ話しかけに行ったりとかしないんです。自分が話しかけたとか、動いたという体験がすごく大事だなあと思います。自分がつかんだという経験をしてほしいという気持ちがあります。
「被爆体験を継承した方がいいと思うんです」という子が時々来るんですけど、「なんで?」と聞くんですよ。「それがいいと思うからです」「なんでいいと思うの?」となって、それで、その子は「えっ」となるんです。自分の中に、本当にちゃんと理由を持っているのかという確認をするようにしています。これが正解で、それをインストールしなくちゃいけないみたいな雰囲気を感じ取ったら、「本当にいいの?それが正解だと思ってるの?」と、グラグラ揺らぎみたいなことをしたくなっちゃう。私は正解で、私は正解の人だからここに来て、きっと褒められると思っている人は全然褒めないですね。
松井
そういう人が来たらそういう揺らぎをもたらす。
安彦
ハチドリ舎に来た理由が何かを聞いて、面白がっているというか、自分のやっていることがすごく楽しいと思っていたら、「よかったね」となって、「それだったらね、これがあってね」「この人に聞きに行ったらいいよ」「ああしたらいいよ」と話をするんだけど、そうじゃない場合は「なんで?なんで?」って聞いているんです。
松井
安彦さんなりの場の空気作りというか…
安彦
独立しているかい?みたいな。
松井
なかなかすごいなあ。面白いですね。イベントの話ですけど、出演者が話す形もあれば、みんなでしゃべる形もあるし、いろんなイベントがあると思うんですけども。
安彦
月例企画が半分ぐらいです。「6のつく日 語り部さんとお話ししよう」も月例だし、「弁護士バー」とか、「セクシャルマイノリティバー」とか。他にも「カウンセラーカフェ」「マインドフルネスカフェ」「ソーシャル語りバー」「ソーシャル英会話」もやっています。「みんなでつくる中国山地コラボ企画」も。月例企画は同じ人たちとずっとやっているから、内容や日付を決めて、告知はこちらでやればいいという。
松井
最初の頃は、何もない状態からスタートするわけですけど、どうやって立ち上げていったんですか。
安彦
スタートした頃の2017年8月は17本ぐらいでした。例えば、一人の女性がハチドリ舎に来て、「ちょっと食に気をつけたいなあという気持ちはあるけど、ストイックな感じはちょっと無理で、どこまで気をつけようかみたいな情報を共有する人がいなくて」と言って来たことがあったんですよ。私が「なるほどね」と言って。
松井
お店に来た時にそんな会話もするんですか。
安彦
「こんにちは」から始まって、ハチドリ舎自体がソーシャルな感じという、ちょっと面白い、変なところという感じですから、「どうして来たんですか?」と聞くと、何かポロッと出てくることがあるんです。それで、企画なりそうだなあ、これ企画にした方がいいなあと思ったら、この女性の場合でいうと、「ちょっと食が気になる人たちのお茶会みたいなことをやりませんか」と声をかけて、「いいですね」となりました。「こちらが企画するから、あなたはそこにいればいいだけで、何の大変さもありません。あなたがそう困っているとしたら、五、六人は困っていると思います。やってみて。私も聞いてみたい」。自分の興味が重要です。
松井
その人から聞いたことに安彦さんが興味を持って、じゃあイベントをやりましょう、形はこっちでつくるからと企画が生まれる。
安彦
そうそう。でも、やってみたら、ネットワークビジネスの人が来たり、食を気にする人たちの気にする度合いに差があり過ぎて、やめました。
松井
食についてそういう話をできる横の繋がりがないから、その人が困っていて、だけどうまくいかなかったのは、その人がもうちょっとハンドリングしてくれたらうまくいったかなあと思うんだけども。1回だけで終わるイベントもありながら、1回やって続けられるなあというイベントが続いていて、毎月喋ることがあるって、すごくいいですね。
安彦
月例イベントを一緒にやる人は仲間みたいな感じです。このお茶会の場合も、仲間になるかもしれなかったんです。自分が困ったことは自分で解決できるんだみたいな感覚を養える、ということを知ってほしいなあと思って、「やってみたら」と背中を押すようなことをちょこちょこやるんですよ。それで乗っていく場合と、どうかなあとなる場合もあるけど、私は、これが成功でこれが失敗と思わなくて。
松井
集客が多ければいいとかではなくて、中身がやっぱり重要だと。
安彦
本当にこれに困っているとか、本当にこれが嫌だとか、全部、オェ~と吐き出せるかが大切。
松井
このイベントが始まる前に、男性同士の会話が下手という話をしてたじゃないですか。男性同士でケアし合えることがなかなかできない。
安彦
2つ前のイベントが終わってからの飲み会での話です。女性は男性の話を聞いてあげるというケアを自然としている、そういう社会の構造の中で生まれてきてしまっているので、ジェンダー、フェミニズムとかをいろいろ調べると、男性同士はどっちが上か下かというマインドにとらわれてしまうような、評価されまくって育ってきていて、それはしょうがないですよね。強くなれ、偉くなれ、みたいな世界で育って来て、マウントし合ってしまうから、弱さみたいなものをさらけ出しづらい。だから「実は悩んでて…」と言ったら、「お前、弱いなあ」「駄目だなあ」とか言われるのが嫌だから、言わないみたいになっちゃっている。だけど、男性同士も「しんどいね」「こうしようかな」「ああしようかな」みたいな話ができた方がいいと思うんだけれども、男性だけの対話の場が、なぜないんだろうかと思っていて、そういう場を作りませんか。
松井
同じことを思ってて、ハチドリ舎さんがやっているアルテイシアさんのジェンダー喋り場というイベントがありますけど、みんながモヤモヤをいろいろ喋る、あれってすごくいい空気でね。やっぱり、どうしても男性が少ないというか、そこに来てほしいと思う人になかなか届かないなあと思ってて。
安彦
ジェンダー喋り場が盛り上がるのは、女性たちが「わかるわあ」となるからだと思う。女性であるということで、いろいろ使われたりとか、いろんな痛みがあって、「こういうことがあったんだよ」となったら、「いやー、わかる、わかる」「あるある」みたいなので、癒されるのですよ。だから女性が多くなるのは、それでまずは癒される必要があるんです。女性には、自分が悪いって思わない、思わないでいいんだよ、という世界がいったん必要だと思う。それの男性バージョンがあったらいいのに。
松井
そうなると、男性限定でやらんとあかんような気がするんですよ。
安彦
そうね。
松井
弱みを見せられない男性もいっぱいいるやろうし、かっこつける男性もいっぱいいるやろうし、そういうのもあるなあと思って。
安彦
男性に、一つ一つ迫って行きたいですね、今の言葉はどんな思いから言ったんですか?と。
松井
迫ってきますね。
安彦
無思考に言葉にしてしまうことが多いから、それはどういう言葉なのか聞きたい。
松井
どういう流れでこういう発言になったのか、紐解いていくと。
安彦
反射的な言葉だったと自覚するのは大事な気がしています。
松井
安彦さん、今後こういうのをやっていくとか、ありますか。
安彦
優秀じゃなきゃいけないみたいな概念の世界はもうやめようよというか。いいことをやって褒められる、悪いことをやったら罰を与えられる、ということで評価ばかりを気にして、自分が何をしたいのか、どうありたいのか、ということにフォーカスできないような構造だなあと思っています。この人は駄目だ、この人はいい、というふうにしているから、それが自分の肩にも乗っかかって、ずっと自分を責め続けるみたいな。しんどいと思っているから、そのしんどさから抜けて、どうしたら自分の人生が面白くなるか、充実、みなぎる、楽しいみたいな。
松井
自分でやりたいと思って、主体性を持って。大事ですよね。
安彦
自分はこの思想があって、これがめちゃくちゃ楽しいとか、面白いとか、これをやっていきたいというものがあれば、いちいち人のことをあれこれ言わないと思います。みんなが、そうなったらいいのにと思うんですけど。
松井
この本に、安彦さんが20代前半の頃、ピースボートに乗って、船内で様々な催しものがある中、どこに行ったらいいかわからない、何をしたらいいかわからない、と書いてありますが、主体性のことで言えば、似ているかなあ。
安彦
そうですね。どの企画に参加していいのかわからなかった、何に興味があるのかもわからなかった、それ以前に自分で自分のことが決められなかったです。それと、好きにしちゃいけない、わがまま言うなとか、楽しいことだけするなとか、茨の道に進めみたいな感じの世界が広がっているじゃないですか。それにやられるから、自分の選択が正しいかどうかわからないみたいな世界に生きていたけれど、ピースボートとその後自分で生きてきた中で、誰の何にどう答えたら自分は認められるんだろうという世界から、解放されたんです。
松井
ピースボートではどういう選び方をしていきましたか。
安彦
小倉祇園太鼓を教えてくれる人たちがいたんですよ。部落出身で、初めて部落差別を身近に感じられました。生まれ育った茨城県では出会うことはなかったんです。在日コリアンの人も乗っていたし、耳の聞こえない女の子も乗っていたし、いろんな人たちとの出会いだったりとか、あと太鼓を習うとか、やりたかったダンスを選んだり、楽しくて。
松井
やりたいことをやっているつもりではあるけど、できていない人の方が多い?やっていると思っている人は多いような気がするけど、どうなんやろ。
安彦
誰かに評価されたくてやってない?と問えるのは、自分がそうだったから。
松井
誰かに評価されるためにやることと、本当にやりたいこととは違うんですよね。
安彦
鼻がふくらんじゃうみたいな感じ、ちゃんと興奮してるみたいな感じ。
松井
うちのことで言うと、イベントをよくやっている本屋だと周りに思われているんです。本屋はイベントをやらなあかんと思ってなくて、イベントをやるのが好きで、著者に会いたいし、自分がやりたいからやっているんですけど、その店主がやりたいことがお店のカラーになっていたりするじゃないですか。やりたいことを自分で見つける、選ぶ、というのは、その力は必要ですよね。
安彦
知的探究心なんですよ。自分は全部調べられないから、専門家だったり、調べたりとか、書いているとか、研究しているとか、そういう人に聞く。知りたいということなんですよね。知りたいと思う人の方が多いと私は思っているんです。みんなが知れ!とは思っていなくて、知りたいと思っている、その人が面白がっているかどうか、そこがすごく大切だなあと思う。
最近、思い出したことがあるんです。ある人に「本当だったら公民館がやるべきことをハチドリ舎がやっていて、今の公民館はできてないのではないか思う。安彦さん、話してみたらいいんじゃないか」と言われて、公民館職員の人たちに講演したことがあるんです。その時、公民館の成り立ちは調べたんですよ。知ってますか。私、それで何と!と思ったんですけど、公民館はどうしてできたか知っていますか。
松井
いや知らないですね。
安彦
日本国憲法を全国に知らしめるためとか、民主主義を人々の暮らしにちゃんと根づかせるために作られたのが公民館なんですよ。
会場一同
へぇ!!!
安彦
民主主義をちゃんと手に入れようというのが公民館の役割なのに、それに反する問題が起こったり、なんということかですよね。
〈2014年、さいたま市の女性が詠んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という俳句が政治的だとして市の公民館が月報への掲載を拒否する事件が起きた。裁判に発展し、市の違法性を認める判決が最高裁で確定した〉
安彦
本来の公民館を取り戻すのが、この本の役割かな。
松井
公民館職員に是非、読んでほしいですね。
安彦
そうですね。

松井
今、ハチドリ舎のような場所をつくりたい、どうすればいいか、聞きたい人は多いと思いますが、相談に来る人はいますか。
安彦
お店に来て、「やりたいんです」と相談に来る人はいますよ。
松井
何と言うのですか。
安彦
「やりなよ」「やったらいいよ」と言っています。「物件を借りるのは無理なんです」と言う人もいます。そういう場合は、「自分のフィールドにあるカフェで、3人集まって社会事の話をするだけでイベントだよ。それを月に1回続けたらいいよ」と答えています。早稲田大学の女の子が来て、「ジェンダーの話がしたいけど、できなくて。学内のカフェはあるけど、人をたくさん集められそうにない」と相談を受けたことがあります。「誰か一緒にやろうと思ってる人はいるの?」と聞くと、「1、2人います」と。インスタのアカウントをつくるとか、学内の掲示板に案内を貼るとかアドバイスして、「やっちゃいなよ!」と言ったら、その後、「やりました」と連絡がありました。
松井
一つの成功体験が大事ですよね。
安彦
ハードルを上げ過ぎなんですよ。何十人も人を集めなくちゃいけないと思い過ぎ。身内数人で始めて続ける。続けていたら、何かやっているらしいと広がって、行ってみたいなあという人が出て来ます。
松井
続けていたら集まってきますしね。続けていくことが告知にもなるし。全国にできたらという話をしていたじゃないですか。
安彦
ハチドリ舎のチェーン展開みたいなのは全然嫌なんです。面白がって、独立して、自分がこの社会をより良くしていく当事者の1人である、自分も迷っているし悩んでいるけれども一緒にやりませんか、そういう人が立つ。たくさんの人が立っていく必要があるなあと思っています。
松井
今、安彦さんが一番興味あるテーマは何ですか。
安彦
基本的にイベントは私が今知りたいことをやっています。正月に実家に帰った時に、兄と兄の息子に言われたんですよ。「中国に侵略されたらどうするんだ。もっと武力を持った方がいい」と。ここまで近くなってきたか、と思いました。
松井
そうですね。
安彦
これに対して、どんな言葉をつむげるか、今すごく興味があるんです。誰に聞くのがいいかと思っていて、沖縄の有識者で中国と沖縄の問題を語ってくれるとか、武力がどれだけ意味がないかをわかりやすく話してくれるとか、そういう感じで企画を作っていきます。
去年12月に父が26時間、行方不明になりました。昼過ぎに会社でお客さんの対応している時に、いなくなっちゃって、次の日の夕方まで見つからなかったんです。すごく怖かったんです。血管性認知症で、日常生活は送れるんだけど、短期記憶ができないという状態です。仕事はほとんどできない状態だけれども、母が会社に連れていって、ずっとソファーでゆっくりしているか、猫を触っているか、草をむしっているか、という感じらしいんです。認知症の企画をこれからします。
松井
日々、これはどうしたらいいんやろか、ということがあって、そこから企画が生まれる、テーマは尽きそうにないですね。
安彦
尽きないですね。
松井
時代によって自分のテーマがどんどん変わるくるやろし。
安彦
ネットを信じる人たちが増えているのはなぜなのかとか。ネットポピュリズムみたいなことを研究する人はいないのか調べたりしています。なんで、みんな、立花孝志とか斎藤元彦が言っていることを信じているのか、わかんないんだけど、信じるロジックが何かあるのだろうみたいな、どんなことが起きているのか、知りたい。
松井
万博も始まるんで。
安彦
万博やりますよ。何がどう良くて、どこがどうマイナスなのか、あんまりわかってないなあと思っていて、みんなね。大阪府民は興味ないというか、勝手にやっているみたいな感じで、そうやって捨て置かれているけれども、もう一回ちゃんと話してもらいたいなあと思っています。
本当なんか、まがまがしいですよね。まがまがしいものって、もういいやと思って、触らないようにしちゃうじゃないですか。そうやって放置されて、進んでしまう。これに対して、どうやってくさびを打つか、すごく考えなきゃいけないなあと思っています。
松井
終わっちゃったら、よかったなあみたいな感じの空気になる可能性も全然あるんですけどね。
安彦
ことなかれと無思考の中、どうしたらいいのかみたいなものは、迫り続けていきたいと思います。
松井
うちと意識は一緒やと思う、それこそ広島と大阪をつなげてね。
安彦
コラボ企画ね。
松井
何かできたら。
安彦
やりましょう。
●『ハチドリ舎のつくりかた』 のサイト
〇モモブックスのサイト
●編集担当:文箭祥人
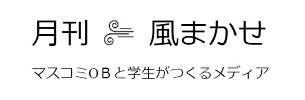







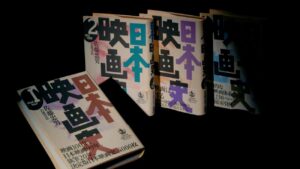

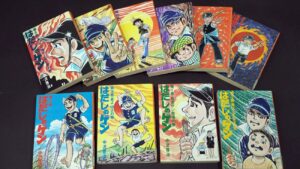









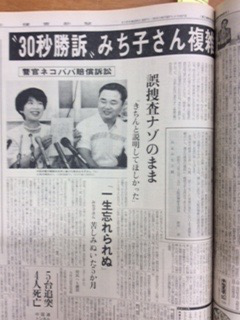

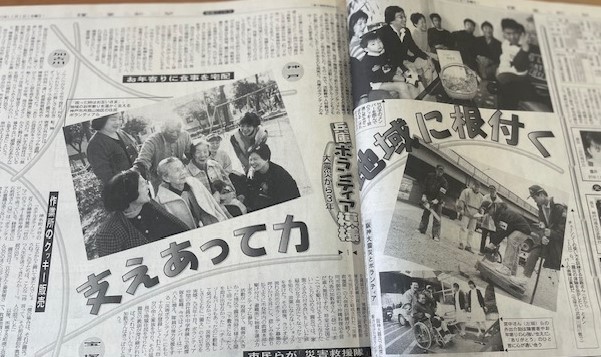
コメント