十三シアターセブンでの「ナナイロ活弁」シリーズをはじめとして、活動写真弁士・大森くみこさんの「活弁・生演奏付きサイレント(無声)映画上映会」が、関西各地で開かれています(冒頭の写真はトリイホールでの公演)。邦洋問わず様々なジャンルの活弁公演は、まず例外無くどれもいつも面白い。愉しめる。私がここ一年くらいの間に彼女の活弁付で観たサイレント映画は、『不壊の白玉(1929年)』『ロイドの要心無用(1923年)』『何が彼女をさうさせたか(1930年)』『大人の見る繪本 生まれてはみたけれど(1932年)』『肉体と悪魔(1926年)』『拳闘屋キートン(1926年)』『恋の花咲く 伊豆の踊子(1933年)』『ファウスト(1926年)』といった作品ですが、その巧みな状況説明、繊細な心理描写、スクリーンからセリフが聞こえるかのような「声色」に引き込まれ、名匠・清水宏や小津安二郎の世界を堪能し、喜劇王のアクションに爆笑し、昭和初期のダークサイドを体感し、若きグレタ・ガルボや田中絹代に心躍らせ、ドイツの名匠F.W.ムルナウの驚異的な映像造形に圧倒され、いずれも忘れ難い映画体験となりました。

トーキー以前のサイレント映画時代=日本における活弁時代(明治末から大正・昭和初期)は、そもそも「絵が動く」という驚愕の見世物体験から始まり、笑いや涙やアクション満載の「活動写真」が娯楽の花形になり、やがて洗練された「映像芸術」としての名作も数多く生まれ、映画史的にも最初の黄金時代だと言えますが、今DVDや映画館などでの上映時にはフィルムに音楽を付けた「サウンド版」で観ることが多く、まさに往時の上映スタイルを踏襲した活弁付上映の盛況は、少なくとも関西においては大森くみこ弁士の登場~活躍と軌を一にしているというべきでしょう。その話芸が、現代の観客にとって音声のない映画の面白さのランクを数段引き上げたといっても言い過ぎではないと思います。戦前のサイレント映画の破格の面白さを体験してみたいという方はぜひ一度、大森さんの活弁公演を観て聴いていただくことをお勧めしたいです。もしかすると、ご自分のなかの映画史が書き換えられるかもしれません。

大森さんにいくつか質問をしてみました。
ーなぜ活動写真弁士になろうと?
「自分が活弁に引き付けられたのは、もちろんサイレント映画そのものの魅力が決定的で、当時の映画が想像を超える面白だったことですね。映画の草創期には、制作者たちがまったく新しい文明・文化に心弾ませながら試行錯誤する様子がよくわかります。楽しく、美しく、想像力豊かな作品ばかりで、今見てもとても斬新。トーキー直前のサイレント映画円熟期ともなるとその進化はすごいです。あらゆる映像手法が確立され、潤沢な予算による豪華キャスト、細部まで素晴らしい美術セット、映画制作に懸ける熱量と作品の完成度は素晴らしい。100年前にここまでの事が出来たのかと驚愕します。」
「活動弁士は一人で何役もの語りを担当します。司会からナレーター、実況者、ストーリーの前後説明、時に声色を使って役者になり、時にはそのツッコミまで、およそあらゆるお喋りの要素がすべて詰まっているので、これまで様々なお喋りの仕事をしてきた私にとってはすごく楽しく、やりがいのある世界ですね。」
ーでは、その活弁という芸能あるいは職業はなぜ日本でのみ発展したのでしょうか?
「いくつか要因はあると思いますが、一番は映像に語りがつくことに違和感がなかったのでは。西洋にはなかった語りの文化の伝統が大きいと思います。日本には浄瑠璃、講談、落語、浪曲などの語る芸能が根付いていたので活動写真に語りがつくことが広く受け入れられたのでは。」
活動写真弁士は、映画説明者あるいは解説者ともよばれ、全盛期には映画館専属の弁士たちが、多種多様の個性豊かな語り(説明)で観客に喜ばれていたようで、七五調の美文を歌うように饒舌に語る弁士もいれば、映写中の所々で一言二言、気の利いた名文句を発して笑いを取るタイプもあったとか。たしかに「語り芸」はこの国の観客に馴染みやすかったといえるのでしょう。
さて、サイレント映画に絶対不可欠なのが伴奏音楽です。活弁付あるいは伴奏のみでの上映会でも大活躍のピアニスト天宮遥さんにも質問を。
ー今も昔もサイレント映画上映に無くてはならない伴奏音楽を担当するにあたって、大切なこと、難しいこととは?
「伴奏も弁士の方と同じく、映画のストーリーを理解して、客観的な状況と主人公の気持ちどちらも音楽にするようにしています。伴奏音楽は観客が気付かないうちにその感情に大きく影響していて、場面に合わない音楽を演奏すると作品全体を台無しにしてしまう可能性があるので、シーンの流れや細部の描写まで覚えるようにしています。映画の場面転換やカット割り、弁士の語りとの密接な相関関係、あるいは観客の方の反応などにも即対応すべく常に即興で演奏していて、想像力、反射神経、演奏テクニックなどすべてを同時に求められるので、その辺が難しくもあり、とてもやりがいのあるところでしょうか。会場によっては、手元が暗くて鍵盤やメモが見えにくかったりすることもありますが、先人が残した映像遺産に敬意を払い、すべての作品を楽しんでいただくためベストを尽くすようにしています。」
なるほど「伴奏音楽」という言葉からして、控え目な存在に聞こえますが、音楽家が聴衆を前にして演奏をするときは、どんな環境であれ常にそれは「自己表現」そのもので、自分が伴奏をする上映会のさいには、映画とともにピアニスト天宮遥のオリジナル演奏会のごとく、そのテクニックと情感をお楽しみいただきたいというお話のようにも、私は感じました。
活動写真弁士も伴奏者も紛うことなき表現者であって、100年前の映像作家と現代の弁士と演奏者の共演であるという、その明快な真実が、今日のサイレント映画の楽しみ方、読み解き方の基本でしょう。
お二人の話からは、各地で開催されている「サイレント映画の活弁・生演奏付き上映」という機会が、20世紀初頭映画草創期の名画を鑑賞し、弁士の縦横無尽の語りに酔い、高度で繊細なピアノ演奏に心奪われる、そういう特別に贅沢な時間であるということをあらためて感じていただけたのではないかと思います。
では最後に「活弁・生演奏付きサイレント映画上映」というエンターテイメントは、これからどこへ向かうのか?向かうべきなのか?
映画草創期の日本で隆盛を極めた「活弁」という芸能は、大正から昭和初期の決して長くはない年月、多くの才能が個性を競い、絶えず進化し変容しつつ庶民の絶大な人気を集め、とは言えひとつの伝統芸能として完成されることはなく、様々な可能性を孕んだままトーキーの登場で終焉を迎えます。しかしその芸能はトーキー以前の映画群を最高に輝かせた、世界にも類のないエンターテイメントでした。そして、その映画作品たちは100年を超えて映画史の中に確実に生きていて、むしろ益々輝きを増しています。その作品たちをひとつでも多く発掘し公開し、その素晴らしさのままにさらに映画史に刻み込むことを「活弁・生演奏付きサイレント映画上映」に期待したいと切に願います。作品の作られた時代背景や監督・俳優についての情報、物語に反映される価値観の違いなど、当時以上に映画説明あるいは解説の必要性は増しているとすらいえるでしょう。
「活弁」が完成されることのなかった芸能であるからこそ、数多の可能性を孕んだままであるからこそ、その進化と変容は実は一世紀を超えて今も続いていて、世界の映画史とともに未来へと開かれたエンターテイメントであり続けていくのではないでしょうか。
〇総合デザイナー協会特別顧問 園崎明夫
●「活動写真弁士 大森くみこ」ホームページ

○天宮遥 公式サイト
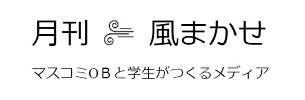









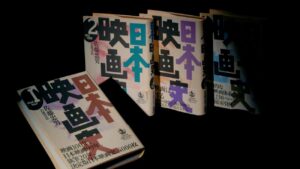

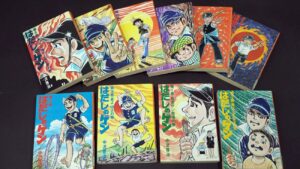







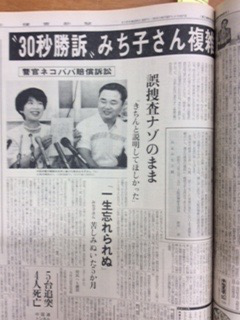

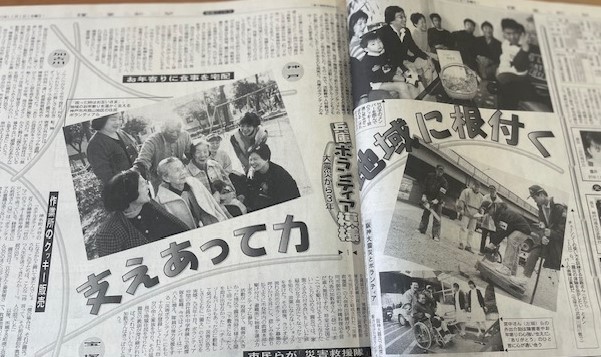
コメント