ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロのデビュー作『遠い山なみの光』が、石川慶監督によって見事に映画化されました。太平洋戦争終戦から間もない1950年代の長崎と1980年代のイギリスが舞台で「時代と場所を超えて交錯する”記憶”の秘密を紐解いていくヒューマンミステリー(公式サイトより)」。原爆投下そして終戦から80年の今年、被爆地長崎で戦後を生きた人々の人生とその内面を、映画ならではの傑出した表現で、とても緻密に感動的に描いた作品だと思います。
石川慶監督は2022年公開の映画『ある男』(原作・平野啓一郎)が素晴らしい傑作でしたが、今回の作品もとても味わい深い原作の構成を読み込んで、さらに映画でしか出来ない、映画でこそ可能な表現で映像化されています。作品の基本ラインは、悦子がイギリスへ渡ってから誕生した次女・ニキに求められて、悦子自身の長崎での戦後の体験、喜びや幸福、願いや夢を、佐知子という女性とその幼い娘との記憶を中心に語るというもの。そして、その「記憶」の在り方そのものがこの上なく重要な、作品の「核」になります。

悦子役・広瀬すずはおそらく彼女のキャリア最高の演技、最高の作品になったと思いますが、彼女と佐知子が絡むすべてのシーン、すべてのカットが美しくもどこか不吉で、多義的で複層的な魅力に溢れています。もちろん佐知子を演じる二階堂ふみもいうまでもなく素晴らしい。
オープニングシーンはまどろみから覚めた(イギリスの)悦子のカットですし、悦子と佐知子とのシーンは、夕暮れや夜明けの薄明の時間が多く、それは悦子の記憶のなかの光景のようでもあり、夜の夢のようでもあり、彼女の孤独な幻想のようでもあります。そして、もちろん美しい。

映画『遠い山なみの光』という作品は、たとえば実在の誰かの人生をひとつのシンプルなストーリーとして語りつくすことが到底無理なように、主人公・悦子の人生もその幸せや夢や願いや後悔や嘘や誰にも言えない秘密や、そういったすべてを抱きしめて過ごしてきた掛け替えのない時間だということを、映画にしかできない表現を駆使して描き上げた傑作だと言えるのではないでしょうか。

そして戦争やさらに核兵器というものが人間にどれほど深い傷を残し、その一生に重大な意味を持つのか。そのことが物語の根底にあると強く感じます。悦子の義父で元教師・緒方をめぐる物語もとても重く、三浦友和の名演もあって深く心に残ります。ちなみに、この映画の広瀬すずを観ていて、あの原節子を想起する観客は多いのではないかと思います。悦子が緒方と過ごすシーンなど、小津安二郎の『東京物語』(映画の街頭のポスターは、その前年の『お茶漬けの味』です)や成瀬巳喜男の『山の音』が見事に重なります。このあたり日本映画の歴史への敬意も見どころです。
いずれにせよ本年屈指の日本映画には違いなく、すべてのシーン、すべてのカットをじっくりとお楽しみいただきたいです。
〇園崎明夫(総合デザイナー協会 特別顧問)
●「遠い山なみの光」9月5日公開
なお、冒頭の写真のコピーライツは©2025 A Pale View of Hills Film Partners
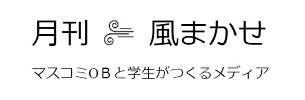









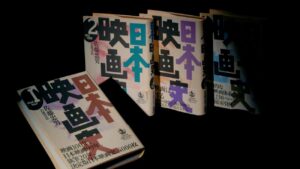

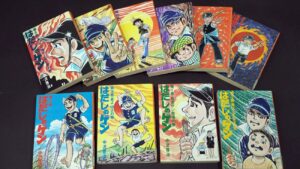







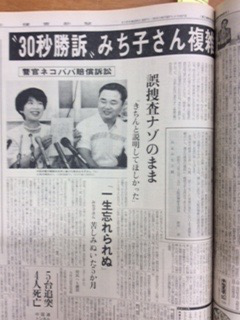

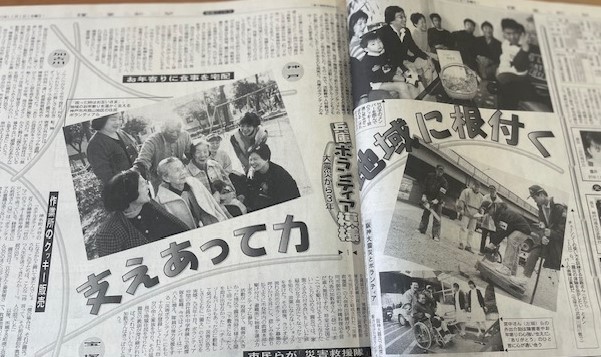
コメント