
ドキュメンタリー映画『黒川の女たち』
80年前の戦時下、国策のもと実施された満蒙開拓により、中国はるか満洲の地に渡った開拓団。日本の敗戦が色濃くなる中、突如としてソ連軍が満洲に侵攻した。守ってくれるはずの関東軍の姿もなく満蒙開拓団は過酷な状況に追い込まれ、集団自決を選択した開拓団もあれば、逃げ続けた末に息絶えた人も多かった。そんな中、岐阜県から渡った黒川開拓団の人々は生きて日本に帰るために、敵であるソ連軍に助けを求めた。しかしその見返りは、数えで18歳以上の女性たちによる接待だった。接待の意味すらわからないまま、女性たちは性の相手として差し出されたのだ。帰国後、女性たちを待っていたのは労いではなく、差別と偏見の目。節操のない誹謗中傷。同情から口を塞ぐ村の人々。込み上げる怒りと恐怖を抑え、身をひそめる女性たち。青春の時を過ごすはずだった行先は、多くの犠牲を出し今はどこにも存在しない国。身も心も傷を負った女性たちの声はかき消され、この事実は長年伏せられてきた。だが、黒川の女性たちは手を携えた。したこと、されたこと、みてきたこと。幾重にも重なる加害の事実と、犠牲の史実を封印させないために―。(『黒川の女たち』公式サイトから)

松原文枝監督:1991年、テレビ朝日に入社。「ニュースステーション」「報道ステーション」のディレクターとして、政治、選挙、憲法、エネルギー政策などを中心に報道。2012年にチーフプロデューサー。報道局経済部長を経て現在はビジネスプロデュース局ビジネス開発担当部長。『刻印 黒川開拓団の女性たち』(KADOKAWA)が2025年8月26日に刊行。
7月20日、神戸・元町映画での上映後、松原文枝監督の舞台挨拶が行われた。その模様を報告します。
松原監督
新聞・テレビが佐藤ハルエさんの取材を始めたのは、2017年ぐらいからです。NHK、地元新聞社、中日新聞岐阜が取り上げています。ハルエさんは事実を淡々と語られましたが、詳細に関しては、おそらく自分の中で一線を引かれていたんだと思います。体験を語ると自分自身が傷つきますから。例えば、ある晩にソ連兵に引っ張られて行って、何があったか、そういう詳細については、語りませんでした。

<佐藤ハルエさん 1925年生まれ。黒川開拓団として1943年に満州に渡る。「性接待」の犠牲に。戦後は故郷を追われて、岐阜県ひるがの開拓に。戦後70年余り経って、公の場で自らの体験を告白。多くの人たちに語り続け、記録として残すことを切望した。2024年1月、老衰のため死去。99歳だった>(映画パンフレットから)
松原監督
実は、ハルエさんは1980年代に、ものすごく細かく語っています。しかし、社会には届きませんでした。本来であれば、守られるべきハルエさんたちですが、彼女たちは蔑まれたり、貶められたり、あるいは、村の人たちはみんな知っているから村に居られなくなって、ハルエさんは岐阜県のひるがの開拓へ行きました。村から外に出ることで、新たな気持ちで人生を始めたと思います。そのことも、語ることへの抑圧をはねのけることにつながったと思います。とはいえ、何があったかを実名で伝えるには時代が許さなかった、許さないことがよくないですが。
ハルエさんはものすごく意思の強い方だと思います。実名で書いていいと言って、1983年に雑誌の取材に体験を話しました。雑誌は、黒川開拓団の中で誰が「性接待」の犠牲にあったのか憶測を呼ぶからということで、開拓団の名前もハルエさんの名前も仮名にしました。仮名になると何が起こるかと言うと、あまりにも生々しいから、記事のタイトルが「処女たちの凄春」(おとめたちのせいしゅん)となりました。ぱっと見ると、色物みたいなタイトルになってしまったんですね。黒川の村の人たちは、その雑誌を名古屋まで行って、買い占めて焼いたり埋めたりして、隠し続けた。「性接待」はずっとないことにされてきました。次に、1995年に岐阜新聞の記者がハルエさんを取材しました。ハルエさんはきちんと理解してくれる人には話をしています。ハルエさんはこの時も実名でいいと言ったんですが、結局、記事になりませんでした。
2013年に満蒙開拓平和記念館が開館しました。この場所ができて、本当によかったと思います。記念館の「語り部の会」にハルエさんたちが招かれ、ハルエさんや、もう一人、安江善子さんがこの事実を聴衆を前に語ったのです。彼女たちの証言に光が当てられました。「性接待」ということが起きていたんだ、戦争はこういう罪深いことが起きるんだということを残してくれました。
<満蒙開拓平和記念館 全国で唯一の満蒙開拓に特化した記念館。所在地は長野県下伊那郡阿智村駒場> https://www.manmoukinenkan.com/
松原監督
黒川開拓団でだけ、「性接待」があったのか。平井和子さんという女性史の研究者が国会図書館や証言集を調べて、44件あったと書いています。その証言が実名でなかったり、あるいは、当事者ではなくて目撃した人の証言や伝聞です。黒川開拓団の女性たちに私自身が突き動かされたのは、女性たちが、顔を出して、実名を出して、自分たちを当事者として語ったことです。そのことによって、「性接待」の史実を揺るぎないものにしました。為政者が歴史を変えようとすれば、歴史というのは変わってしまう可能性がある中で、女性たちが自分たちで自分たちに起きたことをきちんと語ってくれて、それを受け止めてくれた戦後世代がいた、そのことが本当に一つの希望だと思い、映画という形にしました。
佐藤ハルエさんは昨年1月に亡くなられました。ハルエさんは戦後、岐阜県のひるがの開拓に行きます。木を一本一本切って、根っこを掘り起こして開墾して、畑にして、本当に大変なことですけど、ハルエさんは「満州に比べたら、大したことにない」と言うんです。普段はすごく元気なおばあちゃんですが、昨年、体調を崩されて、1月に入院されて、体調がもっと悪くなってしまいました。それから、自宅に戻られましたが、野菜ジュース1本しか飲めないと聞いて、安江菊美さんと藤井宏之さんと3人でお見舞いに行きました。

<安江菊美さん 1934年生まれ。「性接待」に出る女性たちが入る風呂を焚いていた。小学校5年生だった。「性接待」の犠牲になった女性から「性接待」の事実を後世に話すように託された>

<藤井宏之さん 1952年生まれ。黒川開拓団遺族会会長。戦後生まれで、父親が黒川開拓団員だった。「性接待」について、ハルエさんら女性たちのもとを何度も訪れ、具体的に知る。父親が「性接待」の「呼び出し係」だったことや、誹謗中傷した当事者かもしれないと知る>
菊美さんは寝ているハルエさんの耳元で、満州時代の思い出話を話し出しました。それから十分後、ハルエさんは静かに息を引き取りました。ハルエさんはこの二人を待っていたんだと思います。二人を待って待って、安心して旅立たれたんだと思います。家族の看取りをすることがあっても、家族以外が亡くなる場所に立ち会うことはほぼないと思いますが、私自身がそこに立ち会ったわけです。そこにいた時、この人たちがやってきたことを、残さねばという気持ちに突き動かされました。
女性たちは、全然、圧もなく、上から「あなた、書きなさいよ」ということも全くありませんでした。ただ向き合って、真剣に話されるから、聞いている私も何かしなければと思いました。
「性接待」はメディアより先に研究者が知り、メディアが知ることになるのは、その後でした。会社が違っても記者たちは、女性たちがやったことをきちんと伝えなければならないと話し合いをしたわけではありませんが、みんながそう意識していて、共同作業のような形になりました。みんなで女性たちが成し遂げたことを残していこうという感じになったんです。女性たちがずっと声を上げてきて、その声をそのまま残すことができて、この映画を観られたみなさんもこの声を聞いていただいたので、この声を社会に届ける共同作業の一角になっていただきたいと思います。

<安江玲子さん 1928年生まれ。終戦時、17歳だったが、「性接待」の犠牲に。その時のことがトラウマになり、苦しんできた。ハルエさんらに触発されて、メディアの取材には匿名で答えてきた。報道や本で伝えられたことで家族の知る所になる。家族の温かい支えで、笑顔を取り戻し、実名と顔を出して話せるようになった。80年の歳月がかかった>

<安江善子さん 1924年生まれ。2016年1月19日死去。一番年上だったことで、他の女性たちをかばい、最も多くの犠牲となった。「性接待」を決めた開拓団幹部、また帰国後の誹謗中傷に対して義憤を持ち、この事実を封印させてはいけないと幹部たちに働きかけ、「乙女の碑」の建立も主導した。佐藤ハルエさんとともに「性接待」の事実を公に告白。遺族会会長の藤井宏之さんに詳しく教えた>


<水野たづさん 1927年生まれ。最後まで「性接待」の犠牲を公にするのを拒んだ。佐藤ハルエさんや安江善子さんらといつも行動を共にしていた。2024年ハルエさんの死の後に、自身のことを話すようになる。「レッテルを貼られて生きるより正々堂々と生きていきたい」と話す>
7月19日、十三・第七藝術劇場での舞台挨拶。会場から一人の女性が手をあげた。女性は姉の話を始めた。
「私の姉は満州開拓団に行きました。家族で行きました。子どもと自分は方向がわからなくて、逃げ回って、苦労したと日本に帰って来てから話しました。それが私の姉です。私と24歳違います。逃げている時に、自分の子どもが背中で泣かなくなったから、死んでしまったと姉が言い、その子どもはどうしたんと聞いたら、その子はあそこに置いて行った、この話を聞いたのが私の頭に残っておりましたので、今日、この映画を観させていただいて、そういうことだったんだなあとわかって、なんとなしに、私の気持ちがすっきりしたというか、私も何もわからなかったんですけど、姉が満州の開拓団に行った、家が貧乏だから行ったんだということは、母親から聞いていましたから、だいたい、私もわかりました。ありがとうございます」
松原監督
「この映画を観ていただいた方の中に、満州から帰ってこられたご家族や親せきがいらっしゃって、今の時代と地続きだと思います。当時の状況を彼女たちは伝えたかったと思います」
女性
「日本での生活も、差別されて、かわいそうな人生でした」
松原監督
「当時のことを思い出してもらうことも、歴史を風化させないためにとても重要です。この映画をきっかけに一人一人の方に考えていただけることはありがたいです」
●『黒川の女たち』 7月12日(土)よりユーロスペース、新宿ピカデリー他全国順次公開。関西では十三・第七藝術劇場で7月19日より、京都シネマで7月18日より8月7日まで、神戸・元町映画館では7月19日から8月1日まで上映。公式サイトは以下のURL。

〇編集担当:文箭祥人
なお、冒頭の写真のコピーライツは©テレビ朝日
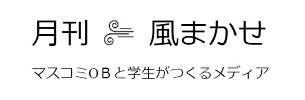






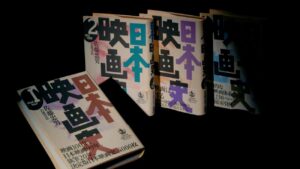

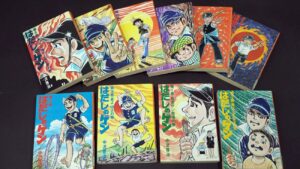









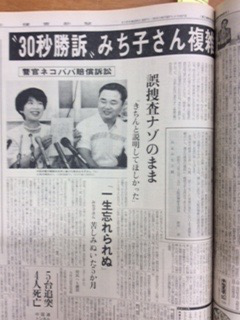

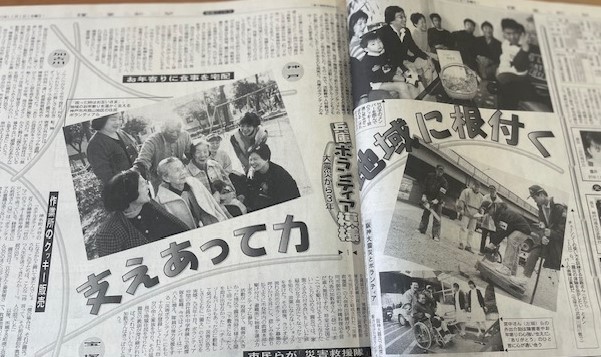
コメント