7月9日、大阪・十三の第七藝術劇場でドキュメンタリー映画「絶唱浪曲ストーリー」上映後、アフリカの芸能を研究する国立民族学博物館(民博)学術資源研究開発センター准教授の川瀬慈さんと川上アチカ監督によるトークイベントが行われた。その模様を報告します。

ドキュメンタリー映画「絶唱浪曲ストーリー」(冒頭の写真は港家小柳 ©Passo Passo + Atiqa Kawakami)
<浪曲師の独特の唸り声、エモーショナルな節回し、キレのよい啖呵。曲師の三味線とのスリリングなインタープレイが、初めて見る者の心をたちまち鷲づかみにする。平成生まれの浪曲師や曲師が育ち、女性の演者が増えた。浅草木馬亭の客席は昔ながらの愛好者と新たなファンが入り混じり、新時代の到来を予感させる。
主人公は、そんな浪曲の世界に飛び込んだ港家小そめ。伝説の芸豪・港家小柳に惚れ込み弟子入りした小そめが、晴れて名披露目興行の日を迎えるまでの物語だ。映画のもう一つの主役というべきは関東唯一の浪曲の常打ち小屋である木馬亭。舞台裏では、さまざまな人生が交錯し、ベテランから若手へと芸が継承されていく。
製作・撮影・監督は、川上アチカ。小そめと同じく小柳の虜になった川上は8年の歳月をかけて本作を完成させた。親密なキャメラは、小柳と曲師の玉川祐子、そして小そめが大切な何かを育んでいく様子を克明に写す。もちろん、迫力満点の口演場面も大きな見どころだ。玉川奈々福、玉川太福など、当代きってのスターたちも顔を覗かせ、たっぷりと楽しめるドキュメンタリー>
港家小柳の浪曲 フランスの映像作家が探し求めた<魂を震わせるような音>
川瀬さん
「国立民族学博物館でアフリカの芸能を研究しています。アチカ監督と会うのは5年振りぐらいです。まず、すごい世界を記録してくれて、我々に届けてくださって、ありがとうございます、と言いたいです」
「僕自身は文化人類学の研究者で、アフリカの路上の芸能を中心に研究しています。映画で描かれた、こういう浪曲の世界があることを全然、知りませんでした。それぞれのキャラクター、港家小柳さん、玉川祐子さん、沢村豊子さん、小柳さんに弟子入りした港家小そめさん、みなさんの潔さ、かっこよさ、立ち振る舞い、たたずまい、魅かれます。そこにまず、強烈な印象を受けました」
「民博には、世界の芸能を淡々と観察して記録した映像が多くありますが、それとは違うアチカ監督のスタイルがあって、分析を前提とした観察ではなくて、共にある、というかなあ、たたずんでいるような淡い感じで漂ってくるカメラワークというか、視点の近さというか、そこに衝撃を受けました」
アチカ監督
「私自身の物語ではないんですね。物語は向こう側にあって、私は媒体に過ぎない感じで、向こうから訴えかけてくる物語をどうやって自分のトンネルを通して、素直な形で出せるか、一番間違いのない形で出せるか、そういうことをやっていました。物語を受信している感じがすごく強かったと思います」
川瀬さん
「この浪曲という世界がアチカさんにやってきた、最初に起きたことはどんなことでしたか」
アチカ監督
「元々は、ヴィンセント・ムーンという世界中を旅して<魂を震わせるような音>を探しているフランスの映像作家が、日本でも探したいということで私に手伝ってほしいと連絡がありました。私は「やります」と返事をして探し始めました。2014年ごろのことです。この時、私は浪曲のろの字も知らなかったんです」
<Vincent Moon は、独立した映画制作者であり、サウンドエクスプローラーです。彼は過去 20 年間にわたり映画を制作しており、スタジアム ロック ミュージックから珍しいシャーマニックな儀式、エレクトロニクスの実験からアカペラ ヴィレッジの歌に至るまで、サウンドを求めて世界中を旅しています。彼は現在、古代の儀式と新しい形式の儀式の間のつながりを探求しています(Vincent Moon公式サイトから)>
「その中で、友川カズキさんという詩人で歌手で絵も描いている方で、私も好きなんですが、友川さんのライブに行った時に、ファンの人から「港家小柳さんはすごい人だから絶対、観た方がいいよ」と言われました。それで浅草にある浪曲の定席を訪ねました」
「小柳師匠の浪曲は、よいというもんじゃなかった、とんでもなくて、すご過ぎちゃって。この時、木馬亭は改装中で日本浪曲協会の畳の部屋で、お客さんは20人ほどで、みなさんご年配でした。三味線は沢村豊子師匠、お二人の一席を観たんです。それがなんというか、向こうの時代に連れてってくれちゃったんです。私がもう、江戸時代に居て、橋のたもとに立っているという、これ何だろうと。雪が降っているのも感じるんですよ。二人は丁々発止でやっていました。楽譜がないんで、即興でやり取りして、30分があっと言う間に過ぎて、もう完全にノックアウトされました。翌々日も観に行って、あの魔法が本当だったのか確認しに行きました。間違いないと思いました」
「芸能が社会の風穴を開ける」
撮影の許可が下りたが、ヴィンセント・ムーンが来日した時、小柳師匠が病に倒れ入院中。撮影は延期となった。その後、小柳師匠が復帰し、芸歴69年の会を開くことになる。しかし、この時、ヴィンセント・ムーンは日本を離れていた。
アチカ監督
「誰も小柳師匠の浪曲を撮る人がいない状況になりました。撮影すると手を挙げる人が誰かしら現れると思ったんですけど、現れなくて。自分でやるしかないと最終的に手を挙げました」

川瀬さん
「人生って、わからないものですね。ヴィンセント・ムーンとは14、15年の長い付き合いで、ヴィンセント・ムーンの作品は素晴らしいけれど、アチカ監督の、柔らかい、淡いタッチの長編作品にはならなかったと思います」
「アチカ監督が話した中に、「私がもう、江戸時代に居て、橋のたもとに立っている」と、「橋のたもと」というキーワードが出て来ました。日本の芸能に詳しい人はピンとくると思います。「橋のたもと」という、いわゆる「河原乞食」という言葉をみなさん、お存じだと思いますけど、小柳師匠の浪曲を観た時に、その場所、その時代に引きずられていくような気分を味わったという、まさに、芸能の原点、すごくコアな場所であり、部分であると思います」
アチカ監督
「小柳師匠は40年間、旅芸人をされていました。芸能の原点の放浪芸の世界にいた人で、放浪芸の中に入ってくる最後の人だと思います。放浪されていた時、顔をくしゃっとする1970年代のテレビで人気者だった、くしゃおじさんや盲目の浪曲師の大利根勝子さんと一緒にまわっていました。芸能が身体の弱い人に開かれていた時代です。小柳師匠も幼いころから右耳が聞こえないんです。沢村豊子師匠も身体が弱くて、家族から普通の仕事はむずかしいだろうということで、三味線を習わせられたと聞きました。小柳師匠、沢村豊子師匠はこういう時代の最後の人だと思います」
川瀬さん
「そういう時代は昭和40年代ぐらいまでですかね。瞽女(ごぜ)さんもそうだし、三河万歳、春駒…。寄席で経験を積むのではなく、移動する中で芸を培っていく」
アチカ監督
「地方であればわからないということで、すごい大看板で東京や大阪で人気のある芸人の名前を名乗って芸を披露するということもあったようです。東京の寄席に入った時、違う雰囲気を持った人が入ってきたということだったと思います」
川瀬さん
「胡散臭いというか、狡猾というか、そういう部分にぐっと来るし、芸能だなあと思いますよね」
アチカ監督
「そうなんです」
川瀬さん
「ステージ上の小ぎれいな洗練されたきれいなものを見せられるとは違う世界です」
川瀬さんは印象に残ったシーンがたくさんあるという。その中で小そめさんが移動中の新幹線で話すシーンを取り上げる。
映画で小そめさんはこう話す。
<「チンドン屋に入ったときも、(浪曲界と)同じような状況で、高齢の方が多かったです」「爺さん婆さんなんですけど、みんなパンクで烈しい。老人は大人しくて心が広いという概念を覆されまして…」「今の世の中はきれいできちんとしている反面、息苦しくてしんどい。だから昔ながらの人を見ると余計にいいなと思う」>
アチカ監督
「チンドン屋時代の小そめさんは大変なこともあったと聞きました。お店の中とかでも急に親方が怒鳴るとかしたそうなんです。それはチンドン屋がばかにされていた職業だったこともあるのかもしれないと小そめさんは言いました。だから、ばかにされちゃいけないという気持ちが親方のどこかにあったのではないかと。そういう気の荒い人たちと小そめさんはお付き合いされていて、でも、すごく正直で温かくて、みんなでご飯を食べたり、という世界にいたと思います」
川瀬さん
「芸能者であることに対する後ろめたさには普遍的なものがありますね。私自身、アフリカの吟遊詩人とずっと生活をしていますが、自分自身の立場から、なかなか音楽を生業にしていることを言えない、そういう人がたくさんいます。そういう世界に、小そめさんはぐっと魅かれたわけですね。そこがすごく興味深いと思いました。私自身が芸能に魅かれるポイントでもあるのかなあと思いました」
アチカ監督
「そこに魅かれるというのは、自分の中に、何か足りない部分があるということですか」
川瀬さん
「小そめさんが新幹線の中で話したようなことです。この社会、この世界において、すべて小ぎれいで、窮屈になっていって、良い意味での、猥雑さとか、いい加減さとか、社会の隙間のような感じとか、そういったものが足りない、息苦しくなっちゃう。芸能者という存在は、そういった中で、社会に風穴を開ける存在かもしれませんね」
アチカ監督
「なるほど」
川瀬さん
「これは日本だけの話ではありません。単に娯楽、エンターテインメントによって、みなさんを楽しませるだけでなくて、世界を異化してとらえる。言葉とか歌とか、あるいは、言葉と歌の中間ぐらいのもの、語りとも歌とも言えないようなもので、違った見方で社会に風穴を開ける。だから、あの新幹線のシーンは、目立たないかもしれませんが、ドキッとさせられました」
アチカ監督
「私もあのシーンはぐっときました」
川瀬さん
「すごく重要な、小そめさん自身の話を超えた、すごく大きなテーマだと思いました」
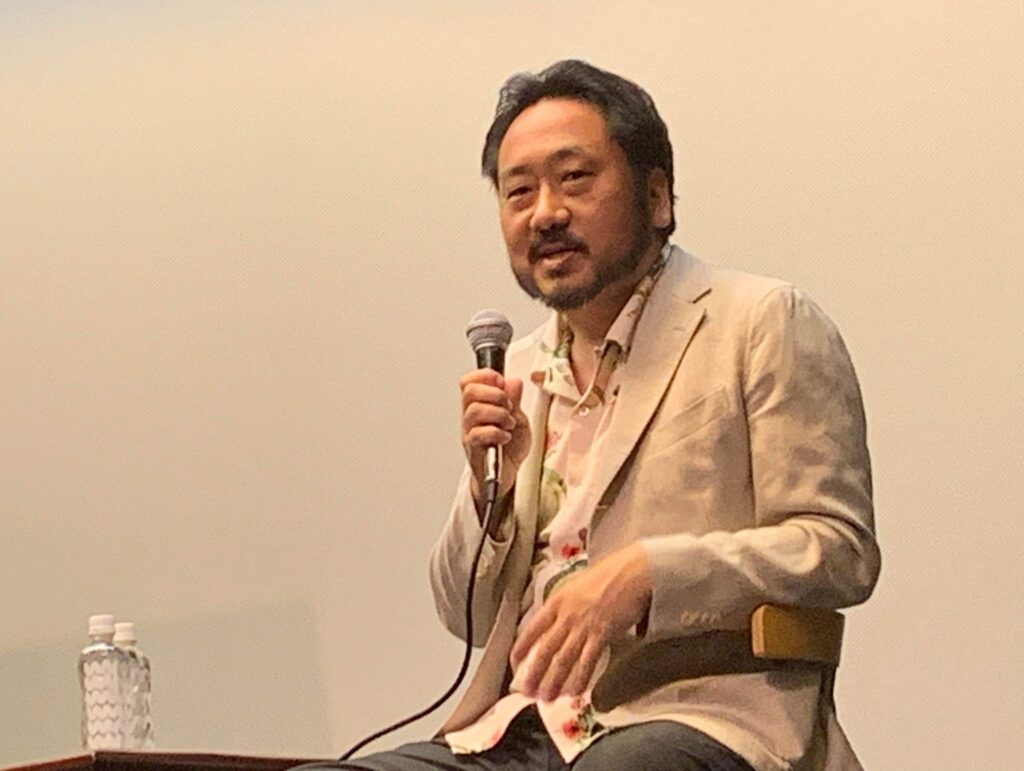
「路上こそが、芸能のゆりかご、芸能が生まれる場所」
アチカ監督
「今、SNSでちょっと間違ったようなことを言ったら、すごく叩かれたりします。若い世代の人に聞いた話ですが、今、レコードがすごく流行っていて、それは懐かしくて素敵だなあということではなくて、若い人たちが、もっと直接的で体感できる世界みたいなものを切実に求めている、と聞きました」
川瀬さん
「世界との直接的な接触ですよね。ステージの上から一方的にパフォーマンスを提供するのではなくて、浪曲師と曲師と観客の境も距離もないような中で呼応する、そうしたところで芸能が生まれてくるような世界」
アチカ監督
「浪曲のルーツは大道芸だったと。道でやっていた、道に芸能があった時代」
川瀬さん
「ほんとそうなんですよね。ステージの上から芸能をするのではなくて、むしろ、芸能者は、今会場でみなさんが座っているイスとイスの間をぬって、歩いて、歌って、踊って、そういう存在だったと思います。私自身、フィールドワークを続けているエチオピアで見る世界は、路上こそが芸能のゆりかごで、芸能が生まれてくる場所ですね。そこに私も魅かれていく。芸能というパッケージ化された商品があるのではなくて、むしろ、人と人との騙し合い、擦れ合い、芸能者は人間的に不安定だし、いい加減だし、狡猾だし、そこなんですよね。そういった芸能者が、生と死の味わい深い哲学を歌で語って、この世の無常を諭して、我々をほろっとさせる、でも、普段生活している姿をみると、どうしようもない奴ら、騙し合い、酒にも女にも弱い、男にも弱いような、そこなんですよね」
アチカ監督
「浪曲にはいい意味での野蛮さが残っているんじゃないかと思います」
「浪曲師も曲師もみなさん、かっこいい」
川瀬さんが次に取り上げたのは小柳師匠が舞台から降りるシーン。
川瀬さん
「小柳師匠は病気のことがあって、途中で声が出なくなって、「大変恐れ入りますが、今日はこれにて失礼させていただきます」と言って、舞台を降ります。小柳師匠の生き様、覚悟、プロフェッショナルをみたと思います。ミスを連発するのではなくて、ああいう形できちんとあいさつして退く、感動しました」
アチカ監督
「映画の公開直前、小そめさんがブログで、「弟子として見ると、つらい」と言ってくれました。私は、小柳師匠の生き様自体が浪曲だと感じていて、去り際も含めて小柳師匠の浪曲人生だと思っていて、あのシーンは撮影していてもつらかったし、編集していてもつらかったです。でも、小柳師匠が去るということがあって、今度は小そめさんが成長していく、そういうコミュニティーの在り方みたいなものを見させていただいたので、この映画にとって非常に重要だと思います」
川瀬さん
「映画は浪曲師の生活に踏み込んでいます。台所のシーンから、普段のなにげないやり取りも出て来ます。そういう中から芸能というものが育まれていく、そこがこの作品の突出したところですね」
アチカ監督
「すごく仲が良くて疑似家族みたいなんですけれど、根底の一番底に、浪曲界にいるもの同志の尊敬とか尊重とかが流れていて、馴れ合いにならないような、踏み込み過ぎないような、そういうところをしっかり持っていらっしゃるなあと感じて、それもかっこいいなあと思って見ていました」
川瀬さん
「みなさん、かっこいいですよね。浪曲師ももちろんですが、曲師の存在、曲師の役割、曲師の掛け声、玉川祐子師匠も沢村豊子師匠もすごいですね。20世紀中ごろのブルースの世界にも通じるようなものを感じました」

アチカ監督
「曲師の存在、すごいんです。沢村豊子師匠は9歳の頃、福岡に暮らしていて、そこに佃雪舟さんの浪曲の一座が巡業でやってきて、三味線ができる子はいないか、ということで豊子さんが楽屋で弾いたら、一緒に来ないかと誘われたんです。次の日には家族と別れて東京に出ていくと、今では考えられない世界ですよ」
川瀬さん
「今では信じられないですね」
アチカ監督
「9歳で自分の娘の命を預ける、命のあり方も違う感じがします。9歳から三味線を弾いてこられた豊子師匠の芸はものすごく説得力があるんです」
川瀬さん
「説得力と、凛としたというかスキッとしたというか、あのたたずまいは何なんですかね」
アチカ監督
「大先生も弾いてこられて、三波春夫さんも弾いてらっしゃいました。坂本冬美さんからも声がかかったりしています」
「木馬亭はまさにアジール」

話は木馬亭に。
川瀬さん
「木馬亭とは不思議な縁があるんです。木馬亭は最初、木馬館と呼ばれていた昆虫博物館でした。つくったのは名和靖さんという昆虫学者だった人で、日露戦争の戦勝記念として建てられました。名和さんは僕が暮らしている岐阜の人で、僕の家の近所に住んでいました。昆虫館からメリーゴーランドになって、それから木馬亭になったんです」
アチカ監督
「東京大空襲で浅草が焼け野原になった時、木馬館は唯一焼け残って、浅草の人たちがみんな、木馬亭に住んじゃったという話を聞きました」
川瀬さん
「アジールと言う言葉がありますが、まさにアジール。困っている人、困窮している人、病人、みんなが集まるスペースだったんだと思います」
アチカ監督
「木馬亭の前の席亭、根岸京子さんが映画に出て来ます。息子さんは映画監督の根岸吉太郎さんです。根岸京子さんは、道で生きていたバナナのたたき売りの芸能の価値を今の時代に押し出してくれた人だと聞きました」
川瀬さん
「根岸さんのたたずまいも、なんとも言えないものがありますね。映画で印象に残った根岸さんのシーンは、小柳師匠が最後に、「お世話になりました」と根岸さんにあいさつするシーンです」
アチカ監督
「この時、小柳師匠は相当、具合が悪かったと思いますが、席亭さんにごあいさつして帰らないと、そういう気持ちがものすごく強かったと思います。自分の芸を生かしてくれる場所に対する尊敬や感謝を常に持っておられました。昔はもっと、日本中に興業主さんがたくさんいたと思いますが、どんどんお辞めになって、そういう中で、木馬亭は続けています。玉川奈々福さんは、「木馬亭は浪曲師にとって、ものすごく大きなお城みたいな存在だ」と言います」
芸能そのものが生き物
芸の継承について。
川瀬さん
「血のつながりはなくても芸のつながりがある、芸の継承がこの映画の重要なキーワードだと思います」
小そめさんは2013年、44歳で小柳師匠に弟子入り。
アチカ監督
「2015年に撮影を始めた時は、小そめさんたちが一番下の世代でした。2019年頃は、浪曲に魅せられて東京芸大を卒業して入ってきた人がいます。新しい世代の人たちが最後のチャンスだと嗅ぎつけて、入ってくるんでしょうね」
川瀬さん
「おもしろい現象ですね。そういう人たちの活動が木馬亭で観られたり、なんらかのメディアに出てくればと思います」
アチカ監督
「この劇場の下の階にあるシアターセブンで毎月、十三浪曲寄席をやっています。真山隼人さん、京山幸太さんが出ています。隼人さんの三味線は沢村豊子師匠の一番弟子の沢村さくらさんです。豊子師匠の生き写しのように、豊子師匠の手をよく取られています」
真山隼人さんは1995年生まれ、京山幸太さんは1994年生まれ、沢村さくらさんは1974年生まれ。
川瀬さん
「新しい世代の浪曲はどう展開していくんでしょうか」
アチカ監督
「野性味みたいなものが残ってくれたらいいと思うんですね。ちょっとインテリっぽくなってくるじゃないですか」
川瀬さん
「これは重要な話だと思います」
アチカ監督
「浪曲は大衆に寄り添った芸能であって、弱きを助けとか、演目も義理人情の話や親を失った子どもの話とか。そういう世界を感情に直に訴えかけてくれるような感じやストリートで生きてきた芸能だという野性味が残っていったらいいなあと思います」
川瀬さん
「野性味というキーワードが出て来ました。芸を野性味たらしめるもの、いろいろな要素があると思いますが、即興的で言葉がバンバン出てくる、それも野性味の一つですね」
アチカ監督
「玉川奈々福師匠に聞いた話ですが、劇場や会場でお客さんが席を立つことは少ないけれど、ストリートであれば通り過ぎて行くわけで、その人たちの注目をずっと引き続けるため、たたみかけるような節や啖呵、たたみかけるような三味線、だから、浪曲の演目の中には、その野性味があるということなんです」
川瀬さん
「私自身、アフリカのストリートで芸能者たちの立ち振る舞いや営みを見ていて、もう、芸能は娯楽ではなくて、空間を支配する、ということですね」
アチカ監督
「はい」
川瀬さん
「音で、声で、喉で、つかまないといけない。それは強烈な技です。押しまくったら引くじゃないですか、押して引いての妙というか、芸の深さというか、そこが重要ですね」
アチカ監督
「浪曲師がセリフで泣いている時、三味線の音色も泣いているんです。色っぽい時もそうなんです。その場面を立ち上げていくような力みたいなもの」
川瀬さん
「空間を組み替えていくというか、それは力というか、魔術というか」
アチカ監督
「楽譜がないから盗むしかないんです。お弟子さんたちはそででみていて、指使いからなにから全部、一個一個盗んでいく。師匠たちもどんどん盗みなさいと言うんです」
川瀬さん
「浪曲の継承において、楽譜がないことも、重要な部分かもしれませんね」
アチカ監督
「メソッド化されていない、メソッド化しない、だからお弟子さんたちは「わからない」の繰り返しだそうです。師匠たちも、細かい説明ができないけれど、「違う」と言うことは言えるそうです。玉川奈々福さんは若い頃、師匠に「違う」、「違う」と言われ続けて、でも、何が違うかが、わからなかったそうです。ずっとやり続けていくうちに、何年かした時に、「あ!これが違うんだ」とわかると話していました。こういう学び方は、すごいなあと思いました」
川瀬さん
「アフリカは、そちらが主流です。メソッド化、成長化はないに等しい。むしろ、口承芸は口承で、身振り手振りで伝わっていきます」
アチカ監督
「体から体へ、移し取っていくということですね」
川瀬さん
「芸能そのものが生き物であって、体から体へホップしていく。芸能が生き物であって、芸能者は媒体、そうやって芸能は生き残っていく。媒体の働きかける力が弱かったり、いい加減だったりすると、芸能という生き物は廃っていく。逆に、100年200年というブランクを経て、いきなり蘇ったりします。活性化することもあります」
映画のワンシーン。

<小柳師匠が自室のベッドに臥せっていた。部屋にはたくさんのカセットテープがあった。その一つを小そめさんがラジカセにかける。小柳師匠の威勢のいい啖呵と三味線の烈しい音が鳴りだした。二人、じっと耳を傾ける。おもむろに小柳師匠の左手が動き出した。テープから流れる音に呼応して、布団の下の小柳師匠の身体が躍動していた>
アチカ監督
「小柳師匠の中に入っている浪曲という生き物が動いているのが見えたんです」
川瀬さん
「印象的なシーンでした。今アチカ監督の話を聞いて、美しいシーンであり、なるほどと思いました」
アチカ監督
「小柳師匠の息遣いが見える気がしたんです。小柳師匠は30分間、たたみかけるようにやっていて、どこで息つぎをしているのかわからないぐらいの芸だったんです。息づかいの秘密みたいなものが手の動きに見えたような気がしました。この手の動きを見たら、小そめさんは学べることがたくさん、あるんじゃないかと思って見ていました。最後に、小柳師匠が小そめさんにみせてくれた舞台だったんじゃないかと思いました」

〇「絶唱浪曲ストーリー」公式サイト
●木馬亭
http://mokubatei.art.coocan.jp/
〇日本浪曲協会
●十三浪曲寄席

〇「100歳で現役!女性曲師の波瀾万丈人生」(玉川祐子/著)
●「浪曲は蘇る 玉川福太郎と伝統話芸の栄枯盛衰」(杉江松恋/著)
http://www.harashobo.co.jp/book/b596901.html
〇川瀬慈ホームぺージ
http://www.itsushikawase.com/japanese/index.html
●ぶんやよしと 1987年毎日放送入社、ラジオ局、コンプライアンス室に勤務。2017年早期定年退職
























コメント