2月5日、大阪・十三の第七藝術劇場で、ドキュメンタリー映画「新生ロシア1991」上映後、ジャーナリストの金平茂紀さんとネットで結んで、トークイベントが行われた。その模様を報告します。
最初に、「1991」年のソ連の状況を振り返る。
共産党書記長となったゴルバチョフ(在任1985~91年)が、情報公開や言論の自由化、市場経済の導入などペレストロイカ(改革)を進める。1989年12月、ゴルバチョフは、アメリカ大統領ブッシュ(父)と会談を行い、冷戦終結を宣言、国内でも翌年、共産党一党独裁を放棄した。しかし、政治的自由化による連邦諸国の独立の動きや市場経済化による市民生活の混乱などで政権は安定しなかった。そして、1991年8月19日、ペレストロイカに反対する共産党保守派がゴルバチョフを軟禁し、軍事クーデター宣言する。クーデターは3日間で終わり、逆に急進改革派が勢いを強める中で、12月には全共和国が連邦離脱を宣言して、ソ連共産党も解党した。こうしてソ連は消滅した。

「新生ロシア1991」は、8人のカメラマンが混乱するレニングラード市中にまぎれて撮影した映像を再構成した。レニングラード市民は、モスクワで起きた緊急事態に困惑し、街にあふれた。ついには宮殿広場に8万人が集まり、共産党支配との決別を決意。「ソ連8月クーデター」に揺れながらも、ロシアの自由のため立ち上がったレニングラードを映し出す。監督は、ウクライナ侵略戦争後、世界が最も注目するセルゲイ・ロズニツァ。
金平茂紀さん。ジャーナリスト。早稲田大学大学院客員教授。沖縄国際大学非常勤講師。
1977年TBS入社。以降 モスクワ支局長、ワシントン支局長、「筑紫哲也 NEWS23」編集長、報道局長などを歴任。2010年より「報道特集」キャスター。2022年9月でレギュラー退任。以降 同番組の「特任キャスター」に。2004年度ボーン上田記念国際記者賞受賞。2022年度外国特派員協会「報道の自由賞」受賞。
『新生ロシア1991』に映し出された、プーチンの映像
冒頭、金平さんは、会場にこう質問する。
「最初に、お聞きしたいことは、映画にプーチンが出てきたシーンをどのくらいの人が気付きましたか」
急進改革派の旗手でレニングラード市長サプチャークの側近を務める、若かりし頃のプーチンの姿が映っている。

「当時のレニングラード市長のサプチャークは、このクーデターを認めることはできないと、市民に呼びかけます。その時、サプチャークが会場に入っていきますが、まるで陰のように寄り添っていたのが、ウラジミール・プーチンです。「ワロージャ、ワロージャ」とサプチャークがプーチンに呼びかけていますが、「ワロージャ」はウラジミールの愛称です。いかにサプチャークがプーチンを頼りにしていたかがわかるシーンです」
「サプチャークが会場から出てくるシーンにもプーチンが出てきます。プーチンは、サプチャークの真横にいるんですが、顔を覆って出て来ます。これが特徴的です。インテリジェンス、つまり諜報関係の仕事をしている人は、本能的に自分の顔が出ることが嫌なんです。だから、顔を隠しているんです。サプチャークの下で何をやっていたか、その前にどんな仕事をしてきたのか、おのずと、ばらしているんです」
「サプチャークの路線が、ロシア全体を引っ張っていく力になっていたらとしたら、今のようなことは起きなかったと思います。サプチャークは、その後、原因不明の死を遂げるんです」
「ソ連8月クーデター」 モスクワ中心部にソ連軍戦車 街頭に集まるモスクワ市民
金平さんは、1991年8月19日のクーデターのとき、モスクワにいた。
「TBSのモスクワ支局長として、仕事をしていました。まさか、この日にクーデターが起こるとは、夢にも思いませんでした。8月19日は、ロシア人にとって夏休み期間中です。僕は、この年の3月にモスクワに行ったばかりで、5か月しか経っていませんでした。モスクワ支局に働いているロシア人たちは「ロシアは労働者の国で必ず1か月間は夏休みをとるのが当たり前、8月は休みます」と。その中で、何人かのロシア人は僕の仕事を手伝ってくれていました。実は、日本のテレビ局や新聞社、通信社の支局長は夏休みを取って、モスクワを離れていました」
この日のことを、こう振り返る。
「モスクワの中心街に戦車が来たんです。朝起きると、ガーという音がして、次々と戦車が来ました。住んでいたアパートの横の通りはクレムリンに直行する大きな通りで、そこを戦車が通るわけです。それでも、クーデターという言葉は、頭に浮かびませんでした。道路を渡ってすぐのところが職場だったのですが、読売新聞のベテラン記者に出会い、「なんですか、これは!?」と聞くと、「クーだ」と。それで、クーデターだと思って、あわてて情報収集を始めて、職場に泊まり込んで仕事をしました。あんなに寝なかった日はないぐらいでした」
この時のモスクワ市内の様子。
「モスクワ市民は街に繰り出したんです。エリツィンがトップだったロシア共和国の最高会議ビルを守るために、市民が集まってバリケードを作り始めるんです。最高会議ビルは、戦車が通っている大通りから歩いて、5分か10分ぐらいのところです。そこで撃ち合いがあったりしました。この時、市民が「保守派のクーデターを許さない!」と立ち上がって、ものすごい数の人たちが、最高会議ビルを守るためにバリケードを作って、守りました。この時、みんなが掲げたスローガンは、<свобода(スワボーダ)>です。自由という意味です。「自由だ!自由だ!」と」
クーデターが起こり、テレビはニュース速報の代わりに、チャイコフスキーの「白鳥の湖」を全土に流した。
「映画を観ていると、レニングラードの人たちはラジオを聞いています。なぜかというと、テレビ局はすぐに保守派に抑えられたんです。御用放送しか流さなかったわけです。だからラジオです。モスクワでも、「モスクワのこだま」というラジオ局を聞いて、みんなが街に出てきたんです」
ロシアのウクライナ侵攻後、注目を集めるロズニツァ監督作品
『新生ロシア1991』の監督は、セルゲイ・ロズニツァ。ウクライナ侵略戦争以降、世界が最も注目すると言われる監督。金平さんは、一連のロズニツァ監督作品について、こう話す。
「ロズニツァ監督の、『ミスターランズベルギス』、『バビ・ヤール』、『ドンパス』の一連の映画や、スターリンの国葬を扱った『国葬』、スターリン時代にでっち上げて改革派を弾圧した裁判を扱った『粛清裁判』、これらの映画を劇場で観て、すごいなあと思いました。ウクライナ出身のロズニツァ監督が、映画を通して、まさに訴えかけている最中に、ロシアのウクライナ侵攻が起き、ロズニツァ監督が見つめようとしたことの大きさに、ものすごく引き付けれられました」
ロズニツァ監督作品。
日本では2020年、『国葬』(2019)、『粛清裁判』(2018)、『アウステルリッツ』(2016)の3作品が群衆ドキュメンタリー3選と題して初公開され、注目を集めた。2022年、ロシアによるウクライナ侵略戦争の勃発をきっかけに、『ドンパス』(2018)を緊急公開。『ドンパス』は、2014年からウクライナ東部ドンパス地方で繰り広げられた親ロシア派とウクライナとの戦争の実相を描いたフィクション。9月、『バビ・ヤール』(2021)を公開。第2次世界大戦中、独ソ戦の最中、ウクライナ首都キーフの郊外で起きたバビ・ヤール大虐殺を描いたアーカイブ・ドキュメンタリー、33,771人のユダヤ人が射殺される過程と、その後の歴史処理を描く。そして12月、『ミスターランズベルギス』(2021年)を公開。1980年代後半から91年のソ連崩壊まで、超大国ソ連を相手に粘り強く戦い、祖国リトアニアを独立に導いた初代リトアニア元首で音楽家、現代の英雄、ランズベルギス氏が文化的抵抗と政治的闘争を語るドキュメンタリー。
金平さんは、ロズニツァ監督作品は重要だと語る。
「そもそも、ロズニツァ監督作品がなぜ、重要か。映画が突き付けているものを考えないと、なぜロシアがかつての兄弟国のウクライナに侵略戦争を仕掛けたのか、その本質的なことがわからないと思います。正義のウクライナに邪悪なロシアが侵略して、正義が勝たなければいけない、だから正義側に武器をどんどん供与して、勝つまで応援しよう、そんな単純な話ではありません」
「ロシアは過去、『新生ロシア1991』に描かれているように、圧政や独裁的な体制が続くことに対して、市民が街頭に出て、闘ったわけじゃないですか。それがどうして、ロシア政府はウクライナに対して国境を越えて軍を送り、ウクライナに住むかつての仲間の住民を殺すのか、そこをちゃんと考え抜かないと、今起きていることはなくならないと思います」
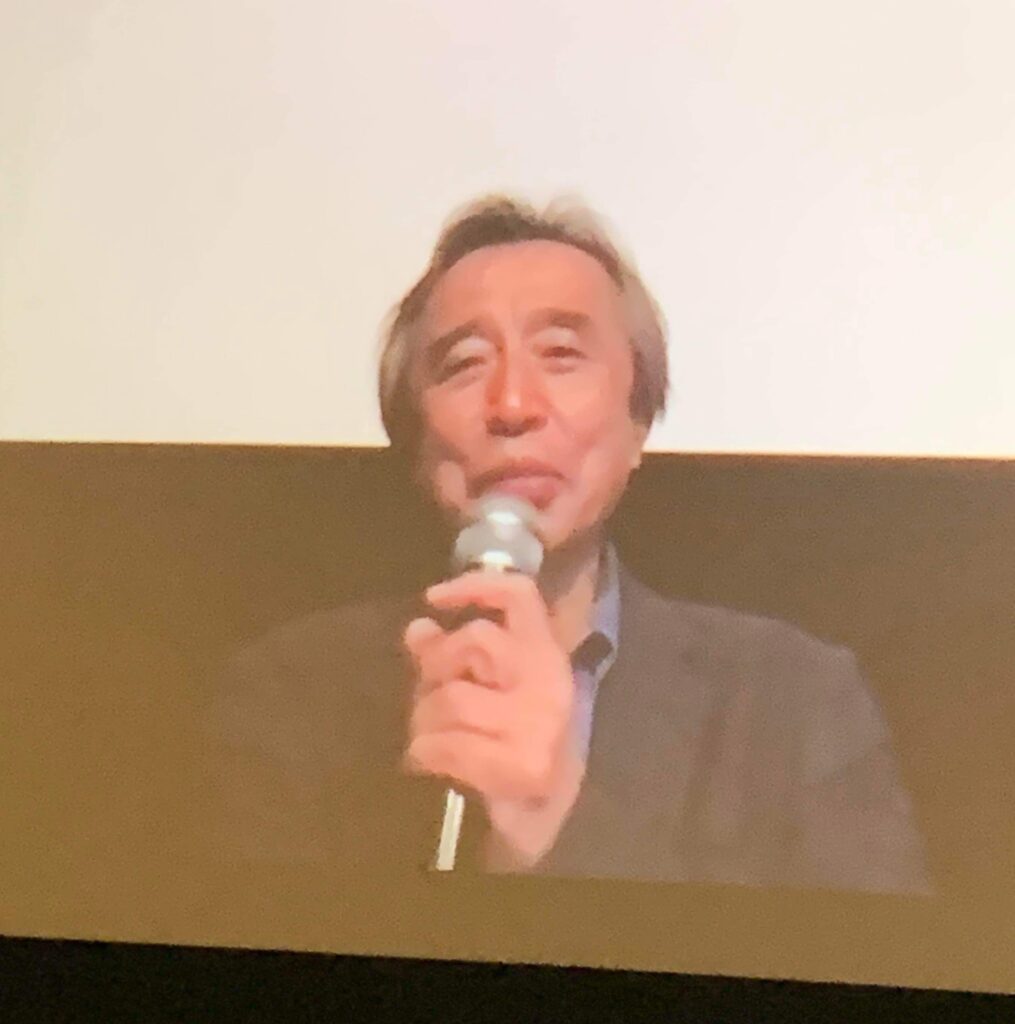
ロシア人は邪悪なのか
今モスクワ市民はどうしているのか、年末年始、金平さんはモスクワに向かった。
「実は、昨年の年末から正月、モスクワに行きました。ごく普通のモスクワ住民がどう暮らしているのか、自分の目で見たいと思ったからです。暮らし向きを見る限り、困っていないし、物は余っているし、何が悪いの?という感じでした。こうした人たちが多数派であることに、ものすごくショックを受けました。もちろん、限られた日数で、観光客として行ったので、本当のところ、ロシア人がどう考えているのか、わかりません。『新生ロシア1991』が映すクーデター阻止に立ち上がった経験を持つロシア人が今でも多くいることはわかっています。おそらく、物を言う知識人やインテリは国外に出て行ったりしたでしょう。ただ、モスクワに住んでいるごく普通の人たちは、ロシア語しかしゃべれません、ロシアで生きていく以外、選択肢がないわけです」
そして、こう会場に問いかける。
「ロシア人全員が、邪悪な人たちですか、無力な人たちですか、権力や強い力に対して隷従して黙っていた方がいいと思っている人たちですか、それは民族的な属性ですか。日本人の方が、ましですか、日本人の方が権力に対して立ち向かって体を張ってでも自由を守るということに優れた民族ですか。僕はそうは思いません。ロシアの人たちに中にも、ものすごく、悲しんでいる人たちもいるし、国外に逃れざるを得なかった人たちもいるし、国内にも、今黙っていても必ず変わらないといけないと思っている人がたくさんいると思います。そういう人たちと連帯していく。ウクライナに武器供与することは、本質的な意味での連帯と逆の方向に行ってしまう恐れはないのか、考えるべきだと思います」
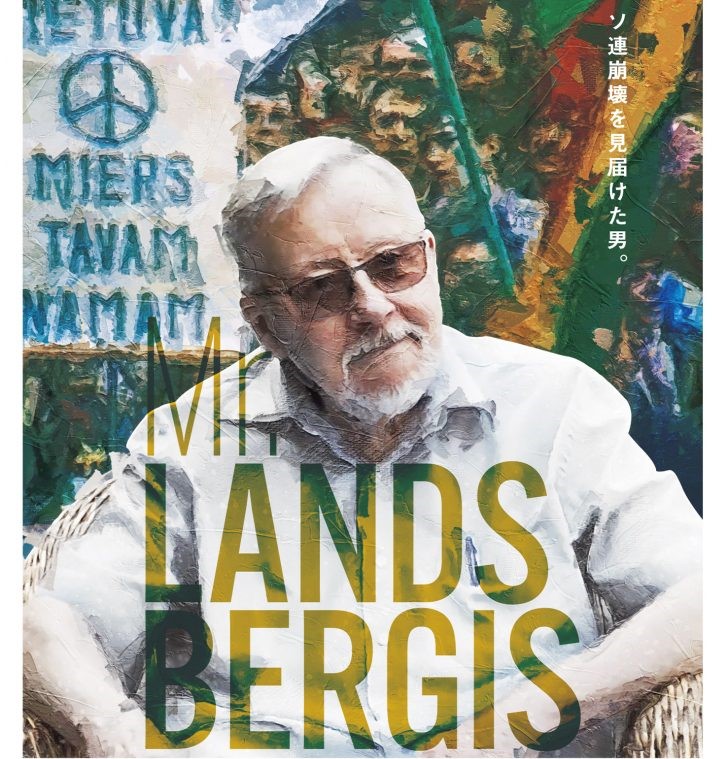
ウクライナ避難民を受け入れるリトアニア
ロズニツァ監督作品『ミスターランズベルギス』は、祖国リトアニアをソ連からの独立を導いた初代リトアニア元首ランズベルギス氏のインタビューと独立運動の映像で構成したアーカイブ・ドキュメンタリー。その中に、1991年1月11日から13日までの「血の日曜日事件」の映像がある。最高会議を死守するため多くの市民が集まりバリケードを作るが、13日、テレビ塔を守備する市民にソ連軍は発砲し、13人が死亡。
金平さんは、この事件の現場にいた。
「「血の日曜日事件」が起こった時、リトアニアの首都ヴィリニュスにいたんです。「血の日曜日事件」が起きた直後、モスクワからロシア人スタッフ3人とヴィリニュスに向かいました。ヴィリニュスのホテルに泊まろうとした際、ホテルのフロントで「ロシア人は出ていけ!」と言われ、途方に暮れました。探し回って、なんとか泊まることはできました。ヴィリニュスはソ連軍に市民が殺された直後でしたから、すごかったです。ランズベルギスがたてこもっていた最高会議ビルのバリケードを見て、今考えると、現代芸術のような感じでした。普通の市民が作り始めたバリケードです。レニングラードやモスクワのバリケードもすごかったですけど、ヴィリニュスのバリケードもすごかったです」
「血の日曜日事件」の国葬が忘れられないと話す。
「思い出すのが、国葬です。「血の日曜日事件」の後、国葬が行われ、立ち会ったのでよく覚えています。まったくの沈黙でした。道路という道路に、ヴィリニュスの市民がわっと全員立ち並んで、そこに棺が運ばれてきて、市民は涙を流していました。この光景は昨日のことのように覚えています。去年のだれかの国葬や、ロズニツァ監督作品のスターリンの「国葬」と、なんと違うことか。ヴィリニュスの国葬を見て、こういう形で、国民が自分の仲間が死んだことに対して弔意を表するのだと、涙が出てきました」
リトアニアは、ウクライナからの避難民を受け入れている。
「ランズベルギスはアーチスト、音楽家です。彼を指導者として持っていたリトアニアという国が、実はウクライナからの避難民の受け入れ国として、一番、きちんと機能しています。ポーランドはウクライナと過去にいろいろなことがあって、複雑です。リトアニアの人たちは、自分たちがソ連から独立した時に流した血のことや、ソ連からの介入を経験したことから他人事ではありません。だから、ウクライナからの避難民の受け入れが機能しているんです」
ロシアによるウクライナ侵略戦争はこれからどうなるのか
「改革派の旗手であったサプチャークの真横にプーチンがいたシーンは、いろいろなことを考えさせられます。サプチャークが死んで、プーチンはロシア共和国のエリツィンの側近になって、KGB部門のトップに昇りつめます。プーチンが権力を手中にした時、エリツィンは酒浸りでアル中状態でした。普通、側近であれば、アルコールを止めるよう言うはずですが、おそらくプーチンはそうしなかったでしょう。しかも、権力を一旦、手に入れると、そのうまみを根っから知ってしまっている、絶対に手放そうとしない。権力を手放した瞬間、自分が粛清される、自分がやったことの裏返しを自分がされることを恐れています。だから、プーチンがいる限り、今の戦争は終わらない、かなり長く続くと思います。その犠牲はロシア人であり、ウクライナ人です。ロシアの内側から、この戦争を止めさせないといけないと変わるには、たいへん長い時間がかかると思います」
「僕は戦争を考える時には、正義の戦争はないと思っています。正義の戦争って、戦争をやっている側は、いつも自分たちの戦争が正義だと言っていますから、正義の戦争はないと思っています。戦争の本質は、殺し合い、敵を殺せ、ということ。止めた方がいい。武器供与を含めて、止めさせた方がいい。僕は武器供与することに反対です、このことを含めて、殺し合いを止める、殺すな、とずっと言い続けないといけない」
映画のパンフレットに、配給会社サニーフィルムの有田浩介さんがこう書いている。
「ロズニツァ監督は兼ねてからロシアは旧体制の犯罪行為を罰することをしなかったため、結果、国家を運営する権力者が変わっただけで独裁国家だった過去から本質的に変われなかったと主張しています。ソ連崩壊から25年の節目に現在のロシアを見つめるためロズニツァ監督が作った『新生ロシア1991』は、ウクライナに対して侵略戦争を仕掛ける現在のロシアを考える上で重要なコンテクストだと思い公開に踏み切りました」
金平さんもこう話す。
「ロズニツァ監督が作品を作り続けてくれたお陰で、ソ連とは何だったのか、プーチンが率いているロシアはいったい何か、考える材料をずっと与え続けてくれています」
●映画情報など 配給会社サニーフィルム
〇ぶんや・よしと 1987年MBS入社。2021年2月早期退職。 ラジオ制作部、ラジオ報道部、コンプライアンス室などに在籍。 福島原発事故発生当時、 小出裕章さんが連日出演した「たねまきジャーナル」の初代プロデューサー






















コメント